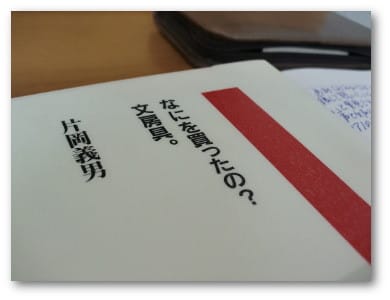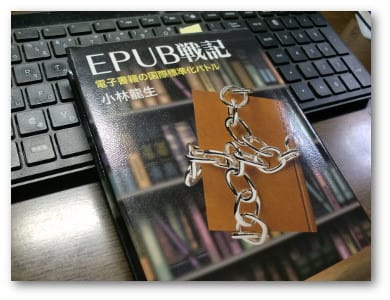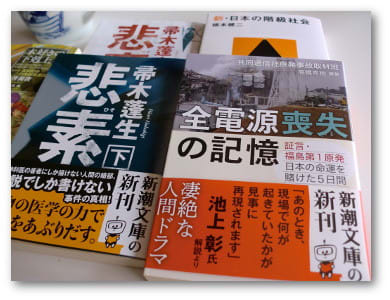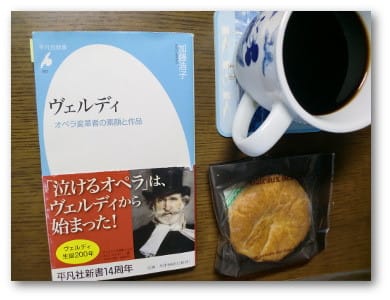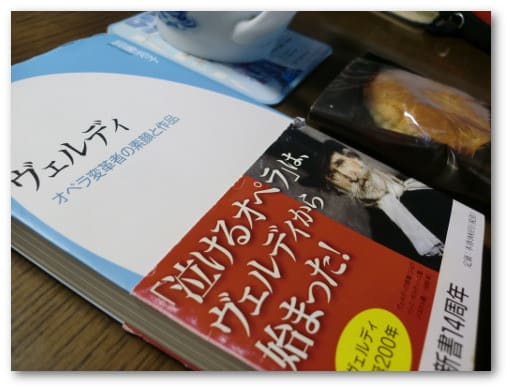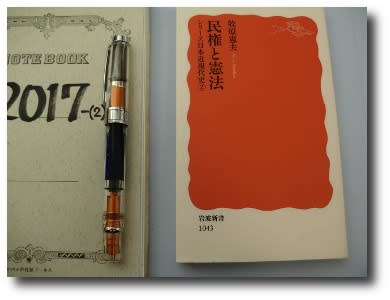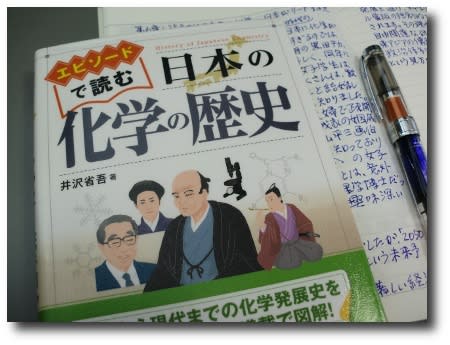人間ドックのおともに、肩の凝らない本を借りようと図書館にでかけ、片岡義男著『なにを買ったの?文房具。』というのを見つけて来ました。2009年に東京書籍から刊行されており、カラー写真をふんだんに使い、著者の文房具観をまじえて紹介されます。登場する文房具はほとんどが舶来製品で、このあたりは著者の嗜好性の現れでしょう。
こうした文具を写真で眺めながら、ふと思ってしまうのは、ツバメノート以外には私の趣味嗜好と重なるものはない、という点です。ボールペンはパーカーのジョッターではなく三菱のジェットストリームやパワータンクを愛用していますし、鉛筆と消しゴムで原稿を書いたり推敲したりするよりは、パソコン上のテキストエディタで済ませたい方です。著者には申し訳ないことながら、接点は限りなく少ない本でした。
○
ただし、一つだけ共感したのは、ノートブックを大量に購入して保管している点。なんと、本棚にいっぱい十年もののノートが並んでいるらしい。まあ、著述を業とする人には大事な商売道具の一つでしょうから、ある意味では当然のことなのですが、いろいろなノートが本棚にたくさんストックされ、よりどりみどりで選べるというのは羨ましいかも(^o^)/
でも、私の場合、いろんなノートに数ページだけ書き散らして、あちこちに放置してしまいそうだなあ(^o^;)>poripori
- 鉛筆、鉛筆削り、消しゴム
- 色鉛筆、クレヨン、色チョーク
- 輪ゴム、定規
- ボールペン
- ルーズリーフ、ノートブック
- カード、封筒
- 紙クリップ
- 糊
- ステープラー
- ハサミ
- 切手帳
こうした文具を写真で眺めながら、ふと思ってしまうのは、ツバメノート以外には私の趣味嗜好と重なるものはない、という点です。ボールペンはパーカーのジョッターではなく三菱のジェットストリームやパワータンクを愛用していますし、鉛筆と消しゴムで原稿を書いたり推敲したりするよりは、パソコン上のテキストエディタで済ませたい方です。著者には申し訳ないことながら、接点は限りなく少ない本でした。
○
ただし、一つだけ共感したのは、ノートブックを大量に購入して保管している点。なんと、本棚にいっぱい十年もののノートが並んでいるらしい。まあ、著述を業とする人には大事な商売道具の一つでしょうから、ある意味では当然のことなのですが、いろいろなノートが本棚にたくさんストックされ、よりどりみどりで選べるというのは羨ましいかも(^o^)/
でも、私の場合、いろんなノートに数ページだけ書き散らして、あちこちに放置してしまいそうだなあ(^o^;)>poripori