引き続き、日曜日(27日)の赤塚植物園です。

クヌギ(椚/櫟)の木にどんぐりが出来ました。

まだ緑色です。

やがて熟すと茶色になり地面に落ちます。

どんぐりは漢字では「団栗」と書くそうです。
どんぐりとはブナ科の果実の俗称です。

現代ではあまり食べませんが、食べられます。
どんぐり粉など食材としても用いられます。
縄文人はどんぐりを好んで食べていたようです。
ノウゼンカズラ(凌霄花)の花もまだ咲いています。

ピークは過ぎましたが、今年は長い期間咲いています。

引き続き、日曜日(27日)の赤塚植物園です。

クヌギ(椚/櫟)の木にどんぐりが出来ました。

まだ緑色です。

やがて熟すと茶色になり地面に落ちます。

どんぐりは漢字では「団栗」と書くそうです。
どんぐりとはブナ科の果実の俗称です。

現代ではあまり食べませんが、食べられます。
どんぐり粉など食材としても用いられます。
縄文人はどんぐりを好んで食べていたようです。
ノウゼンカズラ(凌霄花)の花もまだ咲いています。

ピークは過ぎましたが、今年は長い期間咲いています。

赤塚植物園の野草の道です。

ツルボ(蔓穂)の花が咲きました。

ツルボはキジカクシ科の植物です。

薄紫色の穂状の花が並んで咲いて可愛らしいです。

ハイ、ポーズ!仲良くツーショット??

秋に咲くシモバシラ(霜柱)の花も咲き始めました。

まだまだ暑いですが、秋の気配が感じられます。
引き続き、赤塚植物園の万葉薬用園です。

キンミズヒキ(金水引)の開花が進みました。

小さいですが、黄色い花が目を引きます。
キンミズヒキはバラ科の植物です。

一方、本園にある梅園の近くではミズヒキ(水引)の花がたくさん咲いています。

こちらは赤い花です。

ミズヒキはタデ科の植物でキンミズヒキとは全くの別物です。
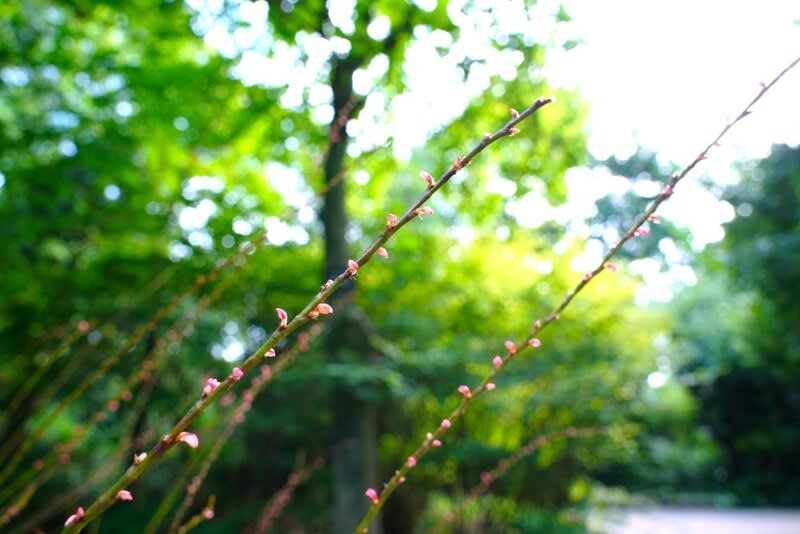
よく見れば花の形も全く違います。
赤塚植物園の万葉薬用園です。

ガガイモ(蘿藦)の花がたくさん咲きました。

イモと言ってもイモは出来ません。

それどころか地下茎には毒があるそうです。
池の畔ではタマアジサイ(玉紫陽花)の花の開花が進みました。

玉の様な蕾が名の由来です。
最後はナンバンギセル(南蛮煙管)です。

ミョウガの根から養分を拝借しながら次々に出てきます。

板橋区小豆沢にある薬師の泉です。

久々に訪れました。

入口では秋の七草のオミナエシ(女郎花)の花がお出迎え・・・。
キバナコスモスの花も咲いています。

お目当てのシュウカイドウ(秋海棠)はまだ咲き始めたばかりです。

見頃はまだ少し先の様です。
サルスベリ(百日紅)の花が見頃です。

白とピンクの花・・・。

サルスベリの下にはタマスダレ(玉簾)の花が咲いています。

ヒガンバナ科の植物でタマスダレと言う名前からに日本に自生する植物かと思いきや、南米原産の植物で明治時代に持ち込まれたそうです。

直ぐ横には中山道(国道17号)が通っている街中の小さな庭園ですが、年間を通していろいろな植物が楽しめます。


再び、赤塚植物園の万葉薬用園です。

カツラの木の下・・・。

葉の緑がきれいです。

カツラの葉が日差しを遮ってくれるので少しはマシですが、この日は湿度が高く蒸し暑いです。
本園へ戻って池の畔へ・・・。

コバギボウシ(小葉擬宝珠)の花がたくさん咲いています。

秋の花、サワギキョウ(沢桔梗)の開花も進みました。

秋の花らしい控えめな花です。

伸びたシラヤマギク(白山菊)にセミの抜け殻が付いています。

シラヤマギクの花が咲くのは、もう少し先です。
赤塚植物園の野草の道です。

タカサゴユリ(高砂百合)の花が咲いています。

存在感があります。

タカサゴユリは園内にいくつかの場所で見られましたが、他の場所は終わってしまいました。

今年はこの一輪で見納めになりそうです。

野草の道の中頃ではタイワンホトトギス(台湾杜鵑草)の花が咲き始めました。

タイワンホトトギスもユリ科の植物です。
これから秋に向けて沢山見られる花です。
辺りにはセミの声が響いています。

アブラゼミですね。

引き続き、20日(日)の赤塚植物園です。

アベリアの花がきれいに咲いています。
街中や公園などでよく見かける花です。

中国原産のスイカズラ科の低木です。
サネカズラ(実葛)の花も咲いています。

アベリアに負けず可愛らしい花です。

秋になると赤い実をつけます。(下の写真)

再び、万葉薬用園です。
オケラ(朮/白朮)がひっそりと咲いています。

見た目とは裏腹、キク科の植物です。

同じキク科のコウヤボウキの花に似ています。(下の写真)

コウヤボウキの花は秋に咲きます。
最後は季節外れのタチバナ(橘)の花です。

タチバナはミカン(ミカン科)の仲間です。

引き続き、赤塚植物園の万葉薬用園です。

ノカンゾウ(野萱草)の花が散水されたしぶきを浴びています。

滴をまとってきれいです。
キンミズヒキ(金水引)の花が咲き始めました。

細長い花序に黄色い花がたくさん咲きます。

ホオズキ(酸漿)の実が真っ赤に熟しています。

風船の様な袋の中には小さな丸い実があります。
一方、クチナシの実は緑色です。

熟すとオレンジ色になります。

今回は赤塚植物園の万葉薬用園で咲いている小さな花々です。

ガガイモ(蘿藦)の花が咲きました。

ガガイモはキョウチクトウ科のつる性の植物です。

毛で覆われた小さな花・・・。

まるでフェルトで作られた様な花です。

続いては紫色の小さな花です。

メハジキ(目弾き/茺蔚)の花です。

シソ科の植物で以前、紹介したシロネの花(下の写真)と似ています。

その近くにはゲンノショウコ(現の証拠)の花が咲いています。

メハジキもゲンノショウコも見過ごしてしまいそうな目立たない花です。

昨日(20日)の赤塚植物園です。
南側の角のボタンクサギ(牡丹臭木)の花がきれいに咲いています。

外側の道沿いからしか見ることが出来ません。

園内にあるボタンクサギの花は1か月以上前に終わってしまっておりますが、この場所だけは毎年遅くまで花が残っています。
万葉薬用園に入るとヤブラン(藪蘭)の花が目につきます。

紫色でラベンダーみたいな花ですが、香りは殆どありません。

ヤブランと言ってもラン科ではなく、キジカクシ科の植物です。
池の畔ではタマアジサイ(玉紫陽花)の花が咲き始めました。

アジサイ科の植物ですが、8月から9月にかけて咲きます。
最後は奥のミョウガの葉の下に出てきたナンバンギセル(南蛮煙管)です。

先日、紹介した花は萎れてしまいましたが、新たに蕾が出てきました。
暗い場所なので感度をISO6400まで上げて撮影しました。
ISO6400で写真が撮れるなんてフィルム時代では考えられません。
赤塚植物園の入口の池の畔でサワギキョウ(沢桔梗)の花が咲き始めました。

名前の通り、キキョウ科の植物です。

風に揺られて靡く姿は涼しげです。

コバギボウシも然り・・・。

涼しいのは見た目だけで台風の影響で蒸し暑いです。
池の畔のタカサゴユリは終わり、ガマ(蒲)の穂だけが残っています。

ソーセージの様です。

この歩にはタンポポの様な綿毛(種子)がたくさん詰まっているのです。
最後はサワギキョウ、コバギボウシの紫の花つながり・・・ヤブラン(藪蘭)です。


赤塚植物園のブラシノキに花が咲きました。

台風の影響により突然雨が降ってきたのでウェルカムセンターの軒下で雨宿りししているとブラシノキに花が咲いているのを発見しました。

本来は4月から5月にかけて咲くのですが、再び咲き始めました。

結構、本格的に咲いています。

元々、オーストラリア原産の樹木であるため、日本の気候に戸惑っているのかも知れません。
秋に花が咲くこともあります。
万葉薬用園ではノカンゾウ(野萱草)の花がきれいに咲いています。

雨で潤っておりオレンジ色が鮮やかです。

14日(月)の赤塚植物園です。

台風の影響により時折雨が降るあいにくの天気です。
日が差したと思ったら突然の豪雨・・・。

ケヤキ広場の直ぐしたではタカサゴユリ(高砂百合)がたくさん咲いています。

雨粒をまとってさいています。

きれいです!

ユリの花の下にセミの抜け殻が付いています。

こんな先っぽで羽化したようです。

こちらのユリにも・・・。

赤塚植物園の万葉薬用園で今年もナンバンギセル(南蛮煙管)の花が咲きました。

ミョウガ(茗荷)の葉の下でひっそりと咲いています。

ナンバンギセルはハマウツボ科の植物でミョウガの根に寄生して育ちます。

他にもススキ、イネ、サトウキビなどのイネ科の植物の根にも寄生します。
ナンバンギセルは葉緑素を持たないので光合成ができません。

そのため、他の植物の根に寄生して養分を拝借しています。