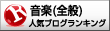◆前日の受付風景

 「奈良マラソン2010」で晴れてサブ4ランナーの仲間入りができました。家内もベストタイムで完走。
「奈良マラソン2010」で晴れてサブ4ランナーの仲間入りができました。家内もベストタイムで完走。
 快晴。絶好のマラソン日和。
快晴。絶好のマラソン日和。 スタート時刻9時の予想気温は8℃。12時で14℃。朝はけっこう寒かった。エントリー17,760人(内フルマラソン10,997人)のうち受付したランナーの数は15,495人(内フルマラソン9,991人)。鴻ノ池陸上競技場は広くて立派だったが、さすがに大変な混雑。これまでに走った、いびがわ、能登和倉、北海道と比べても最も盛大でにぎやかな会場だった。
関西のマラソン大会は初めて。雰囲気の違いが面白かった。なんといってもにぎにぎしく騒々しい。
8:30までに荷物を預け、8:45分までには所定のスタートブロックに並ばなくてはならない。シューズとソックスの選択に迷いがあった。8時過ぎ、今日履く予定の新しい靴とソックスで少し走ってみる。ソックスに違和感があり履きかえる。
そうこうしているうちに8:15。もう荷物をまとめて預けなくてはならない。アップで少し身体は温まったとはいえ、すぐ冷えてしまいそうな寒さだ。ビニール袋をかぶることにする。
荷物を預けてすぐトイレに並んだが、なかなか順番は回ってきそうにない。焦っても仕方ないので、身体を動かしながら待つ。知らない振りして横から入ろうとする人が何人かいたが、関西だろうが関東だろうがさすがにそれは許してもらえない。
どうにか用をすませるともう8:40。あわてて走りだすが、建物の外はまだ簡易トイレに並ぶ人であふれていた。
 半分はQちゃんのおかげ。
半分はQちゃんのおかげ。 時間に間に合い「D」ブロックに並ぶと、スタートセレモニーというわけで、Qちゃんこと高橋尚子さんや知事の話がスピーカーから聴こえてくる。
その中のQちゃんのアドバイスが、このレースの中で大いに役立った。
「後半失速しないようにするためにはとにかく前半脚を使わないこと。身体を前傾させると自然に脚が前に出ますよね。そういう感じで走るとあまり脚を使わなくても走れる。30㎞、35kmになって初めて脚を使って地面を蹴って一生懸命に走るんです」
そうか!とわたしは(心の中で)手を打った。それが骨盤前傾だな、と。今年の「いびがわマラソン」のフルを初めて走った金哲彦さんがこう書いていた。
「前半予定よりスピードが出過ぎていて、『これは後半失速するパターンかな』と思ったが、失速しなかった。骨盤前傾を意識し続けていたからだと思う」
言葉としての骨盤前傾は何となく意味がわかったがマラソンを走るのに具体的にどうしたらよいのかよくわからなかった。Qちゃんの話を聴いても、「身体を前傾させることを意識して走る」という程度のことしか思いつかず、効果的に走りに採りこめるあてはなかったが、そのことを忘れないようにしようと思った。
 いよいよスタート。
いよいよスタート。時計のスタートボタンを押す準備をしながら待ったが、時間になってもピストルが聴こえない。ランナーがのろのろ動き出したからスタートしたのだろう。スタートラインもわかりにくい。ランナーからはアーチの「スタート」の文字が見えないからだ。Qちゃん、せんとくん、知事の前を通って、ここがスタートかとみんなゆっくり走りだす。ここまで4分余りのロス。
走りはじめたら、思ったよりは動ける。「いびがわ」のようなことはない。道幅は広い。沿道は観客で埋まっている。いよいよだと気持ちが高揚する。
今回はタイム狙い。最低でもサブ4は達成したい。チャレンジ・タイムは3時間28分。
エントリーした時には、せっかくの奈良、古都の名所を堪能しながら半ばファンランでいいと思っていたが、勝負レースの「いびがわ」が怪我や病気で不本意なタイムだったために、この奈良で今年の総決算を行うことになった。今年走った2,500kmを無駄にするわけにはいかない。
 最初の5㎞は26:16。
最初の5㎞は26:16。結局、目標タイムをクリアしたのは、最初の5㎞までだった。出だしの1㎞を7分で想定していたので、スムーズにスタートできたということだけによるタイム・ゲイン。
2km過ぎまでビニール袋をかぶったまま走る。日向が続き身体が温まったので、破り捨てて沿道の係員に捨ててもらうように預けた。
右手、ふと見た通路の先に朱雀門があった。思い返しても、コースの一部になっていた天理教関連施設を除けば、奈良を代表するような観光施設・風物で記憶にあるのは、この朱雀門と鹿くらいなものだ。今回はとにかくレースに集中していた。
 距離表示
距離表示いつものように1㎞ごとにラップを取っていたが、序盤から何度か表示を見落としたほか、アップダウンが頻繁にあるとはいえ、イーブンペースを維持しているつもりなのにタイムにバラツキがありすぎる。
タグによる計測装置の位置と距離表示がけっこうずれているし、電柱とかガードレールとか表示板をくくりつける場所がないところには表示板は設置されていない。
また、10㎞のコースと一部かぶっているせいだと思うが、どうやら距離表示を見誤ったりもした。
以上のことから、「今回はラップタイムはあまり参考にできない」と早めに判断して、より自分の体感ペースを信じて--というかその状況でのベストを尽くすことに集中できたのも良かった気がする。
 完璧な準備のつもりが唯一の「うっかり」
完璧な準備のつもりが唯一の「うっかり」10㎞過ぎあたりから、すでに足の裏や指に違和感。少し痛い。「ヤバイ。マメができてるなあ」。いくらなんでも早すぎる。
慣らしの足りない新しいシューズのせいだ、とはこの時は考えもしなかった。これこそが今回唯一のミス。全然思い至らなかった。つま先が当たって黒爪になリやしないかということばかりを気にしていた。
ついでにいうと、フルの場合はいつも必ず塗りこんでいたワセリンも塗るのを忘れた。
レース3日前、ただ1回の試走でこのシューズとユニクロのコンフォートソックスの組み合わせがあまりにもしっくりしていたことで油断していたんだと思う。
小出監督の本にも「厚手のソックスのほうがマメができにくい」と書いてあり、このソックスはまさにぴったり当てはまる。この日最初に履いていたCW-Xのソックスは比較するとやや薄くできていて、今回シューズとの組み合わせではクッション性が足りないのではないかと判断した。
準備段階でもっと何度も試しておくべきだった。
 いつになく冷静に作戦変更
いつになく冷静に作戦変更
目標では15㎞でこのレースの目標ペース=4分40~50秒/㎞に到達し32km(つまり残り10㎞)までこれを維持。その時点の状態で判断し、いけそうならそのまま40kmまでなんとか同じペースで粘るというよう、自分の実力からすればかなり高い目標を掲げていたのだった。
10㎞通過が52分30秒。スタートから5㎞、5㎞から10㎞とともに5分15秒/㎞のペース。10㎞から15㎞はほぼ下りだったせいだと思うが5分06秒/㎞とペースアップ。
(不正確かどうかはこの際措くとして)1㎞ごとのラップでは、目標の5分/㎞前後を目指して何度か4分台のラップも刻んでいた。まだ序盤だし苦しくて仕方がないというわけでもない。マメのせいだけでもない。
マラソンは30km、いや35kmまでは我慢が鉄則だ。ここで15秒/㎞以上もペースを上げて終盤まで維持する走力は今の自分にはないと、ここまでの走りと身体の状態からはっきりとわかったのだった。
ペースアップではなく、5分10~20秒/㎞のペースを30㎞過ぎまでキープしよう、そう思い直した。

■後篇■に続く。