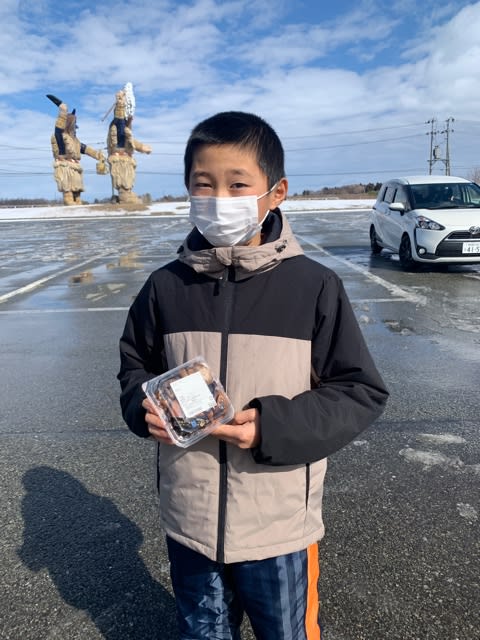

道の駅で購入した黒ニンニクを食べたり弁当食べたり!


久々の水族館でお魚三昧!

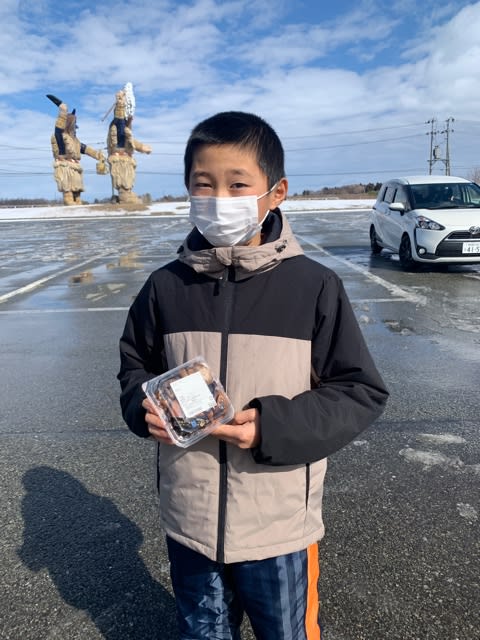




山菜ソムリエの備忘録NO.1ノカンゾウ
春トップバッターの山菜は、ふきのとうの後くらいに採れ出すのがカンゾウです。
初夏になるとオレンジ色のユリに似たノカンゾウの花が咲きます。
ノカンゾウの花は万葉集にも「わすれぐさ」の名で詠まれたロマンチックな植物です。
ここでは、ノカンゾウの特徴・食用としての効能についてまとめてみました。

ノカンゾウと同じ種でヤブカンゾウがあります。
芽が出たときは、全く区別が付きません。食べても同じ味だし効能もあまり変わらないようです。
花が一重か二重の違いですね。
ノカンゾウはユリ科ワスレグサ属の多年草です。日本中の山野によく見られる野草で、土手や川辺から高山まで自生します。
鳥海山ろくどこでも普通に生息していますよ。
河原の土手を見ていけば確実に見つけられます。
花期は6月〜8月で草丈は50〜80cmほどになります。花はユリの花の形をした橙赤色や茶褐色などで、朝開き夕方にはしぼむ「一日花」です。
ノカンゾウ(野萱草)の名前の由来
「ノカンゾウ」(野萱草)という和名は中国のホンカンゾウに似てよく野原にみられるという意味から、漢名(中国の植物名)の「萱草」(カンゾウ)に野原の「野」をつけて「野萱草」(ノカンゾウ)になったようです。

葉や新芽はクセがなく柔らかいので、生で食べることもできます。
火を通すことでほんのりと甘みが増します。
つぼみは、やや酸味のあるアスパラのようで美味しいと評判で、花も湯がくとシャキシャキとした食感になります。
ノカンゾウの蕾は、茹でて、マヨネーズを付けて食べるのがベストだと思っています。
春一番のご馳走ですが、実はとても素晴らしい効能があります。
ノカンゾウには利尿作用・解熱作用があるだけでなく、むくみや不眠・うつ症状を改善する効能もあるとされるんです。
昔は薬として使っていたのです。
根・蕾・若芽など用いる部分の違いよって効能も少し異なります。
花が咲く前に全草収穫して乾燥させると、ハーブティでも楽しめますよ。
6月~7月にかけて採取したノカンゾウの蕾を天日干しにし乾燥させた生薬を「金針菜」(きんしんさい)といって中華料理の食材として袋で売られているものもあります。
自分は花になる前に収穫してしまって、金針菜にしたことはありませんね。
ノカンゾウの若芽・花・蕾は甘みがあってとても美味しいです。春には若芽、初夏には花・蕾が食べられます。
蕾は、熱湯でえ1分ほどさっと湯がいて、みずにさらして、好きなドレッシングでどうぞ!本当に癖がなくて、ほんのり甘くいくらでも食べられます。

おひたしに飽きたら、豚肉と一緒に炒めてもおいしくいただけます。
更に天ぷらも絶品です。
酢味噌和えも酒のあてには最高ですよ。
 中華スープとして煮込んでもおいしくいただけます。
中華スープとして煮込んでもおいしくいただけます。
ノカンゾウは、一日花であるがためのはかなさや、美しさに心を寄せて歌人たちがたくさん歌を詠んでいるんです。
わすれな草でもあります。
ノカンゾウの花を見かけたらしばし立ち止まって眺め、憂いを忘れてみたいものですが、私はすぐに収穫してしまいます。
