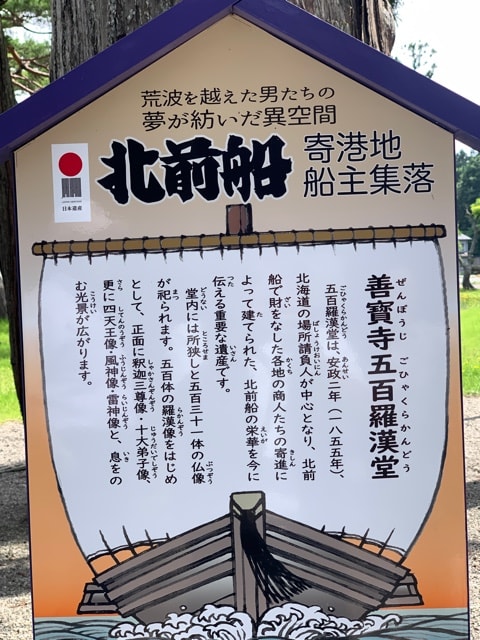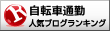昨日は海士剥の専念寺の役員会でした。
鎌倉時代に承元の法難という事がありました
これは、法然上人の弟子たちが念仏集会に参加したことがきっかけです。
奈良の興福寺が朝廷に念仏禁止を訴えていた頃、法然上人の弟子である住蓮と安楽が念仏集会を開催しました。その集会に後鳥羽上皇の女官数名が参加し、念仏こそ救いの教えであると確信して髪をおろしてしまったのです。
怒った後鳥羽上皇は念仏宗を弾圧
このことを知った後鳥羽上皇は激怒し、興福寺の訴えを受け入れてしまいます。そして、承元元年(1207年)に風紀を乱すものとして念仏宗を弾圧し、住蓮と安楽を含む4名を死罪、法然上人ら7名を流罪にしました。
親鸞聖人、越後へ流罪となる
親鸞聖人も流罪となり、越後国(現在の新潟県)へ配流されました。これが「承元の法難」と呼ばれる事件です。当時、法然上人は75歳、親鸞聖人は35歳でした。
師弟の別れと再会を誓う歌
師弟の別れに際し、親鸞聖人は
会者定離(えしゃじょうり) ありとはかねて聞きしかど きのう 今日とは思はざりしを
と詠みました。
一方、法然上人は
別れゆくみちははるかにへだつとも こころは同じ 花のうてなぞ
と詠んでいます。
二人は今生の別れを悲しみながらも、次はお浄土で再会することを誓ったのです。
承元の法難の影響
承元の法難は念仏宗にとって大きな打撃となりましたが、その後の浄土真宗の広まりに大きな影響を与えたと言われています。弾圧によって念仏宗への弾圧が強まる中で、親鸞聖人は念仏の教えをより多くの人に伝えるために尽力しました。
京の京都からすれば上越が流罪の地という事です。それ以降なんども弾圧を受けていてその度に北方教化がなされています。
日本海沿岸に一向宗が散らばったということです。
自分の家の総本家は加賀屋姓なので,石川から流れてきたと言えます。