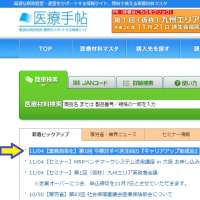● 1か月60時間を超える法定時間外労働
1か月60時間を超える法定時間外労働においては、割増賃金の率が現行の25%から50%へと引き上げられました(ただし、中小事業主については猶予措置が設けられ、当面の間適用を除外されます)。
実務的には、給与の計算方法の変更とともに、就業規則または給与規程の変更が必要です。
なお、通達で法定時間外労働には法定休日労働は含まれないことが示されています。
● 36協定に注意
時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(いわゆる「限度基準告示」)として原則月45時間、年間360時間が定められています。これを超える36協定を締結する(いわゆる「特別条項」を設ける)場合、基準を超える時間外労働に対する割増賃金を定めるよう義務化されました(中小事業主も義務です。猶予措置はありません)。したがって、協定内容の変更が必要です。
● その他、実務対応で求められるもの
改正労基法の施行に伴って、その他の実務的な対応で求められるのが労働時間の適正把握です。長時間労働を抑制するために割増率を引き上げたのですから、この労働時間の把握が不適切であれば何の効果も期待できません。したがって、労基署は、労働時間の適正把握に関する監督指導を強めることは間違いないでしょう。企業としては、労働時間の適正把握ができる仕組みをつくるとともに、法定時間外労働を少しでも短縮する対策を講じる必要があります。
1か月60時間を超える法定時間外労働においては、割増賃金の率が現行の25%から50%へと引き上げられました(ただし、中小事業主については猶予措置が設けられ、当面の間適用を除外されます)。
実務的には、給与の計算方法の変更とともに、就業規則または給与規程の変更が必要です。
なお、通達で法定時間外労働には法定休日労働は含まれないことが示されています。
● 36協定に注意
時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(いわゆる「限度基準告示」)として原則月45時間、年間360時間が定められています。これを超える36協定を締結する(いわゆる「特別条項」を設ける)場合、基準を超える時間外労働に対する割増賃金を定めるよう義務化されました(中小事業主も義務です。猶予措置はありません)。したがって、協定内容の変更が必要です。
● その他、実務対応で求められるもの
改正労基法の施行に伴って、その他の実務的な対応で求められるのが労働時間の適正把握です。長時間労働を抑制するために割増率を引き上げたのですから、この労働時間の把握が不適切であれば何の効果も期待できません。したがって、労基署は、労働時間の適正把握に関する監督指導を強めることは間違いないでしょう。企業としては、労働時間の適正把握ができる仕組みをつくるとともに、法定時間外労働を少しでも短縮する対策を講じる必要があります。