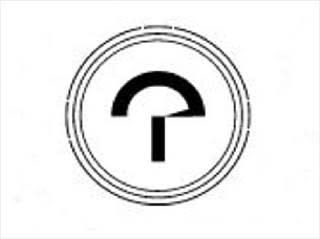浜田市(はまだし)は島根県西部の日本海を望む位置にあり、東は江津市、邑南町、西は益田市、南は広島県に隣接しています。中国山地が日本海まで迫り、また、切り立ったリアス式地形と砂丘海岸の織り成す海岸線は、優れた自然景観と天然の良港をもたらし、山陰有数の水産都市として知られています。「市の木:桜」「市の花:ツツジ」「市の魚:ノドグロ」を制定。

キャッチフレーズは「青い海・緑の大地 人が輝き文化のかおるまち」

市の伝統芸能「石見神楽」が有名で、市内の各所では通年を通して神楽が演じられ、浜田駅前に設置された「どんちっち神楽時計」が観光客を出迎えてくれます。

明治22年(1889)、町村制の施行により、那賀郡浜田町・石見村・長浜村・美川村・周布村・井野村・大麻村・三階村、伊南村・大内村・漁山村(いさりやまむら)・周布村(すふむら)・上府村・下府村・国分村が発足。
1923年、那賀郡石見村が三階村、伊南村大字後野と合併、改めて石見村が発足。
1935年、那賀郡大内村、漁山村が合併、美川村が発足。
1940年、那賀郡浜田町・石見村・長浜村・美川村・周布村が合併、浜田市が発足。
1941年、那賀郡上府村、下府村、国分村が合併。国府村が発足。
1951年、国府村が町制を施行、那賀郡国府町となる。
1955年、那賀郡国府町と有福村が合併、改めて国府町が発足。
1955年、浜田市が那賀郡井野村の一部・大麻村の一部を編入。
1958年、浜田市が那賀郡金城村の一部を編入。
1969年、浜田市が那賀郡国府町を編入。
2005年、旧浜田市、那賀郡三隅町、旭町、金城町、弥栄村が合併、改めて浜田市が発足しました。
マンホールには、海洋館アクアスの「シロイルカ」と、「浜田マリン大橋」が描かれています。


「浜田マリン大橋」

消火栓には、石見神楽の代表的な演目である「鍾馗」がデザインされています。

「鍾馗より、玄宗皇帝と疫病神」

仕切弁には、これも石見神楽の最も代表的な演目である「八岐大蛇退治」がデザインされています。

「須佐之男命の八岐大蛇」

2006年2月23日制定の市章は、「波頭の図案が「浜」を、中央の十字星は輝く未来を表し、同時に全体として里山にある「田」の文字を表徴している。」HPより



中央に「浜田ガス社章」のハンドホール蓋

撮影日:2012年11月9日&2019年4月17日
------------------------00----------------------
2018年8月11日、第8弾として全国76自治体で76種類(累計364自治体418種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「浜田市」のマンホールカードは、「浜田市役所西分庁舎3階 下水道課」でいただけます。
2001年に設置開始されたマンホールには「浜田マリン大橋 」「 石見畳ヶ浦 」と「 シロイルカ 」がデザインされています。

「このマンホール蓋のデザインは、合併前の旧浜田市において、下水道をより身近なものとして関心と親しみを持っていただくため、広く市民の皆さんからデザインを公募し、2001年から旧 浜田市 のマンホール蓋として採用しています。 マンホール蓋の中央には 、浜田市 の市章が大きく描かれ、その外側に日本海をイメージした波の模様、内側には浜田市を代表する観光名所の一つであり、国指定文化財の「石見畳ヶ浦」、中四国最大級の水族館しまね海洋館アクアスの「シロイルカ」、県内唯一の特定第3種漁港の指定を受けた浜田漁港に架かる「浜田マリン大橋」が描かれています。」
訪問日:2019年4月19日