13日(月)。昨日の日経「The STYLE / Culture」面の「文化時評」に同社編集委員・瀬川奈都子さんが「『芸術で食べていく』ということ」というテーマで書いています 超訳すると、
超訳すると、
「新型コロナウイルス感染症のまん延は、はからずも社会におけるアーティストの役割を再考する契機となった まず事象として表れたのはライブイベントの自粛による補償問題。続いて『ステイホーム』を促しファンを癒すオンライン活動の数々
まず事象として表れたのはライブイベントの自粛による補償問題。続いて『ステイホーム』を促しファンを癒すオンライン活動の数々 そして検察庁法改正案の成立見送りを後押ししたSNS上での言論。社会の中でアーティストは、もろさと強さを併せ持つ存在だと、私には映った
そして検察庁法改正案の成立見送りを後押ししたSNS上での言論。社会の中でアーティストは、もろさと強さを併せ持つ存在だと、私には映った 尚美学園大学などで教える林容子さんは『画家、音楽家などを目指す教え子は今、卒業後に食べていけるか不安になっている
尚美学園大学などで教える林容子さんは『画家、音楽家などを目指す教え子は今、卒業後に食べていけるか不安になっている 』と指摘する。コロナ対策で絵を売るギャラリーは閉鎖され、イベントの自粛は巨額の損失を招いた
』と指摘する。コロナ対策で絵を売るギャラリーは閉鎖され、イベントの自粛は巨額の損失を招いた 『どうすればアーティストとして生活できるのか、社会にとって芸術はなぜ必要なのかを、学生はこれまで以上に考えている』と語る。確かに『芸術で食う』のは厳しい。緊急事態宣言下の4月、日本芸能実演家団体協議会(芸団協)が実施した調査によると、俳優や音楽家らの7割以上が『新たな仕事の依頼はまったくない』と答えた
『どうすればアーティストとして生活できるのか、社会にとって芸術はなぜ必要なのかを、学生はこれまで以上に考えている』と語る。確かに『芸術で食う』のは厳しい。緊急事態宣言下の4月、日本芸能実演家団体協議会(芸団協)が実施した調査によると、俳優や音楽家らの7割以上が『新たな仕事の依頼はまったくない』と答えた 宣言は解除されたが、いつ同様の状況に陥るか分からない
宣言は解除されたが、いつ同様の状況に陥るか分からない もともと、創作や表現活動だけで生計をたてられる人は一握りだった。国内の文化・芸術活動を経済的な自立度で区分すると、エイターテインメントビジネスが上位にあり、下位に素人の趣味の活動がある。中間にひしめくのが副業でしのぐプロの活動だ。芸団協常務理事の福島明夫さんは『児童対象の劇団や地方オーケストラなどで収入を得ているが、それだけでは食べていけない人々。日本の芸術家は大半がこの中間層にいる』と分析する
もともと、創作や表現活動だけで生計をたてられる人は一握りだった。国内の文化・芸術活動を経済的な自立度で区分すると、エイターテインメントビジネスが上位にあり、下位に素人の趣味の活動がある。中間にひしめくのが副業でしのぐプロの活動だ。芸団協常務理事の福島明夫さんは『児童対象の劇団や地方オーケストラなどで収入を得ているが、それだけでは食べていけない人々。日本の芸術家は大半がこの中間層にいる』と分析する そもそも『芸術家』は職業なのだろうか。西欧ではルネサンス以降、王侯貴族や裕福な商人が芸術家の庇護者となる時代が続いた
そもそも『芸術家』は職業なのだろうか。西欧ではルネサンス以降、王侯貴族や裕福な商人が芸術家の庇護者となる時代が続いた 貴族社会が終わりを告げると、国家がその代わりを担う構図が出てきた。最たるものが旧ソ連などの社会主義体制下での芸術活動だ。国の威信を示すのに利用できる芸術家には、仕事も住む家も名誉も、国が与えた
貴族社会が終わりを告げると、国家がその代わりを担う構図が出てきた。最たるものが旧ソ連などの社会主義体制下での芸術活動だ。国の威信を示すのに利用できる芸術家には、仕事も住む家も名誉も、国が与えた 今日、職業芸術家は市場経済のなかで生きる。活動を継続するには、切符や作品を買ってくれるファンが必要だ
今日、職業芸術家は市場経済のなかで生きる。活動を継続するには、切符や作品を買ってくれるファンが必要だ 税金で支援してもらう場合も、やはり多くの国民のコンセンサスが必要になる。社会での存在意義を認めてもらえなければ支えてはもらえない。その存在意義とはなにか。芸術はしばしば『炭鉱のカナリア』に例えられる。鋭敏な感覚で世のよどみをいち早く察知し、警告し、意識改革を促す
税金で支援してもらう場合も、やはり多くの国民のコンセンサスが必要になる。社会での存在意義を認めてもらえなければ支えてはもらえない。その存在意義とはなにか。芸術はしばしば『炭鉱のカナリア』に例えられる。鋭敏な感覚で世のよどみをいち早く察知し、警告し、意識改革を促す 『役にたつ』ことが芸術の目的ではないもかもしれない。だがあえて『職業』とするならば、芸術家は自らの居場所をもとめて社会に発信しなければならない。社会の側も失う前に、その価値に気づかなければならない
『役にたつ』ことが芸術の目的ではないもかもしれない。だがあえて『職業』とするならば、芸術家は自らの居場所をもとめて社会に発信しなければならない。社会の側も失う前に、その価値に気づかなければならない 」
」
瀬川さんが指摘する「もともと、創作や表現活動だけで生計をたてられる人は一握りだった」という事実には重いものがあります 音楽で言えば、名の知れたソリストになるには、国内外のその道のオーソリティーに師事するなり、世界的なコンクールに入賞するなり、とにかく実力を客観的に証明しなければなりません
音楽で言えば、名の知れたソリストになるには、国内外のその道のオーソリティーに師事するなり、世界的なコンクールに入賞するなり、とにかく実力を客観的に証明しなければなりません またオーケストラの楽団員になりたくても、定員が決まっているので、欠員が出ないとオーディションが開かれません
またオーケストラの楽団員になりたくても、定員が決まっているので、欠員が出ないとオーディションが開かれません 「競争率が激しい」みたいな生易しい問題ではないのです
「競争率が激しい」みたいな生易しい問題ではないのです
一方、毎年毎年 いったい何人の学生たちが音楽大学や大学院を卒業・修了していくのだろうか・・・そのなかで、自分が志望したところに”就職”でき「芸術で食べていける」学生は何人いるのだろうか
瀬川さんの「あえて『職業』とするならば、芸術家は自らの居場所をもとめて社会に発信しなければならない。社会の側も失う前に、その価値に気づかなければならない」という主張は、まったくその通りで、芸術を発信する側も、それを受け取る側も、心しなければならないことだと思います
ということで、わが家に来てから今日で2112日目を迎え、アメリカのトランプ大統領は軍の病院を視察し、初めて公の場でマスク姿で現れた というニュースを見て感想べるモコタロです

いま 病院でマスクを付けるのは世界の常識! ニュースになること自体が異常だ





ティータイムです 先日、人気作家・中山七里氏 御用達の成城石井オリジナル「プレミアム チーズケーキ」を買ったつもりが、アーモンドとレーズンが入っていない方を買ってしまったので、今回はよく見て購入しました
先日、人気作家・中山七里氏 御用達の成城石井オリジナル「プレミアム チーズケーキ」を買ったつもりが、アーモンドとレーズンが入っていない方を買ってしまったので、今回はよく見て購入しました やっぱりこちらの方が味の幅が広がり美味しいです
やっぱりこちらの方が味の幅が広がり美味しいです






まだ手元の本をすべて読み終わっていないのに、本を6冊買いました やっぱり病気かもしれない
やっぱり病気かもしれない 1冊目は伊坂幸太郎著「ホワイト ラビット」(新潮文庫)です
1冊目は伊坂幸太郎著「ホワイト ラビット」(新潮文庫)です 伊坂幸太郎の作品は文庫化されるたびにご紹介してきました
伊坂幸太郎の作品は文庫化されるたびにご紹介してきました

2冊目は原田マハ著「暗幕のゲルニカ」(新潮文庫)です 原田マハは絵画をテーマとする作品が多いですね
原田マハは絵画をテーマとする作品が多いですね

3冊目は井上荒野著「あなたならどうする」(文春文庫)です この人の作品を読むのは初めてです
この人の作品を読むのは初めてです

4冊目はG.K.チェスタントン著「知りすぎた男」(創元推理文庫)です これは新聞の書評欄に載っていました
これは新聞の書評欄に載っていました
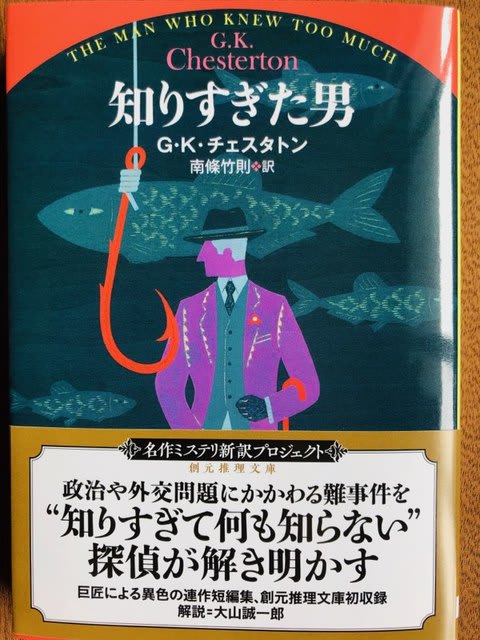
5月目はエリザベス・ウェイン著「コードネーム・ヴェリティ」(創元推理文庫)です これは帯に書かれた「私が影響を受けた1冊 柚木麻子」に惹かれて買いました
これは帯に書かれた「私が影響を受けた1冊 柚木麻子」に惹かれて買いました
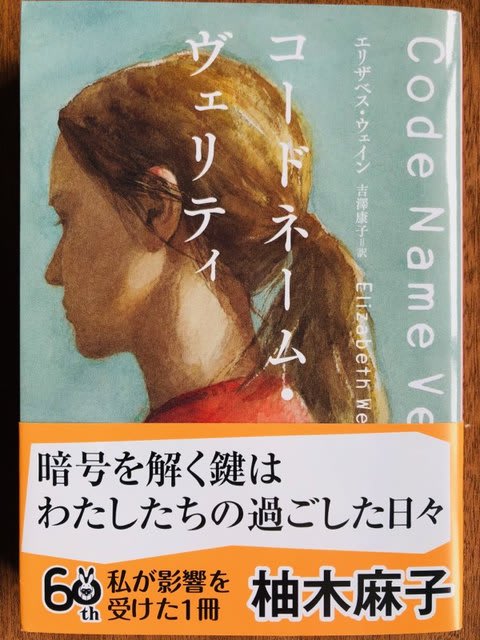
6冊目はチャールズ・ウィルフォード著「コックファイター」(扶桑社ミステリー)です これは新聞の書評欄に載っていました
これは新聞の書評欄に載っていました

いずれも読み終わり次第、当ブログでご紹介してきます

















