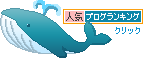小さなお子さん達が家族以外のコミュニティーで人と関わる経験は社会性や感情、行動のコントロールを育む絶好の機会
でも感情や行動のコントロールは大人でも時に難しい。
大人でも、日々の人との関わりなどで、消化しきれない気持ちに遭遇することがありますよね
最初は親御さん達の腕の中、安全なベッドの中で1日の大半を過ごしていた赤ちゃんも、少しずつ世界を広げ、1歳、2歳と歳を重ねるに連れ、関わる人のコミュニティーが広がります。そうすると子供達も日々様々な感情に直面します
他のお子さん達と遊ぶ機会が増えることは、ソーシャルスキルを育てるためにも とても良いことであり 我が子が他の子達と遊ぶ姿を見るのは喜ばしい出来事でもあると思います。また、それと同時に 大人目線で見た子供達の言動に なんでそんな事を言う/するの?? と、感情が揺さぶられる事もあるのではないでしょうか。
でも感情や行動のコントロールは大人でも時に難しい。
大人でも、日々の人との関わりなどで、消化しきれない気持ちに遭遇することがありますよね
最初は親御さん達の腕の中、安全なベッドの中で1日の大半を過ごしていた赤ちゃんも、少しずつ世界を広げ、1歳、2歳と歳を重ねるに連れ、関わる人のコミュニティーが広がります。そうすると子供達も日々様々な感情に直面します
他のお子さん達と遊ぶ機会が増えることは、ソーシャルスキルを育てるためにも とても良いことであり 我が子が他の子達と遊ぶ姿を見るのは喜ばしい出来事でもあると思います。また、それと同時に 大人目線で見た子供達の言動に なんでそんな事を言う/するの?? と、感情が揺さぶられる事もあるのではないでしょうか。
周囲や相手の親御さん達の反応も気になり、自分の子に、相手の子にどう声掛けをしたらいいか。 また周囲の声掛けや対応にモヤモヤが生じることも珍しくないのではないでしょうか
私は正直ありました。そういった場面がきっかけで、もっと子供の行動やその心理を理解したい。時に目の当たりにする子供達の不適切な言動にどう向き合い、対応することが、子供達の自尊心を傷つけず、適切な言動を身につけさせられるのか。そこは長年私の中での大きな課題でした
とにかく子供達は大人と比べると、語彙力も表現力も経験値もまだまだ乏しい。また、発達の速度や得意不得意は子供によってみんな違うので「トラブルは学びのチャンス!」と思って、周りの大人達がどの子に対しても 共感と適切な表現やトーンで その子が自分の気持ちや考えを相手に伝えていく方法を伝え続けていくことが、子供達のコミュニケーション力や気持ちを理解する、適切な言動を習得する学びになります
なぜ共感が必要かというと、仮に大人目線では不適切であったとしても、何かそこに子供なりの意思や考えがある場合が多いからです。結果的に不適切な言動であったとしても、本人はそうなる結果を予想/想像できていなかったり、望んでいなかった。でも失敗しちゃった。
声掛けをする際は、不適切な言動に対してだけでなく、そこに隠れていた気持ちにも共感を示すことで、仮にその後にそれは不適切で、こうした方がよいとアドバイスを受け取るにしても「自分がやろうとした事もわかってもらえた」そんな段階があることで、子供達の心が整いやすくなるからです
何か伝えたい気持ちや考えがある。でも小さな子供達は、その気持ちが何なのか。どうしたらいいのかがわからず、泣いたり、癇癪を起こしたり、叫んだり、物を投げたり、人を叩いたり、押したり、乗っかったり、噛みついたり。。。また、徐々に使える様になってきた数少ない言葉と表現方法を様々な状況で使うため、時に子供同士のやり取りの中で、大人がストレートに聞いて受け止めると ナイフのようにグサッと刺さる言い方や態度を見聞きすることがあります。その言葉が持っている負のエネルギー量を大人のようには理解せずに使っているから仕方がないのです。
何か伝えたい気持ちや考えがある。でも小さな子供達は、その気持ちが何なのか。どうしたらいいのかがわからず、泣いたり、癇癪を起こしたり、叫んだり、物を投げたり、人を叩いたり、押したり、乗っかったり、噛みついたり。。。また、徐々に使える様になってきた数少ない言葉と表現方法を様々な状況で使うため、時に子供同士のやり取りの中で、大人がストレートに聞いて受け止めると ナイフのようにグサッと刺さる言い方や態度を見聞きすることがあります。その言葉が持っている負のエネルギー量を大人のようには理解せずに使っているから仕方がないのです。
だからと言って、そのうち察して学ぶだろうと放っておいては子供達は適切な方法をなかなか身につける事ができず、そのまま大人になってしまうことも。。。
ではどう対応するか。これも全ての子供達や状況に万能なマニュアルがあるわけではなく、その状況や子供の思考や気質、発達に寄り添い どう導くと良いか試行錯誤が必要になります。それでも、私の経験からは不適切な行動への動機やきっかけに共感を示した上で、適切な表現方法を伝える事で多くの場面、年齢層で対応ができると感じています。
年齢が大きい子達は、自分で考える力が育っているので、「〜するのは良い事?〜するとどうなる?」また、小学生以上であれば「〜すると相手はどう感じる?これは良い方法だったかな」と言う問いかけにも自分で考えて、答えを出すことも可能です
そこへ持っていくためにも「今自分が感じた気持ちや考え/相手が感じているであろう気持ちや考え」について言葉で対話できることは、コミュニケーション力を育てる上でも大切だと感じています
なぜなら、言葉の意味を理解していない事を周りから何度も伝えられても 理解が難しいからです
私達もあまりよく知らない言語で伝えられても、何言いたいんだろう??って思いますよね。なので声掛けが響かない時は、その子はこの言葉の意味を知っているだろうか、理解しているだろうか。そんな視点も必要になります
なので私も日々、その子は何を理解していて、何が原因で、何がしたくて、どんなアプローチが効果的かどうかを常に試行錯誤です
ここでは観察力も必要になります
我が家でお預かりのお子さん達とのやり取りで、物の貸し借りで生じる状況や「お友達を叩く」などの不適切な行動に対する例を次のブログで書きます
ではどう対応するか。これも全ての子供達や状況に万能なマニュアルがあるわけではなく、その状況や子供の思考や気質、発達に寄り添い どう導くと良いか試行錯誤が必要になります。それでも、私の経験からは不適切な行動への動機やきっかけに共感を示した上で、適切な表現方法を伝える事で多くの場面、年齢層で対応ができると感じています。
年齢が大きい子達は、自分で考える力が育っているので、「〜するのは良い事?〜するとどうなる?」また、小学生以上であれば「〜すると相手はどう感じる?これは良い方法だったかな」と言う問いかけにも自分で考えて、答えを出すことも可能です
そこへ持っていくためにも「今自分が感じた気持ちや考え/相手が感じているであろう気持ちや考え」について言葉で対話できることは、コミュニケーション力を育てる上でも大切だと感じています
なぜなら、言葉の意味を理解していない事を周りから何度も伝えられても 理解が難しいからです
私達もあまりよく知らない言語で伝えられても、何言いたいんだろう??って思いますよね。なので声掛けが響かない時は、その子はこの言葉の意味を知っているだろうか、理解しているだろうか。そんな視点も必要になります
なので私も日々、その子は何を理解していて、何が原因で、何がしたくて、どんなアプローチが効果的かどうかを常に試行錯誤です
ここでは観察力も必要になります
我が家でお預かりのお子さん達とのやり取りで、物の貸し借りで生じる状況や「お友達を叩く」などの不適切な行動に対する例を次のブログで書きます