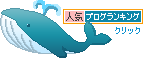Reggio ChildrenのHPにあるReggio Emilia Approachよりそのままコピー
100 languages
NO WAY. THE HUNDRED IS THERE
The child
is made of one hundred.
The child has
a hundred languages
a hundred hands
a hundred thoughts
a hundred ways of thinking of playing, of speaking.
A hundred always a hundred ways of listening of marveling of loving
a hundred joys for singing and understanding
a hundred worlds to discover
a hundred worlds to invent
a hundred worlds to dream.
The child has a hundred languages
(and a hundred hundred hundred more)
but they steal ninety-nine.
The school and the culture separate the head from the body.
They tell the child:
to think without hands
to do without head
to listen and not to speak
to understand without joy
to love and to marvel only at Easter and Christmas.
They tell the child:
to discover the world already there and of the hundred
they steal ninety-nine.
They tell the child:
that work and play
reality and fantasy
science and imagination
sky and earth
reason and dream
are things that do not belong together.
And thus they tell the child
that the hundred is not there.
The child says:
No way. The hundred is there.
Loris Malaguzzi (translated by Lella Gandini)
まさか 100の言語がある
子供は 100でできている。
子どもは
100の言語
100の手
100の思考
100の考え方
100の遊び方
100の話し方がある。
100通りの聴き方、100通りの驚き方、100通りの愛し方
歌う喜び、理解する喜び
発見すべき100の世界
発明すべき100の世界
夢見る100の世界
子どもには100の言語がある
(さらに100の100の)
でも大人達が、その99を盗む
学校と文化は頭と体を切り離す。
彼らは子供に言う:
手を使わずに考える
頭を使わずに行動する
話すことなく聞くこと
喜びなしに理解する
イースターとクリスマスにだけ、愛と驚きを感じなさい
彼らは子供に言う:
すでにそこにある世界を発見し
そして100のうち99を盗む。
彼らは子供に言う:
仕事と遊び
現実と空想
科学と想像力
空と大地
理性と夢
は共にあるべきものではない
こうして彼らは子供に言うのだ。
百は存在しないと
子供は言う:
まさか。100はそこにある。
ロリス・マラグッツィ(レッラ・ガンディーニ訳)
DeepL.comで翻訳
参照
100 languages. Reggio Children. (n.d.). https://www.reggiochildren.it/en/reggio-emilia-approach/100-linguaggi-en/