
本館最後の深海生物ゾーン。出口まで続いている残りの水槽を見ていこう。
まずは、深海に生息する海老の仲間たちから。
危険を感じると口から白い発光液をだす、ミノエビ。


体に白い斑模様があるのは、ミカワエビ。珍星2。
全ての足にハサミを持つことから名前がついた、センジュエビ。
退化して小さくなってしまった眼も、この海老の特徴だ。珍星2。


オオコシオリエビは、長い鋏脚と、折り曲げられた腹部が目につく。
背負ったエビスガイを、イソギンチャクで飾る、ジンゴロウヤドカリ。


一方、イガグリホンヤドカリには、イガグリガイという刺胞動物が巻き付く。珍星2。
続いて、蟹の仲間へ。珍星3、ヒラホモラ。
鉤状になった4番目の脚で、貝殻を背負う事ができる蟹だ。


同じく珍星3から、ヒラアシクモガニ。長く平べったい脚で、砂に潜るぞ。
ごつい体に、つぶらな瞳の、ケンナシコブシ。珍星2。
お腹の筋のせいで、なにか違う生き物の顔のようにも見える。


オオキンセンモドキは、浅い海にいたカラッパに近い種らしい。
魚の仲間からは、毒針の代わりに発電器官をもつ、シビレエイ。
大きい個体は、水槽の隅にいるジンゴロウヤドカリに伸し掛かっていた。
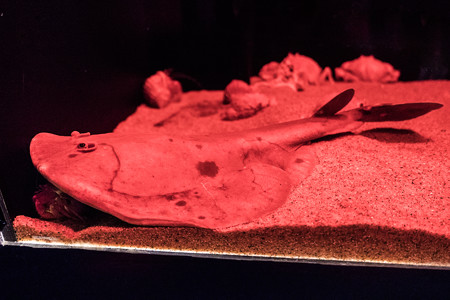

また、手のひらサイズの小さな個体も。これくらいだと可愛いものよ。
アカグツの仲間の、ワヌケフウリュウウオは、背中に輪っか状の模様がある。


そして先ほども見た珍星2、ミドリフサアンコウ。
ヌタウナギもいた。これで一通り展示されていた魚は見れたかな?


最後に、ヒメカンテンナマコと、岩に固定されたミョウガガイ(珍星2)。
蛇腹ホースのような姿で、どこがどう生き物なのか分かりにくい。
これで、イズリバから続いた、伊豆・三津シーパラダイス本館の展示エリアは全て見終えたが
実は、まだ2階の売店の方にも展示されている水槽があるため、次はそちらを見に行ってみよう。
FILE:13へ戻る みとしー目次 FILE:15へ進む
フクロウ・カワウソへ進む イルカの海へ進む
まずは、深海に生息する海老の仲間たちから。
危険を感じると口から白い発光液をだす、ミノエビ。


体に白い斑模様があるのは、ミカワエビ。珍星2。
全ての足にハサミを持つことから名前がついた、センジュエビ。
退化して小さくなってしまった眼も、この海老の特徴だ。珍星2。


オオコシオリエビは、長い鋏脚と、折り曲げられた腹部が目につく。
背負ったエビスガイを、イソギンチャクで飾る、ジンゴロウヤドカリ。


一方、イガグリホンヤドカリには、イガグリガイという刺胞動物が巻き付く。珍星2。
続いて、蟹の仲間へ。珍星3、ヒラホモラ。
鉤状になった4番目の脚で、貝殻を背負う事ができる蟹だ。


同じく珍星3から、ヒラアシクモガニ。長く平べったい脚で、砂に潜るぞ。
ごつい体に、つぶらな瞳の、ケンナシコブシ。珍星2。
お腹の筋のせいで、なにか違う生き物の顔のようにも見える。


オオキンセンモドキは、浅い海にいたカラッパに近い種らしい。
魚の仲間からは、毒針の代わりに発電器官をもつ、シビレエイ。
大きい個体は、水槽の隅にいるジンゴロウヤドカリに伸し掛かっていた。
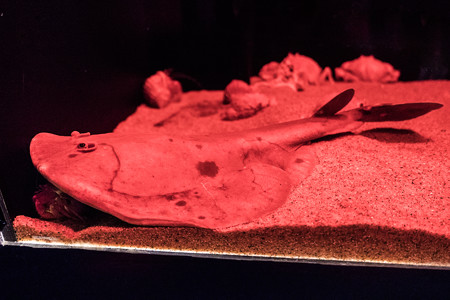

また、手のひらサイズの小さな個体も。これくらいだと可愛いものよ。
アカグツの仲間の、ワヌケフウリュウウオは、背中に輪っか状の模様がある。


そして先ほども見た珍星2、ミドリフサアンコウ。
ヌタウナギもいた。これで一通り展示されていた魚は見れたかな?


最後に、ヒメカンテンナマコと、岩に固定されたミョウガガイ(珍星2)。
蛇腹ホースのような姿で、どこがどう生き物なのか分かりにくい。
これで、イズリバから続いた、伊豆・三津シーパラダイス本館の展示エリアは全て見終えたが
実は、まだ2階の売店の方にも展示されている水槽があるため、次はそちらを見に行ってみよう。
FILE:13へ戻る みとしー目次 FILE:15へ進む
フクロウ・カワウソへ進む イルカの海へ進む




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます