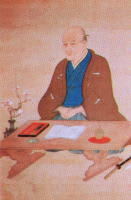今日(8月27日)は「益軒忌」、儒学者・貝原益軒の1714(正徳4)年の忌日。
貝原 益軒(かいばら えきけん)は江戸時代の本草学者、儒学者。1630(寛永7)年に、筑前国(現在の福岡県)黒田藩士、祐筆役の貝原寛斎の五男として生れる。名は篤信、字は子誠、号は柔斎、損軒(晩年に益軒)、通称は久兵衛。成長し黒田藩に仕えたが、二代藩主黒田忠之の怒りにふれ、一時浪人生活を余儀なくされ、この浪人生活の間に江戸や長崎で修行を重ねた。その後、三代目藩主光之の命で再出仕し、藩費による京都留学中に本草学や朱子学等を学ぶ。このころ木下順庵、山崎闇斎、松永尺五ら多彩な学者・文人らと交わった。帰藩後、藩士としての正式の待遇を与えられ、儒学者として藩主や重臣に朱子学を講じたほか、 藩命により「黒田家譜」を編纂したり、藩内をくまなく歩き回り「筑前国続風土記」を編纂また、朝鮮通信使の対応なども行った。自然科学分野においては大和本草」を発刊した。又、自らの畑に数十種類もの野菜・薬草を植えて事細かに研究。その経験に基づいて「花譜、菜譜」を発刊した。益軒は自らの学問を「民生日用の学」(=実際つかえる実用学)と称し、これらの著作は庶民に向けての平易な和文で綴っている。
そして、江戸時代の三大農学者の1人である宮崎安貞には中国の農書『農政全書』の講義をした。宮崎安貞の著作である近世農書を代表する「農業全書」は本草学者・貝原楽軒(貝原益軒の兄)と益軒の協力を得てはじめて誕生したものである。更に、教訓書「養生訓」「和俗童子訓」を執筆し独自の精神修養法を示した。こうした彼の著作は膨大なもので、全部で60部270余巻に及ぶという。
私などには、貝原益軒と言えば、先ず、養生訓」が頭に浮かぶ。
近代の医学はあまりにも薬に頼っており、「食の大切さ」を忘れていたといえる。しかし、最近は、予防医学の面から「食の大切さ」が見直されている。
そして、最近の健康ブームの影響で、TVなどでも様々な養生方法が放送され新しいダイエット方法が出ては消えしている。
それでは日本人にとっての食事療法としては何が良いのであろうか。日本人の身体の特徴としては、外人などと比較して、野菜を沢山食べるように腸が長いと言われている。
だから、当然に日本人が古くから日本で食べてきた伝統食を普段から食することこそが、最大の養生といえるであろう。
食の養生を考えるとき、現代でも、貝原益軒の「養生訓」から得るものはとても大きいという。
貝原益軒自身、生来体が虚弱で、生涯病気に苦しみ、夫人も病弱であったため、健康に留意し、医薬、食、などの養生に心がけ実践した成果ともいえる著作がこの養生訓である。
「養生の術を学んで、よくわが身をたもつべし。是人生第一の大事なり・・・
慾を欲しいままにして、身を亡ぼし命をうしなふ事、愚かなる至り也・・・
命短かければ、天下四海の富を得ても益なし・・・」
貝原益軒は「養生訓」の巻頭で、先ず、上記のような言葉を書いている。要するに、いずれ訪れる死は避けられないにしても生きて在る間は、不健康より健康がずっと良い筈である。健康であることは、単に楽しみを享受する為ばかりでなく、人生の目的や、人生観にも関わるものである。・・・その通りである。
そして、養生の術は、まず自分のからだをそこなうものを遠ざけることである。からだをそこなう物は、内欲と外邪とである。内欲というのは、飲食の欲、好色の欲、眠りの欲、しゃべりまくりたい欲と、喜・怒・憂・思・悲・恐・驚の七情の欲のこと。外邪とは天の四気であり、風・寒・暑・湿のことである。内欲をこらえて少なくし、外邪を恐れて防ぐのである。こうすれば元気をそこなわず、病気にならず天寿を保つだろう。およそ養生の道は、内欲をがまんするのを根本とする。この根本をしっかりやれば、元気が強くなって外邪もおかしてこない。元気が弱いと外邪に負けやすくなり、大病となって天寿を保てない。内欲をがまんするのに大事なのは、飲食を適量にして飲み過ぎ食い過ぎをしないことだ。脾胃をきずつけ(むかしは脾臓が直接消化に関係があると誤って信じられていた)病気をおこすものは食べない。色欲を慎んで精力を惜しみ、寝るべきでない時に寝ない。長時間眠ることを戒め、楽だからといって長く坐っていないで時々からだを動かし、気の循環をよくしなければいけない。・・・と教えている。
上記のうち、飲食についての教を補則をしておこう。
1「腹八分目」。
食欲は大欲の一つで、用心しないと満腹になるまで食べ、肥満の原因となる。肥満が生活習慣病の主な原因の一つであることは周知のことである。益軒は﹁飢え﹂をしのぐ程度でよいと諭してある。ただ、食べた後、いくらか体を動かしておけばカロリーを消費するので多少体を動かす事を勧める。益軒は3300歩、歩くように、出来ればもう少し運動しても良という。
ご馳走や愉しく夕食を囲めば、話も弾み、ついつい食欲も増す。その後、ゆっくり休めば、余剰のカロリーが、脂肪として蓄えられる。そこで幾らか体を動かしておけば、体はカロリーを消費(燃焼)する方向へと働く、そのため多少体を動かす事を勧める。
2、「凡ての食、淡薄なる物を好むべし。肥濃油膩(ひのうゆに)の物多く食ふべからず。生冷堅硬なる物を禁ずべし。あつ物、只一によろし。」
食事は薄味であっさりしたものが良い。脂っこいものを食べるな。又、単に薄味であれば良いというのではなく生ものや冷たいもの、堅いものも禁物と書かれている。
3、「肉も一品なるべし。サイ(副食)は一、二品に止まるべし。肉を二つかさぬべからず。又、肉多くくらふべからず。生肉をつゞけて食ふべからず、滞りやすし。」
肉は獣肉に限らない。魚肉も肉とする。二つ以上とらず一つにする。また、日本人は胃脾(いひ)︵胃腸︶薄弱なるゆえに、肉は多く食べなうよう注意している。
刺身は美食の代名詞であるが、生食は胃腸に滞り、消化に手間取り胃を疲労させる。しかし、美食も食の愉しみとして欠くべからざるものである。動物でしか摂取できない栄養素は美食の時を以って補う。楽しみなくば養生も空しい。美食とされる食物の性質を知れば、それと相反する、また制する食物を同時に摂れば良い。あるいは調理に工夫を凝らす。獣肉が胃腸にもたれるのを防ぐためにスパイスを使い、腸内での動きを早めるため、多めの野菜で繊維を摂取する。刺身はワサビを使い、魚毒の解毒に使う紫蘇を同時に食べる。焼魚に大根おろし、鰻に山椒、牡蠣にレモン、海老と椎茸、貝汁に春菊、このような生活の知恵は生かすべきである。
4、「肉は多けれども、飯の気にかたしめずといへり。肉を多く食ふべからず。食は飯を本とす。何の食も飯より多かるべからず。」
肉は蛋白質や脂質の代表である。魚や乳製品、卵、大豆製品も同じである。それに比べ「飯」は炭水化物の代表である。ヒトの食性はアミラーゼ活性が高く炭水化物を効率よく消化吸収し利用出来るようになっている。これを「本」とすべきである。肉などの蛋白質や脂質を多く食べても、その量がご飯を越えるようではいけない。越えればたちまち食性のバランスを崩し、長期に渡ると病を引き起こす。ご飯は生きるためのエネルギーの源で、穀物ナシで必要なカロリーは効率よく摂取できない。副食だけでそれをまかなおうとすれば、肝障害を引き起こす。
5、「味噌、性和(やわらか)にして、胃腸を補う」
昔から味噌、醤油、豆腐、納豆、きな粉に代表される大豆製品の中のイソフラボンは健康によい。最近の乳癌、前立腺癌の増加は、大豆製品の摂取の減少によるといわれている。
6、「怒りの後、早く食すべからず。食後、怒るべからず。憂ひて食すべからず。食して憂ふべからず。」
尤もな事である。食事は楽しく食べ、ゆっくり噛んで食べること。怒りや憂いなどの七情はそれぞれ五臓を傷める。家族や知人と会食の時はせめて、他に不快や憂いを与えないくらいは配慮したい。飲食しながらの深刻な議論は、頭に血を集め消化に良くない。
最後に、益軒は,又、「酒、タバコ」についての解説もしてある。
酒については、酒は食欲増進剤として用いる。酒は微酔にのみ、半酣をかぎりとすべしと飲みすぎを戒めている。そして、「人の病、酒によつて得るもの多し。酒を多くのんで、飯をすくなく食ふ人は、命短し。」と結んでいるが・・・これは、痛い!!私など、毎晩、ご飯代わりに、酒を飲んでおり、もう、何10年と夜にご飯を食べたことがない(寿司を覗く)。最近、医者に注意され、週一日だけ酒を飲まない日を作っているが・・・・本当にその日は寂しい・・・。またタバコは﹁性毒である・・・とすでに断定している。流石である。タバコに関しては、私も10年ほど前に禁煙した。・・・理由は、当時、仕事でアメリカへ行ったときもう、アメリカではタバコを吸っていると、非常に冷たい軽蔑の目で見られるので、悔しいから、止めた。健康上の理由で止めたのではないが結果的には良かった。
肉だけではなく、魚の食べすぎも良くないとある。山の奥底に住む人々が長生きしているはそういったものが中々手に入らず食べ過ぎる事がないからだそうで、植物性タンパク、大豆とご飯のような炭水化物と野菜を煮たものなどを食べていて益軒は、84歳まで長生き出来たと言っているのだが、贅沢に慣れた今日、私には、これを守るのは難しいね~。
野菜を沢山食べておかず(たんぱく質である、肉・魚)を少なく食べるのが腸の長い日本人の長生き方法だとしたら、これからの日本人の平均寿命は、完全に短かくなるだろうね~(-。-)。
(画像は貝原益軒。週刊朝日百科「日本の歴史」より)
参考:
貝原益軒 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%9D%E5%8E%9F%E7%9B%8A%E8%BB%92
貝原益軒アーカイブ
http://www.lib.nakamura-u.ac.jp/kaibara/
宮崎安貞 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E5%AE%89%E8%B2%9E
農政全書
http://www.tabiken.com/history/doc/O/O155L200.HTM
農業全書 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%85%A8%E6%9B%B8
農文協図書館 江戸農書 案内
http://www.ruralnet.or.jp/nbklib/book/10edonousyo1.html
【養生訓の話】
http://ww7.tiki.ne.jp/~onshin/yozyo.htm
[PDF] 貝原益軒の養生訓に学ぶ食養生
http://www2.eisai.co.jp/clinician2/cl2_05_536/sp_536_03.pdf
中国本草学の科学技術と思想
http://www.hum.ibaraki.ac.jp/mayanagi/paper01/ChiBencaoTec.html
貝原 益軒(かいばら えきけん)は江戸時代の本草学者、儒学者。1630(寛永7)年に、筑前国(現在の福岡県)黒田藩士、祐筆役の貝原寛斎の五男として生れる。名は篤信、字は子誠、号は柔斎、損軒(晩年に益軒)、通称は久兵衛。成長し黒田藩に仕えたが、二代藩主黒田忠之の怒りにふれ、一時浪人生活を余儀なくされ、この浪人生活の間に江戸や長崎で修行を重ねた。その後、三代目藩主光之の命で再出仕し、藩費による京都留学中に本草学や朱子学等を学ぶ。このころ木下順庵、山崎闇斎、松永尺五ら多彩な学者・文人らと交わった。帰藩後、藩士としての正式の待遇を与えられ、儒学者として藩主や重臣に朱子学を講じたほか、 藩命により「黒田家譜」を編纂したり、藩内をくまなく歩き回り「筑前国続風土記」を編纂また、朝鮮通信使の対応なども行った。自然科学分野においては大和本草」を発刊した。又、自らの畑に数十種類もの野菜・薬草を植えて事細かに研究。その経験に基づいて「花譜、菜譜」を発刊した。益軒は自らの学問を「民生日用の学」(=実際つかえる実用学)と称し、これらの著作は庶民に向けての平易な和文で綴っている。
そして、江戸時代の三大農学者の1人である宮崎安貞には中国の農書『農政全書』の講義をした。宮崎安貞の著作である近世農書を代表する「農業全書」は本草学者・貝原楽軒(貝原益軒の兄)と益軒の協力を得てはじめて誕生したものである。更に、教訓書「養生訓」「和俗童子訓」を執筆し独自の精神修養法を示した。こうした彼の著作は膨大なもので、全部で60部270余巻に及ぶという。
私などには、貝原益軒と言えば、先ず、養生訓」が頭に浮かぶ。
近代の医学はあまりにも薬に頼っており、「食の大切さ」を忘れていたといえる。しかし、最近は、予防医学の面から「食の大切さ」が見直されている。
そして、最近の健康ブームの影響で、TVなどでも様々な養生方法が放送され新しいダイエット方法が出ては消えしている。
それでは日本人にとっての食事療法としては何が良いのであろうか。日本人の身体の特徴としては、外人などと比較して、野菜を沢山食べるように腸が長いと言われている。
だから、当然に日本人が古くから日本で食べてきた伝統食を普段から食することこそが、最大の養生といえるであろう。
食の養生を考えるとき、現代でも、貝原益軒の「養生訓」から得るものはとても大きいという。
貝原益軒自身、生来体が虚弱で、生涯病気に苦しみ、夫人も病弱であったため、健康に留意し、医薬、食、などの養生に心がけ実践した成果ともいえる著作がこの養生訓である。
「養生の術を学んで、よくわが身をたもつべし。是人生第一の大事なり・・・
慾を欲しいままにして、身を亡ぼし命をうしなふ事、愚かなる至り也・・・
命短かければ、天下四海の富を得ても益なし・・・」
貝原益軒は「養生訓」の巻頭で、先ず、上記のような言葉を書いている。要するに、いずれ訪れる死は避けられないにしても生きて在る間は、不健康より健康がずっと良い筈である。健康であることは、単に楽しみを享受する為ばかりでなく、人生の目的や、人生観にも関わるものである。・・・その通りである。
そして、養生の術は、まず自分のからだをそこなうものを遠ざけることである。からだをそこなう物は、内欲と外邪とである。内欲というのは、飲食の欲、好色の欲、眠りの欲、しゃべりまくりたい欲と、喜・怒・憂・思・悲・恐・驚の七情の欲のこと。外邪とは天の四気であり、風・寒・暑・湿のことである。内欲をこらえて少なくし、外邪を恐れて防ぐのである。こうすれば元気をそこなわず、病気にならず天寿を保つだろう。およそ養生の道は、内欲をがまんするのを根本とする。この根本をしっかりやれば、元気が強くなって外邪もおかしてこない。元気が弱いと外邪に負けやすくなり、大病となって天寿を保てない。内欲をがまんするのに大事なのは、飲食を適量にして飲み過ぎ食い過ぎをしないことだ。脾胃をきずつけ(むかしは脾臓が直接消化に関係があると誤って信じられていた)病気をおこすものは食べない。色欲を慎んで精力を惜しみ、寝るべきでない時に寝ない。長時間眠ることを戒め、楽だからといって長く坐っていないで時々からだを動かし、気の循環をよくしなければいけない。・・・と教えている。
上記のうち、飲食についての教を補則をしておこう。
1「腹八分目」。
食欲は大欲の一つで、用心しないと満腹になるまで食べ、肥満の原因となる。肥満が生活習慣病の主な原因の一つであることは周知のことである。益軒は﹁飢え﹂をしのぐ程度でよいと諭してある。ただ、食べた後、いくらか体を動かしておけばカロリーを消費するので多少体を動かす事を勧める。益軒は3300歩、歩くように、出来ればもう少し運動しても良という。
ご馳走や愉しく夕食を囲めば、話も弾み、ついつい食欲も増す。その後、ゆっくり休めば、余剰のカロリーが、脂肪として蓄えられる。そこで幾らか体を動かしておけば、体はカロリーを消費(燃焼)する方向へと働く、そのため多少体を動かす事を勧める。
2、「凡ての食、淡薄なる物を好むべし。肥濃油膩(ひのうゆに)の物多く食ふべからず。生冷堅硬なる物を禁ずべし。あつ物、只一によろし。」
食事は薄味であっさりしたものが良い。脂っこいものを食べるな。又、単に薄味であれば良いというのではなく生ものや冷たいもの、堅いものも禁物と書かれている。
3、「肉も一品なるべし。サイ(副食)は一、二品に止まるべし。肉を二つかさぬべからず。又、肉多くくらふべからず。生肉をつゞけて食ふべからず、滞りやすし。」
肉は獣肉に限らない。魚肉も肉とする。二つ以上とらず一つにする。また、日本人は胃脾(いひ)︵胃腸︶薄弱なるゆえに、肉は多く食べなうよう注意している。
刺身は美食の代名詞であるが、生食は胃腸に滞り、消化に手間取り胃を疲労させる。しかし、美食も食の愉しみとして欠くべからざるものである。動物でしか摂取できない栄養素は美食の時を以って補う。楽しみなくば養生も空しい。美食とされる食物の性質を知れば、それと相反する、また制する食物を同時に摂れば良い。あるいは調理に工夫を凝らす。獣肉が胃腸にもたれるのを防ぐためにスパイスを使い、腸内での動きを早めるため、多めの野菜で繊維を摂取する。刺身はワサビを使い、魚毒の解毒に使う紫蘇を同時に食べる。焼魚に大根おろし、鰻に山椒、牡蠣にレモン、海老と椎茸、貝汁に春菊、このような生活の知恵は生かすべきである。
4、「肉は多けれども、飯の気にかたしめずといへり。肉を多く食ふべからず。食は飯を本とす。何の食も飯より多かるべからず。」
肉は蛋白質や脂質の代表である。魚や乳製品、卵、大豆製品も同じである。それに比べ「飯」は炭水化物の代表である。ヒトの食性はアミラーゼ活性が高く炭水化物を効率よく消化吸収し利用出来るようになっている。これを「本」とすべきである。肉などの蛋白質や脂質を多く食べても、その量がご飯を越えるようではいけない。越えればたちまち食性のバランスを崩し、長期に渡ると病を引き起こす。ご飯は生きるためのエネルギーの源で、穀物ナシで必要なカロリーは効率よく摂取できない。副食だけでそれをまかなおうとすれば、肝障害を引き起こす。
5、「味噌、性和(やわらか)にして、胃腸を補う」
昔から味噌、醤油、豆腐、納豆、きな粉に代表される大豆製品の中のイソフラボンは健康によい。最近の乳癌、前立腺癌の増加は、大豆製品の摂取の減少によるといわれている。
6、「怒りの後、早く食すべからず。食後、怒るべからず。憂ひて食すべからず。食して憂ふべからず。」
尤もな事である。食事は楽しく食べ、ゆっくり噛んで食べること。怒りや憂いなどの七情はそれぞれ五臓を傷める。家族や知人と会食の時はせめて、他に不快や憂いを与えないくらいは配慮したい。飲食しながらの深刻な議論は、頭に血を集め消化に良くない。
最後に、益軒は,又、「酒、タバコ」についての解説もしてある。
酒については、酒は食欲増進剤として用いる。酒は微酔にのみ、半酣をかぎりとすべしと飲みすぎを戒めている。そして、「人の病、酒によつて得るもの多し。酒を多くのんで、飯をすくなく食ふ人は、命短し。」と結んでいるが・・・これは、痛い!!私など、毎晩、ご飯代わりに、酒を飲んでおり、もう、何10年と夜にご飯を食べたことがない(寿司を覗く)。最近、医者に注意され、週一日だけ酒を飲まない日を作っているが・・・・本当にその日は寂しい・・・。またタバコは﹁性毒である・・・とすでに断定している。流石である。タバコに関しては、私も10年ほど前に禁煙した。・・・理由は、当時、仕事でアメリカへ行ったときもう、アメリカではタバコを吸っていると、非常に冷たい軽蔑の目で見られるので、悔しいから、止めた。健康上の理由で止めたのではないが結果的には良かった。
肉だけではなく、魚の食べすぎも良くないとある。山の奥底に住む人々が長生きしているはそういったものが中々手に入らず食べ過ぎる事がないからだそうで、植物性タンパク、大豆とご飯のような炭水化物と野菜を煮たものなどを食べていて益軒は、84歳まで長生き出来たと言っているのだが、贅沢に慣れた今日、私には、これを守るのは難しいね~。
野菜を沢山食べておかず(たんぱく質である、肉・魚)を少なく食べるのが腸の長い日本人の長生き方法だとしたら、これからの日本人の平均寿命は、完全に短かくなるだろうね~(-。-)。
(画像は貝原益軒。週刊朝日百科「日本の歴史」より)
参考:
貝原益軒 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%9D%E5%8E%9F%E7%9B%8A%E8%BB%92
貝原益軒アーカイブ
http://www.lib.nakamura-u.ac.jp/kaibara/
宮崎安貞 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E5%AE%89%E8%B2%9E
農政全書
http://www.tabiken.com/history/doc/O/O155L200.HTM
農業全書 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%85%A8%E6%9B%B8
農文協図書館 江戸農書 案内
http://www.ruralnet.or.jp/nbklib/book/10edonousyo1.html
【養生訓の話】
http://ww7.tiki.ne.jp/~onshin/yozyo.htm
[PDF] 貝原益軒の養生訓に学ぶ食養生
http://www2.eisai.co.jp/clinician2/cl2_05_536/sp_536_03.pdf
中国本草学の科学技術と思想
http://www.hum.ibaraki.ac.jp/mayanagi/paper01/ChiBencaoTec.html