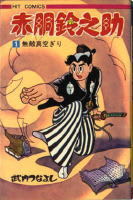1887(明治20)年の今日(4月20日)、首相官邸で伊藤博文主催による仮面舞踏会が開催された。
伊藤 博文は、明治憲法の起草に関わり、初代・第5代・第7代・第10代の内閣総理大臣および初代枢密院議長・韓国統監府統監・貴族院議長そして、わが地元である兵庫県の初代の知事(官選)をも務めた人物である。
周防国(現・山口県)の百姓の長男として生れながら、明治維新の元勲の仲間入りをし、位人臣をきわめた伊藤を世間では豊臣秀吉以来の出世と称した。しかし明治維新によって長年の身分、階級社会が打破されたとはいえ、そのような貧農のせがれで、武士になったのは維新の直前という。しかるに、最も低い身分の出身である伊藤が参議たちの総理選考会議で、初代内閣総理大臣になれたのは、英語に堪能な事を買われてのことだったという。
伊藤 は、吉田松陰の松下村塾に学び、高杉晋作、井上聞多らと倒幕運動に加わり、1862(文久2)年には公武合体論を主張する長井雅楽の暗殺を画策しイギリス公使館焼き討ちに参加するなど尊王攘夷の志士として活躍したが、その後、英国・ロンドンに渡航し半年滞在しており、帰国後に革新派に加わる。維新後は天皇が外国大使と会見する時は、必ず伊藤が通訳をし、1871年12月23日(明治4年11月12日)から1873(明治6)年9月13日までの、岩倉使節団の欧米巡視にも同行するなど、明治政府きっての英語に堪能な人物であったようだ。そんな、伊藤は、女たらしで、当時の政治家の中では色豪ぶりでもナンバーワン!だったという。生涯、金や派閥などには執着せず、全く無欲であっさりしていた伊藤だが、女だけには目が無く、女性関係の出入りが激しく、全国行く先々に女がいたという。宴会では新橋の芸者たちを何人もはべらせて、寝るときも、ふとんの両側に若い娘を寝かせて遊んでいたとか、最期まで毎夜のように女を抱いていた絶倫男だったという。
神戸には、JR元町の少し西北あたりに明治時代から昭和40年代くらいまでは賑ぎわいだ料亭街があった。そこには、料亭、お茶屋、仕出屋など戦前は120軒を超える店があり、最盛期には「千人近い芸者衆で華やだいといわれる高級料亭街「花隈」と言う地域である。今はその面影もないが、私が幼い頃、父親は商売が好調で景気がよく、酒好きでもあったので、しょっちゅう花隈通いをしていたようで、夜中に、数人の芸者衆に送られてご機嫌で家に帰って来たのを記憶しているが、初代兵庫県令であった伊藤も毎晩花隈に入り浸っていたといい、伊藤に贔屓にしてもらっていたという元芸者のお婆さんのインタビュー記事を神戸新聞で読んだことがある。 何でも、伊藤の妻・梅子は賢夫人のほまれ高かったそうだが、元々は下関の芸者「お梅」だったという。伊藤には英国留学前に結婚した「おすみ」という女がいたが離婚して、お梅を正妻にして梅子と名のらせた。伊藤が思いきって女道楽のできたのは、梅子の内助のおかげで、梅子は女遊びについて一切文句をいわなかったという。日本の場合、昔は、今と違って芸者などを相手の女遊びは、男の甲斐性のようにもなっていたので、私の親父も花隈などの芸者を相手に相当遊んでいたようだが、そんなことで、私の母親がとやかく言っていたのを聞いたことはなかった。それは、遊びと割り切っていたんだね~。
1883(明治16)年11月28日、外務卿(後に外務大臣)井上馨は鹿鳴館の落成式で、「国境の為に限られざるの交誼(こうぎ)友情を結ばしむる場となさんとする」ために鹿鳴館を開いたことを述べ、この文明開化の殿堂が「各国人の調和の交際を得る場」となることを希望すると、その所信を表明。本来は国賓クラスの外国からの賓客を宿泊・接待するための使節であったが、國際親善の場であると同時に、鹿鳴館に招かれた外国人に日本が決して未開の国ではなく、欧米諸国に劣らぬほど文明開化された国である事を印象付けるという役割が架せられた社交場でもあった。(週刊朝日百貨「日本の歴史)
英語通の伊藤もともに欧化主義の積極的な推進者として、鹿鳴館に相当入れ込んでいた。明治政府は明治憲法制定と同時平行で不平等条約改正に取り組んでいたが伊藤も井上も条約改正のためには、日本が文明国であることを外国人に示すことが必要であると考えていた。
1883(明治16)年7月に落成後は、外国人を招いた舞踏会や夜会が毎週のように開かれ、伊藤自らも主催して「舞踏内閣」と悪口を叩かれたという。そして、無類の女好きの伊藤は、夜の部では、こうした舞踏会や夜会を利用して片っ端から女を口説いたとも。
そして、世間の耳目を集めた1887(明治20)年、今日(4月20日)の伊藤博文首相夫妻主催の仮装舞踏会(ファンシー・ボール)は、鹿鳴館ではなく、首相官邸で行われたものである。
それは、社交界で評判の美人であった戸田氏共伯爵夫人との関係がウワサとなったもので、極子(きわこ)夫人は岩倉具視の次女であり、恵まれた環境で育ったことから、英語とダンスが大の得意で当時の鹿鳴館社交界の名花と謳われ、外人も日本人も争ってダンスの相手になろうとした美人だった。伊藤はこの日、その極子夫人を裏庭の茂みに誘い込んで、乱暴して、いかがわしい振る舞いに及んだので、夫人がはだしで逃げだしたといったスキャンダルを新聞が書き立て、伊藤の好色漢、ハレンチぶりを非難したという。それまで、「嬌奢を競い淫逸にいたる退廃的行事」として鹿鳴館での社交パーティーに非難の声を挙げていた者達もこの仮装舞踏会が開催されるや「亡国のきざし」と口を極めて罵るようになったという。勝海舟も憂国の感を深め、21か条の時弊を挙げて政府に建白している(以下参考に記載の「勝安房 時弊廿一條を内閣に建白」参照)。そして、井上の鹿鳴館外交への風当たりは厳しいものとなり、さらに条約改正は多くの努力にも関わらず果たせず、面目を失した井上は同年9月に外務大臣を辞任している。
この鹿鳴館外交が、外国人の目には、どう映ったか?などもう少し書きたいのだが、長くなるので、また、次の機会に書くことにし、今日はこれで終わる。
(画像は、井上馨(左)と伊藤博文。「ひたすら生き望んだ哀れな古強者」ピゴー画。週刊朝日百科「日本の歴史」より)
参考:
伊藤博文 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E5%8D%9A%E6%96%87
おどる近代 ―交際・ダンス・〈アソビ〉
http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~ito/works/dm/dancem1.htm
鹿鳴館 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E9%B3%B4%E9%A4%A8
エピソード「結ばれたロミオとジュリエットー大山巌と鹿鳴館の華ー」
http://www.geocities.jp/michio_nozawa/episode34.html
ジョルジュ・ビゴー - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BB%E3%83%93%E3%82%B4%E3%83%BC
Belle’s bar 日本のワインの歴史
http://blog.goo.ne.jp/urbankitty/c/da75844ddea3b79e648ebf06f8b06937
反米嫌日戦線 LIVE and LET DIE(美は乱調にあり):朝鮮人に暗殺され ...
http://ch05028.kitaguni.tv/e134015.html
戸田氏共 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E7%94%B0%E6%B0%8F%E5%85%B1
勝安房 時弊廿一條を内閣に建白
http://www.ballroom-j.com/history/18870523.htm
伊藤 博文は、明治憲法の起草に関わり、初代・第5代・第7代・第10代の内閣総理大臣および初代枢密院議長・韓国統監府統監・貴族院議長そして、わが地元である兵庫県の初代の知事(官選)をも務めた人物である。
周防国(現・山口県)の百姓の長男として生れながら、明治維新の元勲の仲間入りをし、位人臣をきわめた伊藤を世間では豊臣秀吉以来の出世と称した。しかし明治維新によって長年の身分、階級社会が打破されたとはいえ、そのような貧農のせがれで、武士になったのは維新の直前という。しかるに、最も低い身分の出身である伊藤が参議たちの総理選考会議で、初代内閣総理大臣になれたのは、英語に堪能な事を買われてのことだったという。
伊藤 は、吉田松陰の松下村塾に学び、高杉晋作、井上聞多らと倒幕運動に加わり、1862(文久2)年には公武合体論を主張する長井雅楽の暗殺を画策しイギリス公使館焼き討ちに参加するなど尊王攘夷の志士として活躍したが、その後、英国・ロンドンに渡航し半年滞在しており、帰国後に革新派に加わる。維新後は天皇が外国大使と会見する時は、必ず伊藤が通訳をし、1871年12月23日(明治4年11月12日)から1873(明治6)年9月13日までの、岩倉使節団の欧米巡視にも同行するなど、明治政府きっての英語に堪能な人物であったようだ。そんな、伊藤は、女たらしで、当時の政治家の中では色豪ぶりでもナンバーワン!だったという。生涯、金や派閥などには執着せず、全く無欲であっさりしていた伊藤だが、女だけには目が無く、女性関係の出入りが激しく、全国行く先々に女がいたという。宴会では新橋の芸者たちを何人もはべらせて、寝るときも、ふとんの両側に若い娘を寝かせて遊んでいたとか、最期まで毎夜のように女を抱いていた絶倫男だったという。
神戸には、JR元町の少し西北あたりに明治時代から昭和40年代くらいまでは賑ぎわいだ料亭街があった。そこには、料亭、お茶屋、仕出屋など戦前は120軒を超える店があり、最盛期には「千人近い芸者衆で華やだいといわれる高級料亭街「花隈」と言う地域である。今はその面影もないが、私が幼い頃、父親は商売が好調で景気がよく、酒好きでもあったので、しょっちゅう花隈通いをしていたようで、夜中に、数人の芸者衆に送られてご機嫌で家に帰って来たのを記憶しているが、初代兵庫県令であった伊藤も毎晩花隈に入り浸っていたといい、伊藤に贔屓にしてもらっていたという元芸者のお婆さんのインタビュー記事を神戸新聞で読んだことがある。 何でも、伊藤の妻・梅子は賢夫人のほまれ高かったそうだが、元々は下関の芸者「お梅」だったという。伊藤には英国留学前に結婚した「おすみ」という女がいたが離婚して、お梅を正妻にして梅子と名のらせた。伊藤が思いきって女道楽のできたのは、梅子の内助のおかげで、梅子は女遊びについて一切文句をいわなかったという。日本の場合、昔は、今と違って芸者などを相手の女遊びは、男の甲斐性のようにもなっていたので、私の親父も花隈などの芸者を相手に相当遊んでいたようだが、そんなことで、私の母親がとやかく言っていたのを聞いたことはなかった。それは、遊びと割り切っていたんだね~。
1883(明治16)年11月28日、外務卿(後に外務大臣)井上馨は鹿鳴館の落成式で、「国境の為に限られざるの交誼(こうぎ)友情を結ばしむる場となさんとする」ために鹿鳴館を開いたことを述べ、この文明開化の殿堂が「各国人の調和の交際を得る場」となることを希望すると、その所信を表明。本来は国賓クラスの外国からの賓客を宿泊・接待するための使節であったが、國際親善の場であると同時に、鹿鳴館に招かれた外国人に日本が決して未開の国ではなく、欧米諸国に劣らぬほど文明開化された国である事を印象付けるという役割が架せられた社交場でもあった。(週刊朝日百貨「日本の歴史)
英語通の伊藤もともに欧化主義の積極的な推進者として、鹿鳴館に相当入れ込んでいた。明治政府は明治憲法制定と同時平行で不平等条約改正に取り組んでいたが伊藤も井上も条約改正のためには、日本が文明国であることを外国人に示すことが必要であると考えていた。
1883(明治16)年7月に落成後は、外国人を招いた舞踏会や夜会が毎週のように開かれ、伊藤自らも主催して「舞踏内閣」と悪口を叩かれたという。そして、無類の女好きの伊藤は、夜の部では、こうした舞踏会や夜会を利用して片っ端から女を口説いたとも。
そして、世間の耳目を集めた1887(明治20)年、今日(4月20日)の伊藤博文首相夫妻主催の仮装舞踏会(ファンシー・ボール)は、鹿鳴館ではなく、首相官邸で行われたものである。
それは、社交界で評判の美人であった戸田氏共伯爵夫人との関係がウワサとなったもので、極子(きわこ)夫人は岩倉具視の次女であり、恵まれた環境で育ったことから、英語とダンスが大の得意で当時の鹿鳴館社交界の名花と謳われ、外人も日本人も争ってダンスの相手になろうとした美人だった。伊藤はこの日、その極子夫人を裏庭の茂みに誘い込んで、乱暴して、いかがわしい振る舞いに及んだので、夫人がはだしで逃げだしたといったスキャンダルを新聞が書き立て、伊藤の好色漢、ハレンチぶりを非難したという。それまで、「嬌奢を競い淫逸にいたる退廃的行事」として鹿鳴館での社交パーティーに非難の声を挙げていた者達もこの仮装舞踏会が開催されるや「亡国のきざし」と口を極めて罵るようになったという。勝海舟も憂国の感を深め、21か条の時弊を挙げて政府に建白している(以下参考に記載の「勝安房 時弊廿一條を内閣に建白」参照)。そして、井上の鹿鳴館外交への風当たりは厳しいものとなり、さらに条約改正は多くの努力にも関わらず果たせず、面目を失した井上は同年9月に外務大臣を辞任している。
この鹿鳴館外交が、外国人の目には、どう映ったか?などもう少し書きたいのだが、長くなるので、また、次の機会に書くことにし、今日はこれで終わる。
(画像は、井上馨(左)と伊藤博文。「ひたすら生き望んだ哀れな古強者」ピゴー画。週刊朝日百科「日本の歴史」より)
参考:
伊藤博文 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E5%8D%9A%E6%96%87
おどる近代 ―交際・ダンス・〈アソビ〉
http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~ito/works/dm/dancem1.htm
鹿鳴館 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E9%B3%B4%E9%A4%A8
エピソード「結ばれたロミオとジュリエットー大山巌と鹿鳴館の華ー」
http://www.geocities.jp/michio_nozawa/episode34.html
ジョルジュ・ビゴー - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BB%E3%83%93%E3%82%B4%E3%83%BC
Belle’s bar 日本のワインの歴史
http://blog.goo.ne.jp/urbankitty/c/da75844ddea3b79e648ebf06f8b06937
反米嫌日戦線 LIVE and LET DIE(美は乱調にあり):朝鮮人に暗殺され ...
http://ch05028.kitaguni.tv/e134015.html
戸田氏共 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E7%94%B0%E6%B0%8F%E5%85%B1
勝安房 時弊廿一條を内閣に建白
http://www.ballroom-j.com/history/18870523.htm