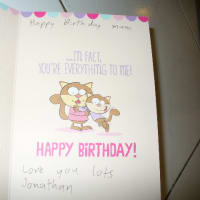バードウォッチングの続きです。
バードウォッチングをしながら同行者のイギリス人エリザベスと
ガイドのエドさんとおしゃべり。
わたしはどちらかというとお話を聞くのが好きなのでお二人のお話に
耳を傾けました。
ガイドのEdさんはキナバル山麓出身のドゥスン族
11人兄弟で4年前にお父さんを亡くし、月に数回帰っては小さい弟妹たちの
父親代わりとして面倒を見ているとか。貧しい家庭に育ち、12歳のときから
ポーターとしてキナバル山にくる外国人相手の荷物運びの仕事をしていたらしいです。
そこで沢山の外国人に出会い、耳で英語を覚え習得。加えて山で育ったので野山の
動植物の知識が豊富。そして運よくシャングリラでの仕事をみつけ、働くように
なったとか。
小さい弟妹たちに一生懸命勉強してもらって、いい仕事につけるように助けたい。
亡くなった父親に代わって、お母さんを助けたい。
お母さんには一生懸命働くこと、どんなに貧しくても人に物乞いするようなことを
してはいけないと育った。小さいときからココナツの木に登って毎週日曜日
教会帰りの人たちにココナツの実を売って家計を助けていた。ココナツの実を
とるのも大変だけれど、重くて運ぶのも大変だったけれど、それがポーターの
仕事に役立ったとか。
ポーターの仕事をしていたときは、毎日決まった場所に行って、登山客がいれば
その荷物を運ぶ仕事をする。とにかく毎日行って、自分の名前が呼ばれるのを待つ
だけだった。仕事があるかどうかは、保障されていない。ただ行って待つ。
仕事がもらえればラッキーという日々だったと。本当に苦労したんですね。
でもニコニコと愛嬌よく前向きに生きる姿はとても好感が持てます。
勤勉な28歳。一度もボルネオ島を出たことはないけれど、一生懸命働いて、
お金を貯めて、飛行機に乗って外国に行くのが夢だそうです。
ボルネオの中心地はかなりにぎやかで開発も進んでおりますが、富と貧しさが
混在しているようなところです。
水上集落にすみ漁業を営むバジャウ族はお家も粗末で、見るからに貧しそうですし、
子どもには義務教育をうけさせず、親が漁師としてのスキルを子どもたちに教えて、
それで十分という人が多いそうで、漁師としての古くからの生活スタイル、方法を
頑なに守り、変化を拒む人が多いとか。
水上集落は環境汚染にも繋がるということで、政府は陸上の集落を無償提供して移動を
促進するように働きかけているようですけど。一部の若い人の中には新しい生活様式に
溶け込もうとしている人たちもいるらしいですけれど。
キナバル山麓は低地に比べると涼しく作物が育ちやすいということで農民が多いらしい
ですが、ドゥスン族の人たちもEdさんがそうしたように、山から降りてよりよい仕事を
求めて都市部で生活する人も増えていくのではないかと思うわけです。
これから大きく変化していくことでしょう。
10年後、20年後 コタキナバルがどのように変わっていくのか、人々の生活は
どのようになっていくのか....興味深いところです。
バードウォッチングをしながら同行者のイギリス人エリザベスと
ガイドのエドさんとおしゃべり。
わたしはどちらかというとお話を聞くのが好きなのでお二人のお話に
耳を傾けました。
ガイドのEdさんはキナバル山麓出身のドゥスン族
11人兄弟で4年前にお父さんを亡くし、月に数回帰っては小さい弟妹たちの
父親代わりとして面倒を見ているとか。貧しい家庭に育ち、12歳のときから
ポーターとしてキナバル山にくる外国人相手の荷物運びの仕事をしていたらしいです。
そこで沢山の外国人に出会い、耳で英語を覚え習得。加えて山で育ったので野山の
動植物の知識が豊富。そして運よくシャングリラでの仕事をみつけ、働くように
なったとか。
小さい弟妹たちに一生懸命勉強してもらって、いい仕事につけるように助けたい。
亡くなった父親に代わって、お母さんを助けたい。
お母さんには一生懸命働くこと、どんなに貧しくても人に物乞いするようなことを
してはいけないと育った。小さいときからココナツの木に登って毎週日曜日
教会帰りの人たちにココナツの実を売って家計を助けていた。ココナツの実を
とるのも大変だけれど、重くて運ぶのも大変だったけれど、それがポーターの
仕事に役立ったとか。
ポーターの仕事をしていたときは、毎日決まった場所に行って、登山客がいれば
その荷物を運ぶ仕事をする。とにかく毎日行って、自分の名前が呼ばれるのを待つ
だけだった。仕事があるかどうかは、保障されていない。ただ行って待つ。
仕事がもらえればラッキーという日々だったと。本当に苦労したんですね。
でもニコニコと愛嬌よく前向きに生きる姿はとても好感が持てます。
勤勉な28歳。一度もボルネオ島を出たことはないけれど、一生懸命働いて、
お金を貯めて、飛行機に乗って外国に行くのが夢だそうです。
ボルネオの中心地はかなりにぎやかで開発も進んでおりますが、富と貧しさが
混在しているようなところです。
水上集落にすみ漁業を営むバジャウ族はお家も粗末で、見るからに貧しそうですし、
子どもには義務教育をうけさせず、親が漁師としてのスキルを子どもたちに教えて、
それで十分という人が多いそうで、漁師としての古くからの生活スタイル、方法を
頑なに守り、変化を拒む人が多いとか。
水上集落は環境汚染にも繋がるということで、政府は陸上の集落を無償提供して移動を
促進するように働きかけているようですけど。一部の若い人の中には新しい生活様式に
溶け込もうとしている人たちもいるらしいですけれど。
キナバル山麓は低地に比べると涼しく作物が育ちやすいということで農民が多いらしい
ですが、ドゥスン族の人たちもEdさんがそうしたように、山から降りてよりよい仕事を
求めて都市部で生活する人も増えていくのではないかと思うわけです。
これから大きく変化していくことでしょう。
10年後、20年後 コタキナバルがどのように変わっていくのか、人々の生活は
どのようになっていくのか....興味深いところです。