手作り感あふれるガラス風鈴です。

全長 60㎝(吊糸含む)、幅 12㎝。昭和。

上側に、金魚の描かれた灯篭状のガラス。

その下に、板ガラスが竹輪から吊り下げられています。

風が吹くと、この板ガラスがお互いにぶつかり合って、音が出ます。
時代や産地は、はっきりしません。民芸品、あるいは、おみやげ品かもしれません。讃岐、丸亀ともいわれます。いずれにしても、小規模に家内生産された物でしょう。

全体はこんな風です。
飾りの金魚部は、4枚のガラス板に穴を開け、糸で結んでいます。

音を出す板硝子は、正方形が4枚、長方形が6枚です。

片側には、素朴な花の絵が描かれています。

裏側はというと、糸紐を紙で押さえ、糊でくっつけてあります。表側からみると、この紙は、花びらで目立ちません(^^;

細長い板ガラスにも、素朴な花びらが描かれています。

これも、やっぱり、紙で糸を止めています。
これを拡大してみると・・・

本(小説?)の1ページを切り取って、押さえ紙につかっているではありませんか(^^;
内職の舞台裏が覗けますね(^.^)
手作り感にあふれて、ほほえましい風鈴ですが・・・

普通の板(窓?)ガラスを切ったままなのです。切り口がとても鋭い。

こちらの板ガラスも、エッジが鋭い。

金魚の板も、切りっぱなしですが、色を塗っていて、その分にぶくなっているので少しはマシ(^^;

定位置に吊るしてみました。
先回のガラス風鈴とちがって、これは一つだけで、結構複雑な音がします。
でも、糸が相当古くなっていて、風が吹くと、切れるやもしれません。
この場所は、吹き抜けの上部です。もし、糸が切れたり、止めの紙が剥がれたりすれば、鋭い板ガラスが下へ飛んでいくことになります。
はらはら、ドキドキの手作り風鈴です(^.^)












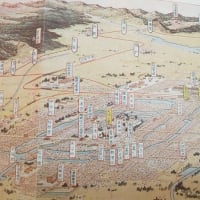




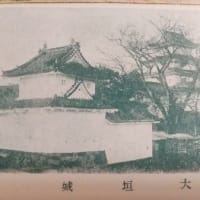
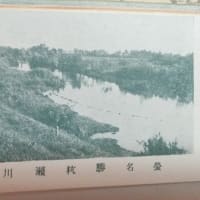







手作り感いっぱいの風鈴ですね。
でも、実際に使用するとなると、危険も伴いますし、風鈴も壊れてしまいそうですね。
現実には、ガラスケースの中に外した状態で収納し、その傍らに、吊った状態の写真を添えておくという方法をとらざるをえないのでしょうか、、、?
実は、江戸風鈴と一緒に、この位置で毎日、音をだしています。
糸がいつ切れるかもしれない危うさとガラスのはかない音が、妙にマッチするのです(^^;
風鈴が落ちたように装った殺人、なんていうセコい推理小説が書けそうです。
本当に切れかけです。
これだけガラスを使っているとそこそ重いですから、余計ハラハラします。
TVが白黒のころ、推理ドラマが盛んで、その一つに完全殺人事件がありました。男が首から血を流して死んでいます。争ったあとや凶器らしきものは、どこにもありません。屋根のツララが落ちてきて刺さったのです。犯人云々は忘れました(^^; 今なら、コナン君が謎解きをしてくれるでしょう