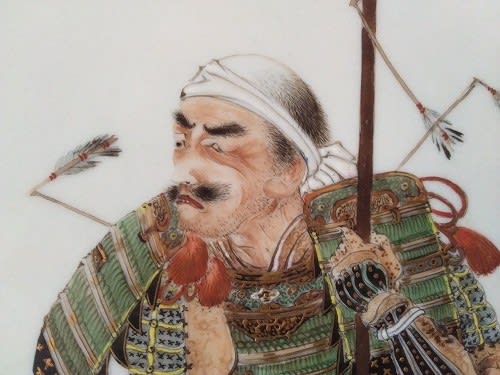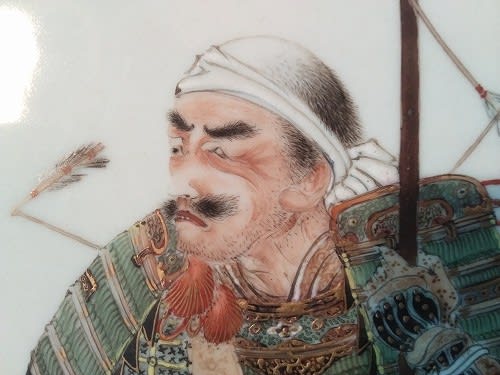今回は、江戸後期の古伊万里大皿です。
牡丹の花が大きく描かれています。

径 28.6㎝、高 4.9㎝、高台径 16.7㎝。江戸時代後期。


満開の牡丹が、雲をたなびかせて、波間をぐんぐん進んでいるかのようです。
名付けて、牡丹船。

ふくやかな蕾。

満開の花。

これは虫でしょうか。
UFOにも見えますね。
その下には、UFOから飛び立った小型機。

牡丹船の周りにも、UFO小型機が飛び回っている!?
実はこの皿を持っていた憶えがなく、大皿をさがしに棚の奥をごそごそやっていて見つけました。
伊万里に特に関心があったわけでないので、購入した記憶もないけれど ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・はたと気が付きました。実はこの皿、拾い物です。しかも私ではなく、つれ合いさん(^.^)
ずっと以前は、粗大ごみを出す日が決まっていて、早朝には、置き場所が山のようになっていました。プロの業者が巡回して、それらしい品を車に積んでいく光景は、いつも通り。たまたま傍を通りかかったつれ合いさん、おや!ということで、家へ持ち帰り、「これ、古いもの?」と、汚れた皿を私に見せるではありませんか。「おお、伊万里だがや」と岐阜弁で答える私。
そんな訳で、この大皿がここにあるのです。
後期の伊万里とはいえ、無疵。絵柄もなかなかしゃれています。
せっかく日の目をみたのですから、しばらく展示しておきます(^.^)