彼岸過ぎまで寒さがぶり返していた不純な天候も、やっと終わったようです。
気がつけば、冬越しをしたエンドウのツルが伸び放題になっていました。
早急に、棚をこしらえねばなりません。
これまでは、2.1mの棚を頑張って作っていました。
ところが、今年は大問題が・・・・
以前に、広重ゆかりの竹藪を伐採したことはブログに書きました。
実は、2.1mの大棚は、この竹を使って組み立てていたのです。
竹は年々劣化していきます。ところが、竹藪がない!新しい竹は、もはや手に入りません。
どーする!?
市販品を使うか・・・・これまでも、キュウリやトマトには、2.1mの農業用資材(緑のポール)を使って棚を作ってきました。しかし、この資材は弱い!豆類やゴーヤなど繁茂する野菜には、強度不足なのです。
ならば、もっと太い農業用資材を使えばいいのでは?
今まで使ってきたポールの径は20㎜です。ところが、これより太い品は、急にベラボウな値段になってしまうのです。
そこで今回、探し当てたのがこれ。


防獣杭として売られていました。長さ 210㎝、太さ 25mm、とても頑丈です。10本、買いました。キュウリネット込みで、5000円弱。まあ、これ位の出費に抑えることができればヨシとしましょう。出来上がる棚の高さは2.1mよりかなり低くなりますが、やむをえません。
夫婦共同作業により、何とかネットも張り終えました(^.^)
ポールを木槌で打つとき、少し離れて見ていてもらわないと、真っ直ぐに打てないから、どうしても助手が要るのです。
合掌棚にすれば、強度も出るし、一人で組み立てが可能ですが、防獣杭が倍必要となります。これでは、財布がもちません(^^;

出来上がった棚の高さは、1.85mです。
両端は、防獣杭ではなく、通常の農業資材(径 20mm)です。その理由は後ほど。

この写真でわかるように、右の農業用資材は、左の防獣杭に較べて細いだけでなく、木槌で打たれてきたことにより、上端がひどく損傷しています。ここから入った雨水が、腐食をすすめ、数年後にはポキリと折れてしまいます。
防獣杭なら大丈夫かというと・・・

10本の内、数本は、木槌で打たれたことにより、鉄パイプが剥き出しになっています。
そこで、

ありあわせのボンドをたっぷり塗り、

蓋をしてやりました(^.^)
残る作業は、ポールの固定です。
頑丈な農業用紐をポールの上端に結び、

下端をアンカーで固定します。

ギュっと張れば、多少の暴風雨にはOK。

二本、ピンと張れました。
ところで、この固定紐は、端から2本目のポールを固定しています。その理由は、固定してできた三角形の角度をできるだけ大きくして、強度、安定度を増すためです。
端のポールは、いわばダミー。従来の農業資材(径20mm)です。
予算の都合上、やむをえませんね(^^;











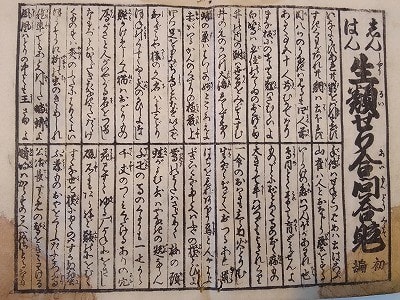






 ・・・・・
・・・・・  思いきって、内側にジャージャーと水を流してみました。
思いきって、内側にジャージャーと水を流してみました。

















