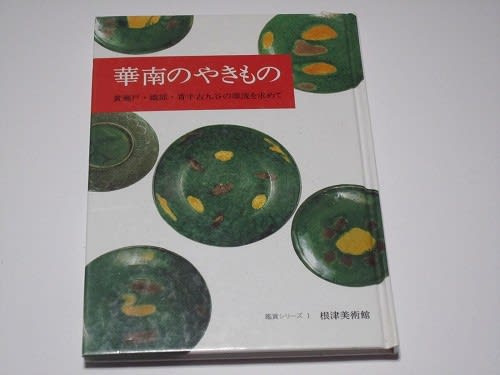小鼓を習い始めて、20年以上になりました。
つい、あれも、これも、と手を出して、気がついてみればこの有様です(まあ、外の骨董も似たり寄ったりですが(^-^;)。
鼓の店でも開くつもりか、とひやかされそうですが、すべて個人用です。
鼓道楽

いわゆる、小鼓の胴です。
大きさは決まっていて、長さ25cm、径10cmです。品物による違いは、数mmしかありません。素材は山桜。重い品ほど、重厚な音が出ます。一般的には、400g代。500g以上、300g以下の品は稀です。
値段のかなりの部分は、蒔絵によります。
時代が古く、かつ、良い蒔絵の施された鼓胴はかなりの価格になります。

もう一つ、重要なアイテムは、皮です。
胴に比べて姿形がきれいでないので、ぞんざいに扱われることが多いです。さらに、やぶれやすい、虫が食う、などの理由で、良い皮を求めるのはなかなか難しい。
ある意味では、胴よりも、皮の方が貴重かもしれません。

胴と皮を組むと、こんな感じです。
長い間組んだままにしておくのは、皮のためによくないので、鼓を打つとき以外は、胴と皮を外しておきます。
私のイッピン
こんなにもたくさん、小鼓をもっているのですが、使うのは次の鼓胴と皮だけです。
鳴りが良いからです。

蕪蒔絵鼓胴:江戸中期 495g

蕪蒔絵は、江戸時代から現代まで、鼓胴に好んで描かれています。蕪は、根(音)が太い、よくな(鳴)る、とかけているのです。

胴の内側は、細かな段鉋が施されています。鉋目の入り方が、音色に影響するので、鼓胴を選ぶ時の判断材料になります。
大事なのは、皮(子豚の皮)です。
打ち込めば打ち込むほど、良い音色になります。したがって、新しい皮よりも、長い間使われてきた皮に価値があります。200年、300年前の胴は案外ありますが、程度の良い100年前の皮は希少品なのです。

小鼓を始めてから20年以上たって、やっと入手することができた古皮です。

左側の皮(打つ方、表皮)は、プロに修理してもらいました(いくら日本に一人とはいえ、目がくらむほどの金額・・・・トホホ(^-^;)。
右側の皮(打たない方、裏皮)は、元のまま。
おかげで、外周の黒漆、100年以上前と現代との比較が可能になりました。そして、私にとって、長年の課題であった、「漆が透ける」ことの謎解きができたのです。すごく高くついた謎解きではありますが、また、いずれブログで。

組立てると楽器になります。2枚の皮を結んだ紐(縦調べ)とそれに直角に交わる紐(横調べ)が、小鼓の独特の音色をつくりだします。
そのために、縦紐を張るのは非常に繊細です。ミリメートル単位の微調整を繰り返して、やっと、小鼓らしい音がでるようになります。

横調べを掬うようにして、左手で小鼓を持ち、手首を返して、右肩甲骨にあて、右手の中指で表皮を打ちます。
この時、左手の握りの強弱で、音の高低を変えます。能の小鼓では、4種の音を使い分けます。
実際に、小鼓らしい音が出るようになるまでには、習い始めてから、最低、5年ほどかかります。
小鼓の胴や皮は、それぞれに個性があります。実際に、打ってみてるとわかります。
簡単に音が出るけれど、音色がもう一つ、気難しいけれどはまると素晴らしい、等々。
さらに、鼓胴と皮には、相性があります。ピッタリの組み合わせなら、得も言われぬ音色がでます。逆に、そこそこの品なのに、組み合わせてみるとガッカリという場合もあります。なんだか、人間みたいです(^-^;)。
そんな訳で、いつのまにやら、小鼓コレクターになっていました(笑)。
鼓胴のいろいろ
手元にある鼓胴を紹介します。

蓮葉蒔絵鼓胴:見事な蒔絵の品です。蓮のデザインが流行した明治期の作。

貝尽蒔絵鼓胴:貝や海藻が描かれた品です。江戸後期。505gある重い胴。

芭蕉蒔絵鼓胴:大胆な芭蕉のデザインが斬新な品。江戸後期。

松葉蒔絵鼓胴:松葉紋で埋め尽くした品。江戸後期。

鉄線蒔絵鼓胴:昭和。

松鶴蒔絵鼓胴:チープな蒔絵の胴。重さはわずか285g。おもちゃのような品ですが、皮を選べば、不思議にも妙なる音色。

黒無地鼓胴:いわゆる烏胴。江戸初期。
骨董品としての鼓
鼓は楽器ですが、骨董品の要素も持っています。
1)まず、美しい。胴の蒔絵はもちろんですが、そのフォルムも洗練されています。落しを入れて、花活けにしてもなかなかのものです。
2)希少価値があります。能管ほどではありませんが、骨董屋さんではたまにしかお目にかかれません。特に時代の遡る品は数が少ない上に、名器が多いので、演奏楽器としての価値も加わります。
ネットオークションでも出品はされるのですが、どう見ても2級品ばかり。これはという品は、半年に1個あるかないか・・・・・・ところが、このところ、ビックリするような名品が、怒涛のように出品されています。世代交代?時代の変化?呉須赤絵みたいなものです。理由は不明ですが、買い時です。
私はどうかって? もう、どうにもなりません(^-^;)