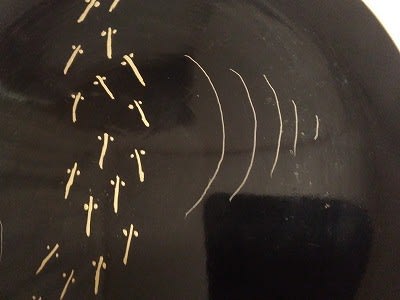かなり古い茶棚です。

幅 46.0㎝、奥行 34.5㎝、高 77.3㎝。中国、明ー清。
中央に収納部を備えた茶棚です。骨董屋の店先で私を待っていました。聞けば、高齢の趣味人の所から出た品とのこと。こんなのが一つ欲しかったので、私には珍しく即決となりました。さすがに野口先生では歯が立たず、福沢諭吉先生何人かのお世話になりました(^^;
左面:

右面:

背面:

あちこちに痛みがあり、目立たないように漆を塗りました。螺鈿の剥がれは、白塗りでお茶を濁しました(^^;
元々、かなり凝った造りなので、素人補修でもなんとか様になりました(^.^)



中央部は、2枚の戸をスライドさせて物を出し入れできるようになっています。扉の把手は蝶の形になっていて、玉製です。

文字の部分は、写真では白ペイントのように見えますが、
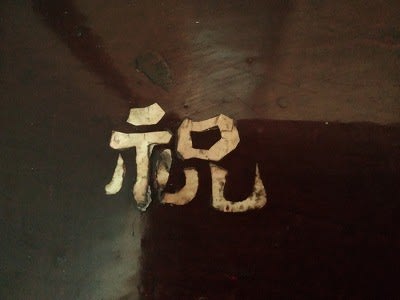
近づくと確かに螺鈿であることがわかります。
では、いったい何が書かれているのでしょうか。
天板の文字はわかりません。

中段:

福 自
天 来
丹 鳳
朝 陽
福自天来・・・雲の中に蝙蝠が飛ぶ図。吉祥画題。
丹鳳朝陽・・・朝日に鳳凰図。吉事、平和の象徴。
下段:

呈 (祥)
富 貴
芝 仙
祝 寿
呈祥は龍鳳、富貴は牡丹、 芝仙は霊芝を表し、長寿を祝う。
左面:

春 風
満 坐 (すべての人々)
十 里
荷 香 (荷=蓮)
春風がそこの人々すべてに吹きわたり、蓮の香りが十里にもわたって香る。
右面:

雲 中
白 鶴
左 琹(琴)
右 書
雲中白鶴・・・世俗を超越した高尚な境地にいる人。雲は高潔な境地のたとえ。
左琹(琴)右書・・・琴と書とともにある文人生活を表現。
棚物入扉:

倦夜 杜甫
竹涼侵臥内
野月満庭隅
重露成涓滴
稀星乍有無
暗飛蛍自照
水宿鳥相呼
萬事干戈裏
空悲清夜徂
竹涼(ちくりょう)は臥内(がだい)を侵し
野月(やげつ)は庭隅(ていぐう)に満つ
重露(ちょうろ)涓滴(けんてき)を成し
稀星(きせい)乍(たちまち)に有無
暗きに飛ぶ蛍は自ら照らし
水に宿る鳥は相呼ぶ
萬事は干戈(かんか)の裏
空しく悲しむ清夜の徂(ゆ)くを
竹林の涼気が寝室に入って来て、
野の月の光は庭の隅々にまで満ちている。
草葉の露は集まって滴となり、
まばらに浮んだ星がまばたいている。
暗闇の中に飛ぶ蛍は自分のまわりだけを照らし
水に宿る鳥は互いに呼び合っている。
しかし、静かで平和な自然の営みがある一方で、
世の中には戦いが渦巻いている。
私は空しく悲しむ。清らかな夜がふけていくのを。
この品を入手した時は、螺鈿の具合から、中国か李朝の品物か判断が付きませんでした。しかし、書かれた詩句を読んでみると、中国の品、それも文人にふさわしい物であることがわかりました。
これはもう、この茶棚に道具類を置き、煎茶をすするより外はありませんね(^.^)