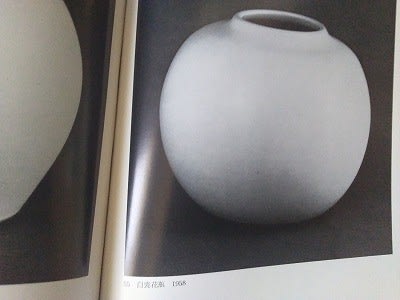昨日のブログで、古伊万里収集家Dr.Kさんが、古九谷の名品雉文小皿を紹介されていました。
ん!?そこまで古くはないが、古伊万里色絵小皿なら・・・といつものように後出しジャンケン大王の虫がうずいて、今回のブログと相成った次第です(^^;
この小皿は、最近、ネットオークションでゲットした品です。
陶磁器には、たまにしか手を出さない今日この頃ですが、この品ばかりはぜがひでも、と気張りました。かなりの人気で、このご時世の古伊万里としては、結構なお値段になってしまいました(^^;


横 12.5㎝、縦 10.9㎝、高台 7.9x6.2cm、高 2.4㎝。重 189g。江戸前ー中期。
上下に陽刻模様、中央に色絵で鵜飼図が描かれた四方小皿です。中央の絵付け部分は、両端が少し飛び出た変形皿です。周縁の鉄釉が、絵付け部分には塗られていないので、中央の絵付け部が、スクリーンのように浮かび上がっています。
生掛け焼成のせいでしょうか、上辺が少し歪んでいます。


高台の造りなどからすると、中期に近い品かもしれません。
あまり印象の良くない(ダメな品が多く)折れ松葉も気になります。
が、この絵付けには、いろんな懸念を吹っ飛ばすほどの魅力があります(あくまで個人的感想です(^^;)

陽刻部は、唐草模様です。

左の鵜は、魚を捕りに水中へ潜っていくところでしょう。


後絵も疑ってみたのですが、皿全体に全く表面疵が無いので、判断ができませんでした。
色釉の色調からは、古作と矛盾しないように思えます。
多くの図録をあたったわけではありませんが、鵜飼図の皿は、長良川鵜飼図の印判皿(明治時代)より他に見たことがありません。
大枚をはたいた甲斐があったかどうか、二匹の鵜に聞いてみたいです(^.^)
ps。鵜飼図印判皿にひと言。皿には、鵜飼が行われている下流に軌道のある橋が描かれています。ものの本には、東海道線の列車が通る橋となっていますが、これは岐阜市内の忠節橋で、その上を走るのは東海道線ではなく、名鉄谷汲線です(現在は廃線)。東海道線の鉄橋は、ここから5㎞ほど下流です。