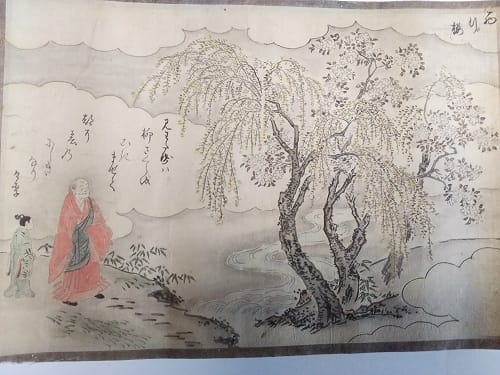伯庵茶碗
世に伯庵茶碗という名物があるそうです。
利休の弟子、医師伯庵が秘蔵していた黄瀬戸茶碗に由来します。
こういう品は約束がやかましく、私のようないい加減な人間には苦手な物です。
加藤唐九郎の原色陶器大辞典には、伯庵の十誓という10の約束事が記されています。
①枇杷色
②海鼠釉
③しみ
④三日月高台
⑤縮緬皺
⑥轆轤目
⑦きらず土(おから色の土)
⑧茶だまり
⑨小貫入
⑩端反り
伯庵手?黄瀬戸茶碗
先回の黄瀬戸茶碗を、この条件でチェックしてみます。
①枇杷色
きれいな枇杷色です。
②海鼠釉
海鼠釉と言えなくもない。
③しみ
大きな雨漏りがあります。
④三日月高台
NO. 付け高台では、あり得ません。
⑤縮緬皺
無し。
⑥轆轤目
見事な轆轤目があります。
⑦きらず土(おから色の土)
OKです。
⑧茶だまり
しっかりと、有り。
⑨小貫入
無し。
⑩端反り
無し。
総合すれば、55-60点というところでしょうか。
伯庵茶碗は、10個ほどあるそうですが、納まるところへ納まっていますので、一部の美術館をのぞいて、そう簡単に見ることができません。
ましてや、手に取ったり、お茶を喫することなどはあり得ません。
そこで、私のこの茶碗、大まけにまけてもらって、伯庵手?黄瀬戸茶碗の名をつけさせてもらい、もう少し育てていこうと思っています。
PS.
実は、この伯庵手?黄瀬戸茶碗とほぼ同一の品があります。
白山信仰の総本山、長滝白山神社は、古瀬戸黄釉瓶子(国重文)で有名ですが、若宮修古館(現在,改修中休館)の宝物庫にも社宝が収蔵されています。その中の一つが、今回の品と同じ手の黄瀬戸茶碗です。
「室町時代、茶碗」とだけ表示され、粗末なガラスケースにさりげなく入っていますが、まぎれもなく無傷伝世の黄瀬戸茶碗です。
白山神社、恐るべし。