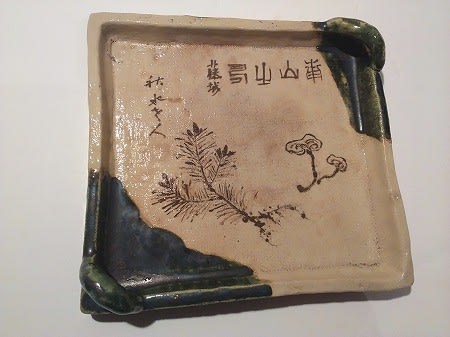いつのまにか、ブログ開設6年になりました。最近は文人書画を扱うことが多くなり、その中で6周年に相応しい品ということで選び出したのが今回の作品です。

全体:32.6㎝x128.7㎝、本紙(紙本):34.8㎝x204.6㎝。大正十三年春(三渓、56歳)。
【原三渓(はらさんけい)】慶応四(1868)年 ― 昭和十四(1939)年)。美濃國(岐阜県)佐波村生れ。実業家、美術品蒐集家、茶人。横浜に三渓園造設。若手画家を援助し、育てるとともに、自身も書画を嗜み、日本画や漢詩作品を多くのこした。
春の山里を描いた典型的な山水画です。
非常に透明感のある画面です。

山には、家々が身を寄せ合うように建っています。
あちこちに、梅の木が花を咲かせています。



実業家として成功をおさめた原三渓は、美術品コレクターであったと同時に、自らも書画をよくしました。これは、母方の祖父、高橋杏村の影響を強く受けたためです。杏村は三渓が誕生した年に亡くなっているので、直接指導を受けたわけではありません。しかし、三渓は高名な南画家であった祖父、高橋杏村を大変尊敬し、終始、心の師として、書画に研鑽しました。
原三渓は、書画集を出すなど、実業家の余技にはおさまりきらない質と量の書や日本画をのこしています。
そのうちで、今回の品は、彼の代表作の一つと言ってもよいでしょう。
通常の山水画は、雄大な山々が連なる山奥に谷川が流れ、ひっそりと佇むあずま屋が周りの自然にとけこんでいる情景が描かれています。これは、俗世間から離れ、精神の自由を求めて逍遊する文人の理想郷をあらわしています。
ところが、今回の山水画は、通常の山水画とは少し異なっています。奥深い山ではなく、何軒かの家屋、さらにはお寺が中央に描かれ、梅の花が咲きほこる山里の光景です。最下部の川面には、薪を運ぶ水夫・・・・世間から隔絶しているのではなく、人々の息づかいが聞こえそうな温かい画面です。
この絵を理解するには、どうしても、右上の讃(七言絶句)を読まねばなりません。

題春景山水図(私が作題(^^;)
長嘯臨風客養仙
看梅最好欲明天
依微当認前宵月
砕在渓橋清瀬邉
大正甲子春三渓併題
春景山水図に題す
長嘯、風に臨んで、客、仙を養う。
梅を看るに最も好(よ)きは、明なんと欲す天。
依微たりて、当(まさ)に認む前宵の月。
砕けて渓橋清瀬の邉り。
【長嘯(ちょうしょう)】声を長くひいて詩や歌を吟ずること。
【臨風(りんぷう)】風に向かう。
【依微(いび)】ぼんやりすること。
【前宵(ぜんしょう)】昨夜。
【渓橋(けいきょう)】谷に渡された橋。
風に向かって、朗々と詩を吟ずれば、旅人は術を得て、仙人になるかのようだ。
梅を観るのに最もよいのは、明けようとする空。
ぼんやりしているうちに、昨夜の月が天にあることに気がついた。
だが、それも砕けて、谷川にかかる橋や清瀬の辺りにある。
なんという幻想的で美しい詩でしょうか。
詩を吟じる旅人、そして長嘯するのも、おそらく、三渓自身。梅をみようと見上げれば、そこには夜明けの月が。やがてその月も落ちて、渓谷の橋や流れに消えていく。
原三渓は梅を愛した人です。三渓園には各地から名梅を移植して梅園が造られました(明治41年完成)。この梅をモチーフにした日本画の名作があります。三渓の支援によって才能を開花させた下村観山の代表作「弱法師(よろぼし)」です。彼は三渓園の臥龍梅に着想をえて、能に題材をとり、不朽の名作「弱法師」を描き上げたといわれています。


下村観山『弱法師』(大正4年、重文)
能『弱法師』では、人の讒言を信じた親に捨てられ、悲しみのあまり盲目となった俊徳丸が、四天王寺を彷徨います。そして、境内で梅の花の散る中、沈む夕日を心に留め、極楽浄土を想う日想観をなします。下村観山『弱法師』は、能『弱法師』のこの場面を描いています。作品からは、孤独と不安に苛まれながらも、心の闇を晴らそうとする俊徳丸の思いが伝わってきます。キーワードは、梅花と沈みゆく太陽。
一方、原三渓の今回の春景山水図の場合、画面からは山里の梅花が浮かびあがるのみです。しかし、添えられた讃(漢詩)を読むと、渓谷に沈んでいく夜明けの月が重要なモチーフであることがわかります。
下村観山の「梅花と夕陽」に対して、原三渓は「梅花と朝の月」。どうやら三渓は、観山の名作(大正4年)を意識して、今回の作品(大正13年)を書き上げたのではないかと思われるのです。また、大正12年9月には、関東大震災が起こりました。その半年後に製作された今回の作品は、震災復興に明け暮れていた三渓が、ふと、文人の世界に遊んでみたくなったのかも知れません。その際も、世捨人が隠棲する深山幽谷ではなく、人の温もりが感じられる山里を舞台にして書と画をしたためました。竹薮と梅花に埋もれた家々、川に浮かぶ小船、これらは三渓の故郷、美濃にごく普通にみられる風景です。大財界人として名をなした後も、彼の心は市井の人々や故郷の山河から離れた所にはなかったのです。
このように、原三渓の春景山水図では、漢詩『題春景山水図』が非常に重要です。よく、水墨山水画では絵と讃が表裏一体の関係にある言われます。恥ずかしながら、私はその意味がよく理解できませんでした。しかし、今回の作品に接して、讃の重要性がはっきりとわかりました。もし、この春景山水図に漢詩文が添えられていなければ、作品の魅力が半減するどころか、月並みな習作で終わっていたでしょう。
先に述べたように、三渓は、母方の祖父、南画家、高橋杏村の影響を強く受け、祖父の子、高橋杭水について絵画を学びました。
では、漢文、漢詩はどのようにして習得したのでしょうか。
原三渓は、慶応4年(明治元年) 、美濃国厚見郡佐波村(現、岐阜市柳津町佐波)の青木家長男(名、富太郎)として生まれました。幼少から非常に勉学を好んだ富太郎少年に、学問を手ほどきしたのが、近くの山田省三郎という人物です。青木家と山田家は、庄屋ー名主の関係(交代で担った?)にあり、省三郎は、勉学好きの富太郎の相談にのり、世話をしていました。そして、富太郎が14歳の時、大垣の儒者、漢詩人、野村藤蔭の鶏鳴塾で学べるよう計らいます。富太郎は、8㎞の道のりを徒歩で通いました。この時期に、原三渓は漢詩、漢文の素養を身につけたのです。
なお、この辺りは、洪水が頻発する地域でした。三渓の勉学の師、山田省三郎は、当時から治水事業に奔走していました。そして、生涯を治水にささげ、後に、「治水王」と呼ばれました。しかし、今ではほとんど忘れられています。
なお、私の母(故人)は、隣村の古刹の生れ、山田省三郎は伯父にあたります。