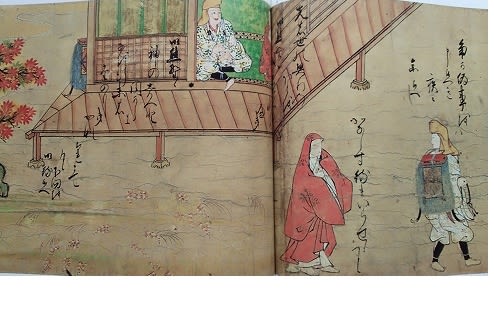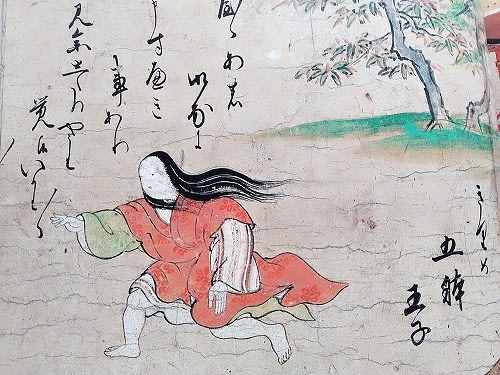不思議な絵皿の謎解き
先回の黄瀬戸の石皿のブログで、多くのコメントをいただいた不思議な絵付けの品です。
無地の黄瀬戸風石皿が径が32cmなのに対して、こちらの方は、37.5cmもあります。大きさも、石皿としては最大級でしょう。
どっしりと重い。
さて、問題の絵です。
もう一度、じっくりと眺めてみました。
真ん中にある炎にも、川のようにも見える所。この部分が、呉須で、薄く青色に塗ってあるではありませんか。
川です。
川を舞台に、男が逃げ、怪獣(のようなもの)が追いかけている。
上と下に2個ある花びらのようなものは、炎でしょう。
ピンときました。
これは、安珍・清姫伝説の一場面ではないだろうか?
ということで、道成寺縁起絵巻(国重文、『続日本の絵巻』中央公論社)を調べてみました。
ありました。
これです。
恋しさと怒りのあまり、毒蛇に変身しつつある清姫が、安珍を追いかける場面です。
道成寺縁起絵巻
道成寺縁起絵巻は、古くからある物語をもとに、室町時代、15世紀後半に描かれた絵巻です。
奥州から熊野詣にやってきた青年僧に恋慕した人妻が、逃げる僧を追って大蛇となり、道成寺の鐘のなかに隠れた僧を焼き殺す。その後、道成寺の僧たちの供養によって、両人共に昇天して天人になるという物語です。
宿の人妻に言い寄られた青年僧は、熊野詣の途中だからと断り、熊野からの帰りには、立ち寄ることを約束して立ち去った。
女は、約束の日になっても姿を見せない僧のことが不安になり、旅の人々に行方を問う。
「若い僧をみかけませんでしたか?」
「もうとっくに、通り過ぎましたよ」
「さては私をだましたか」
女は、髪を振り乱し、胸元、脛もあらわにして、必死に探し駆けまわる。「ええい、くやしい。あの坊主をとっつかまえるまでは、心がおさまらぬ。恥もなにもあったものか。草履が片方失せようとも、かまわぬ」
すると、前方に若い旅僧の姿が。
「もしや、あなたはあの日の僧では?」
「いや人違いです。そんなにおっしゃっても、はなはだ迷惑です」
と言って、若僧は大股に走り去る。
みるみるうちに、女の顔が変わった。
目はつり上がり、口は耳元まで裂け、
口から吐く息は、大きな炎となって・・・・
「やれまてい。己をどこまども行かせるものではないぞよ」
女は、怒りで、ついに大蛇に変身。襟元からは、鱗のはえた蛇の生首がニョキッと。
目は爛々と輝き、口からは火炎を吐いている。
僧は逃げながら、必死に観音を念じる。
「先世にいかなる悪業を作て今生にかかる縁に報らん。南無観世音、此世も後の世もたすけ給へ」
日高川に来た僧は船で増水した川を渡る。
船頭は、女を渡そうとしない。
しかし、女は、着物を脱ぐと、たちまち、一匹の毒蛇となって川を渡った。
道成寺に逃げ込んだ青年僧。
鐘を降ろして、かくまう僧たち。
日高川を渡った蛇は、ついに道成寺の境内に現れた。
三時ばかり焼きつくした後、大蛇は両眼から血の涙を流しながら、もと来た方へ帰って行った。
人々は、水をかけて火を消した。
鐘の中からは、墨のようになった僧が。
住持は、二人が蛇道に転生した夢を見た。
聞けば、焼けた青年僧と大蛇に変身した女だと言う。
僧たちは、法華経供養を営んだ。
老僧の夢に、二人が天女の姿で現れた。
二人は、熊野権現と観音菩薩の化身だったことを明かすと、別々に、虚空の彼方へ飛び去っていった。
道成寺縁起絵巻は面白い
とても、室町時代に描かれた物とは思えません。
劇画を見るようです。
特に、人物の描写が迫力満天。
怒りがつのって、女が次第に大蛇に変身していく描写は圧巻です。女の表情、髪、衣服など、細部わたって変身の様子が描かれています。
若僧が、なりふり構わず逃げる姿も真に迫っています。
主人公の女は、娘ではなく、何と人妻。それが、美しい若僧に一目惚れし、夜這いをかけるのですから、ビックリです。
若僧の焼死体もリアルです。
安珍、清姫の名は、絵巻には出てきません。絵巻の主人公の女は人妻ですが、能や歌舞伎の道成寺では、娘で、真砂の清次の娘となっています。その後に演じられるようになった浄瑠璃から、清姫となったようです。
なお、道成寺絵巻の末尾には、花押と但し書きが添えられています。
この花押は、最後の室町将軍、足利義昭のものです。
織田信長によって、将軍職に就いた義昭ですが、その後、信長と不仲になり、軍を挙げて信長に挑んで敗れ、各地を転々とします。
そして、紀州の興国寺に滞在したとき、道成寺からこの絵巻を取り寄せ、読んだと言われています。義昭は、絵巻を絶賛し、花押を記したと言われています。
義昭は、道成寺縁起絵巻のどこに惹かれたのでしょうか。
怒りと怨念の塊となった女に追われる若僧を、信長から逃れて各地を転進する自分に重ねたのでしょうか。
室町幕府を滅亡にみちびいた無能の将軍、と揶揄されるなど、散々な評価の義昭です。が、信長の死後、別格の大名として秀吉に重用され、室町歴代将軍の中では、最も長命でした。
似たような人物として、徳川慶喜が思い浮かびます。
足利義昭は、案外、聡明でしたたかな人だったのかもしれません。