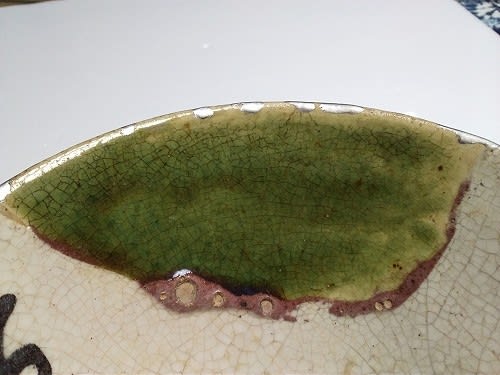一時にくらべれば、少し涼しくなってきました。
夏の間、伸び放題の草をとらねばなりません。
ところが、暑さで姿を隠していた蚊が、ここぞとばかりに飛び回るようになりました。
私は、特に、蚊に好まれる体質のようです。
ほんの少しの草取りですら、蚊の集団に襲われます。
何とかしなければ。
そうだ、ハーブ。これならいけるかも。
ということで、家の周りにあるハーブを探してみました。
かつては、ものすごい勢いではびこっていたハーブの類、のけ者にされ、今は、細々と命をつないでいます。
探し当てたのは、5種類ほど。
ハーブといってもさまざまですね。
そのうちで、極端に臭いのきつかったのがこれ。

ローズマリーです。優雅な名前とは似ても似つかぬ強烈な臭い。

これならいけるぞ。

葉を少し手に取り、朝顔の葉を揉む要領で、両手で揉み擦りました。

しかし、葉は全くつぶれません。臭いはするのですが、液が出なければ、肌に塗ることができません。

アルコールがあったのを思い出しました。

葉を摘んで、アルコールに浸けました。

2日もすると、濃い緑色の液体が。
これはいけそう。

手と腕に塗って、さっそく草取りです。
向かいには竹藪。そこから藪蚊が出張して来て、毎回、刺されまくっていたのですが、
この日は無傷。
大成功!

これに気をよくして、別の場所へ。
いちじくの大木です。日本いちじくで、大変味がよいのですが、採るのに時間がかかります。その間に、蚊の猛攻撃を受けるのです。
さて、ハーブ液の効果は?
残念。塗らない時の3分の1くらいの刺されようですが、完ぺきではない。よく見ると、ズボンやシャツの薄い部分に喰らいついているヤツさえいます。
ここの蚊は、数も多いし、獰猛。
作戦を練り直して、いちじくが終わらないうちに、再度挑戦です。