庭の花でダッチアイリスが咲きましたので、
その関連としてアヤメの仲間を取り上げます。
アヤメの仲間
アヤメ(アヤメ科)の中にはアヤメ、ハナショウブ、カキツバタ、イチハツ、
キショウブ、ドイツアヤメ(ジャーマンアイリス)等あります。
外出自粛で家周りの限られた範囲と時期的に少し早いのでアヤメの仲間の一部です。
後日に機会が有れば、まとめた形で特徴等、取り上げてみたいです。
▼ダッチアイリス(オランダアヤメ)
アヤメ科アヤメ属、多年草、花期:4月~5月、


もう一株はまだ蕾状態です。
道端に丁度今が見頃で咲いています。






▼ジャーマンアイリス(ドイツアイリス)
アヤメ科アヤメ属、多年草、花期:5月~6月、
切花、花壇用に栽培、ヨーロッパ原産の数種のアイリスを交雑した園芸品種。
虹の色(レインボーフラワー)とも呼ばれ、色とりどりの花を咲かせ華やかで品種多い。
少し早いのでジャーマンアイリスかどうか、花の根元付近が黄色くヒゲがあるのでアイリスとした。







▼シャガ(射干)
アヤメ科アヤメ属、常緑多年草、中国原産、花期:4月~5月、
春に茎を斜めに伸ばして、その先に白地に青い斑点が入る花を多数咲かせます。
人里近くの湿地に自生しているので、名前は知らなくても よく見かける花ですね。
家の周りのあちこちに咲き始めています。丈夫な花です。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー





















 赤い蕾の方は場所が違うので、葉は健在です。
赤い蕾の方は場所が違うので、葉は健在です。


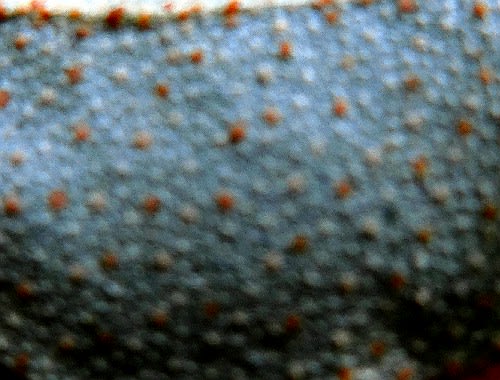


 の
の










































































































































 *3輪咲きを見つけました4/9追加
*3輪咲きを見つけました4/9追加





 ジジババに見えますか?
ジジババに見えますか? 













