数日前から
雪虫がフワフワと飛ぶ姿が見られるようになりました。
こちらもいよいよ冬のようです。

北海道や東北地方では
初雪の降る少し前に出現するとのこと。
当地の今朝の外気温は5℃
空は灰色の雲に覆われていて
北風強く今にも雪が舞い落ちそうです。

雪虫の正式名は「リンゴワタムシ」
リンゴの木の枝や根に寄生する害虫
白い蝋物質を分泌して体にまとい
フワフワ飛ぶ姿が雪のようだとして
雪虫の名があります。
寿命はわずか1週間ほどで
メスは産卵後に死んでしまい
熱にも弱く
人間の体温でも弱るそうです。
飛んでいる雪虫を
掌にそっと包んだつもりでしたが
体にまとっていた蝋物質は簡単に取れてしまいました。
その後も飛んでいたので命に別状はなかったようですが
蠟が取れて可哀想なことをしました(>_<)💦

皺だらけの手で失礼しました~(^^;)
翅は透明で白い蝋物質が無ければ一見蚊のようですが
これでもアブラムシ科なんだそうです。
今週は今日からどんどん寒くなる予報です。
雪虫も来たことですし
石油ストーブを出して寒さに備えようと思います。
皆さんも風邪などひきませんよう
温かくして下さいね~(^_-)-☆
※ 参考ーウィキペディア
原色学習ワイド図鑑(学習研究社)
































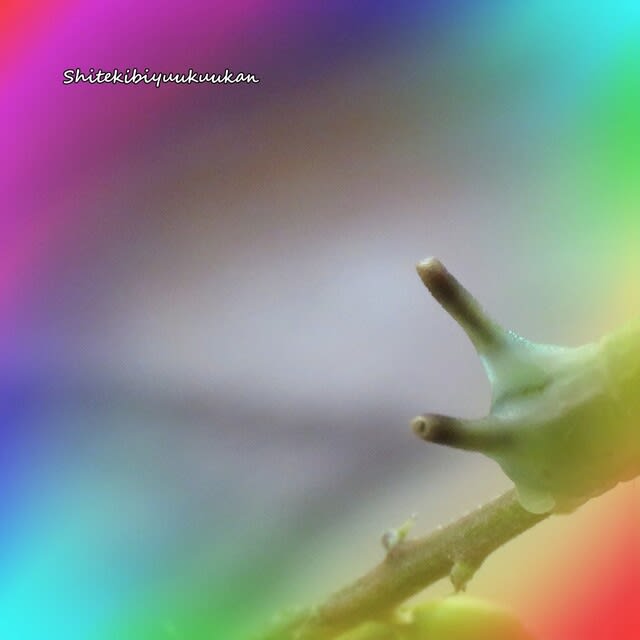





























 いつ飛び立つんだろう?
いつ飛び立つんだろう?









