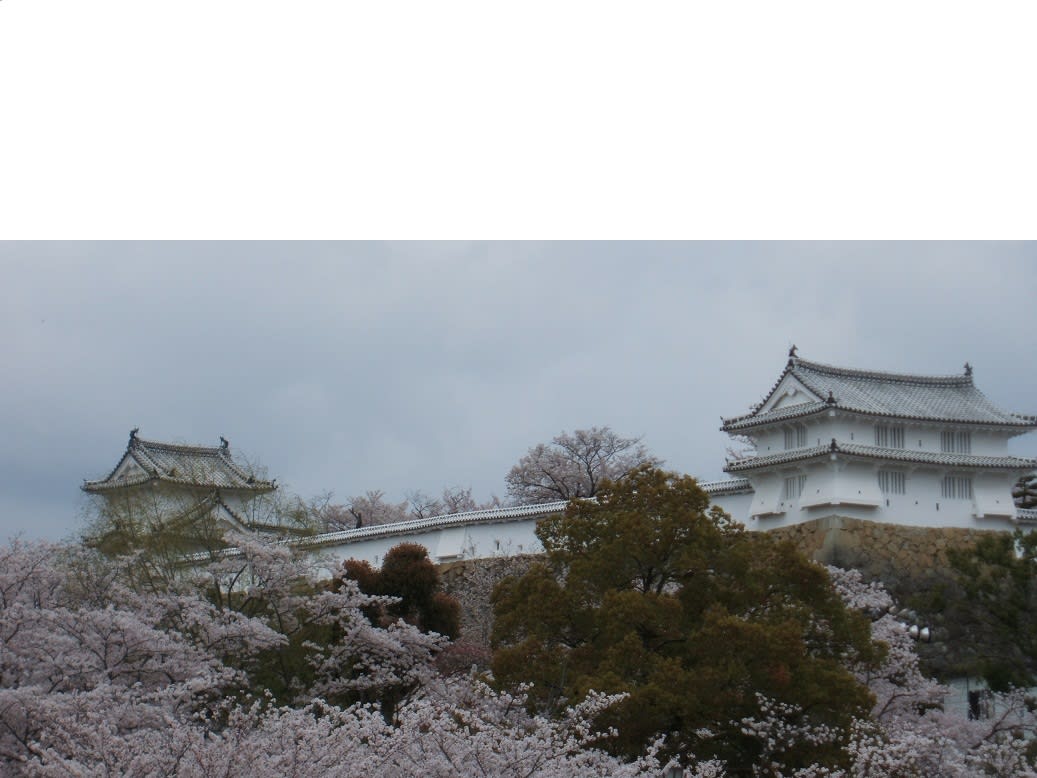忍耐の地中生活
この穴はヒロ画伯のイタズラの跡ではない。
アブラゼミの幼虫が這い出てきた穴である。
今ではカエルがちゃっかりと夏の暑さを避けるために使っている。
アブラゼミの卵は木の幹や枝の中に産みつけられて、その中で冬を越して
翌年孵化(ふか)する。
そして、孵化した幼虫は地上に落ち、自分の前足を使って、地中にもぐっていく。
土中にトンネルを掘るため、前足はモグラのように大きく丈夫だそうだ。
そのトンネルの中で、木の根の樹液を吸いながら成長していくのだが、
その幼虫の期間は6年間にも及ぶ。
人間で言えば、生まれてから小学校に入るまでの期間がかかるのである。

最善の選択
6年間の地中生活を終え、いよいよ7年目、再び地上に姿を現し、
木の幹や枝などに登って羽化するわけだが、
この写真が羽化したあとのぬけがらである。
この中身であるアブラゼミは昨年の7月に羽化した。
羽化はセミの一生の中で最も危険な時だろう。
羽化するまでに地上に落ちればアリのえじきとなる。
そして、羽化の途中で鳥などの外敵におそわれてはひとたまりもない。
しかも、羽化直後はまだはねは縮んでいるし、柔らかい。
はねを伸ばして固くなってからでないと飛び立てないのである。
そしてさらに難儀なことに、はねが固くなる前にものにふれたりすると、
形が変わってしまうというのだ。
だから、羽化前の幼虫は、どこが適当なのかをしっかり考えて、
場所を選ばなければならないのである。
してみると、このアブラゼミのぬけがらは大したものだ。
前足でがっしりとサザンカの葉を抱き込み、
昨年の7月に羽化してから9ヶ月間も、まだ生きているかのように
しがみついている。
6年もの時を経て、やっと生れ出た命だ。
「決して無駄にはしまい」という必死さが伝わってくるのである。
また、このサザンカは藤棚の下にあって、外敵から襲われにくい。
そして、雨や風にも当たりにくいところにある。
小さな幼虫がここまで考え、最善の選択をした場所なのである。
この幼虫、真に天晴れである。
これだけ苦労して飛べるようになったというのに、自由に動ける成虫の
期間はわずか1ヶ月足らずということだ。
それを思えば、庭で鳴くセミの声が「うるさい」などと言ってはおれない。
また今年もしばし我慢することにしよう。
この穴はヒロ画伯のイタズラの跡ではない。
アブラゼミの幼虫が這い出てきた穴である。
今ではカエルがちゃっかりと夏の暑さを避けるために使っている。
アブラゼミの卵は木の幹や枝の中に産みつけられて、その中で冬を越して
翌年孵化(ふか)する。
そして、孵化した幼虫は地上に落ち、自分の前足を使って、地中にもぐっていく。
土中にトンネルを掘るため、前足はモグラのように大きく丈夫だそうだ。
そのトンネルの中で、木の根の樹液を吸いながら成長していくのだが、
その幼虫の期間は6年間にも及ぶ。
人間で言えば、生まれてから小学校に入るまでの期間がかかるのである。

最善の選択
6年間の地中生活を終え、いよいよ7年目、再び地上に姿を現し、
木の幹や枝などに登って羽化するわけだが、
この写真が羽化したあとのぬけがらである。
この中身であるアブラゼミは昨年の7月に羽化した。
羽化はセミの一生の中で最も危険な時だろう。
羽化するまでに地上に落ちればアリのえじきとなる。
そして、羽化の途中で鳥などの外敵におそわれてはひとたまりもない。
しかも、羽化直後はまだはねは縮んでいるし、柔らかい。
はねを伸ばして固くなってからでないと飛び立てないのである。
そしてさらに難儀なことに、はねが固くなる前にものにふれたりすると、
形が変わってしまうというのだ。
だから、羽化前の幼虫は、どこが適当なのかをしっかり考えて、
場所を選ばなければならないのである。
してみると、このアブラゼミのぬけがらは大したものだ。
前足でがっしりとサザンカの葉を抱き込み、
昨年の7月に羽化してから9ヶ月間も、まだ生きているかのように
しがみついている。
6年もの時を経て、やっと生れ出た命だ。
「決して無駄にはしまい」という必死さが伝わってくるのである。
また、このサザンカは藤棚の下にあって、外敵から襲われにくい。
そして、雨や風にも当たりにくいところにある。
小さな幼虫がここまで考え、最善の選択をした場所なのである。
この幼虫、真に天晴れである。
これだけ苦労して飛べるようになったというのに、自由に動ける成虫の
期間はわずか1ヶ月足らずということだ。
それを思えば、庭で鳴くセミの声が「うるさい」などと言ってはおれない。
また今年もしばし我慢することにしよう。