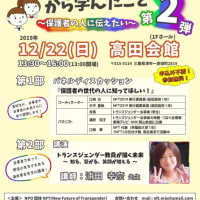令和4年2月20日(日)、オミクロン新型コロナウイルスの勢いが衰えない中、交流会は無事に開催されました。
参加者の親御さんから感想をいただきましたので、お届けします。
初めてのお三方を含めて七組の参加者の皆さんで会は進行しました。FTMの当事者のお一人を除き、あとはお子さんのLGTの問題で来られた親御さんでした。皆さんからお話を伺うことが出来ました。
マイノリティである子どもが親にカミングアウトするまで思い悩み、どのように打ち明けようかなど、葛藤の日々を過ごしていたに違いありません。「今日こそは言おう」と思いながらも、勇気がしぼみ、言えない言いわけを見つけては先延ばしにしていた子どもがほとんどのはずです。
そしていよいよ親にカミングアウトする時を迎えます。そこでマイノリティは子ども側だけの問題ではなくなります。その親もまたマイノリティという一面が加わった自分の人生を歩み始めることになります。
親は自分の子どもの様子にどこか不安を感じていたところ、そのようなカミングアウトを受け、思い描いていた未来が思い通りに行かないということを思い知らされます。初めての自分の感情と向き合いながら日々を過ごしていくことになります。
親子関係も話さなければならない新たな事柄が噴出し、その都度考えの違いもあり、衝突も避けられない場合も出てきます。親は子どものことを思うため、子どもはなんで親はわかってくれないんだ、という感情からお互いに傷つけあう口論に発展することも、どの家庭でも起こりえます。
FTMの参加者の方の発言でハッとさせられた親御さんがほとんどだったはずです。*1子どもは自分でも自分という人間がわからない、自分でも自分の気持ちがわからない、このなんとも言えない不安定なもやもやを言語にすることが出来ない、本当に分からない。それ故、究極に相手を傷つける言葉を吐いてしまう、というようなお話をされました。
本人も分からないのです。そして親も分からないのです。
また、少し社会の変化を感じたのは保育園に通っているお子さんのことで来られた親御さんのお話からでした。4歳半のそのお子さんは2歳の頃から自分の性とは違う好みを示してきたそうです。保育園の先生は理解を示してそのお子さんの意のままを受け入れてくださっているようです。
この話から派生して、小さい頃から男の子は男らしく、女の子は女らしく、という考えをなくしていこうという動きもあることを知りました。*2
これからは教育現場での先生方の意識が大変重要であると感じました。
グループワークの後のシェアである親御さんのコメントが印象的でした。
みんな同じなんだ。
まともだから悩むんだ。
死ぬなんて考えないで欲しい。
参加者の皆さんは会場に入ってきた時より少し表情を明るくして帰っていかれました。
*1セクシュアリティで悩む子どもの言語と親の言語は違う、という言葉が印象的でした。同じ日本語なのに通じ合えないもどかしさ、セクマイ親子あるあるですね。
*2にじいろ保育の会(多様性を考える保育士研究会)・・・「~らしさ」というジェンダー規範を幼児の生活から薄めていこうというスタンスの保育士さんは、性別違和の子どもを持つ親にはとても心強い味方です。最近は、ジェンダーニュートラルな個人マークシールの商品開発のクラウドファンディングを立ち上げ、着々と実践に向かっている様。子どもたちの未来を変える為には、子どもに関わる大人たちの意識改革が重要ということですね。 [M]