衆院憲法審査会の野党筆頭理事である立憲民主党中川正治議員の主張を読んだ。
主張の要旨は、「改憲論議よりも国民投票法のCM規制を優先論議すべき」との従来主張を繰り返すとともに、党の「論憲姿勢」を強調してのPRに努めるものであったが、『・・・権力の暴走を国会がいかにコントロールし・・・国会がどう首相を管理下に置くかという意味では議員任期延長も議論する必要はある』としている点が立民の憲法観を端的に示しているように感じた。
憲法41条では『国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関」と定めているが、最高機関との語句について種々の解釈が行われている。代表的な解釈は
・統括機関説- 国会は、国権の最高機関として内閣、裁判所の上位に君臨し、国政全般にわたって最終的な決定権を有する。
・最高責任地位説 - 国会は、国権の最高機関として国民に対して国政全般の責任を負い、行政、司法作用を調整する。とされている。
国会議員としては、統括機関説に依って国家運営を担当したいところであろうが、責任の所在がはっきりしない国会に行政・司法まで預けるのは危険すぎるように思える。そのことは、司法が権力に阿る韓国での徴用工賠償判決を見れば十分であり、寸秒を争う震災や防衛出動に出動に対して国会の小田原評定が適切であろうかとの疑問を持つ。
現在の日本にあっては、緊急の決定は内閣が行って○○日以内に国会に報告する若しくは国会の承認を得るという法律が多いところを見れば、国会は行政、司法を調整するという最高責任地位説に依って運営されているように思えるが、立憲民主党の憲法観は統括機関説にあるようである。
中川議員は、、ジョージタウン大学(ワシントンD.Cに本部を置く私立大学で、 政治や国際関係などの学問では世界最高峰の大学)の外交学部国際関係学科卒業し、国際交流基金に勤務された後に政界に転じたとされているので、政治や国際関係に通じておられるように思う。それならば猶更に、国会の地位に関する憲法規定が曖昧であるという問題点は十分に承知されておられると思うが、それに触れることなく「首相を管理下に置く」とサラリというところは、いかにも立民議員であるように思える。
長年に亘って野党に甘んじ、一旦は手にした政権も「空白の3年間」との評価が定まり、現状打破の政策提言では維新に後れを取り、と散々な立民が縋るのは「論憲」と糊塗した強固な護憲によってコアな有権者を繋ぎとめるしかないのであろう。
尖閣・チベット・台湾問題には「中国は最大の貿易相手」と煙幕を張り、アフガンでは沈黙し、ウクライナを多山の石と観ることも無く、・・・。立民は、何時まで現下の国際情勢に目を閉じ続けるのだろうか。














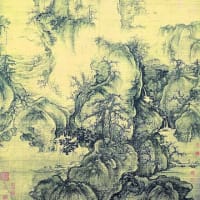





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます