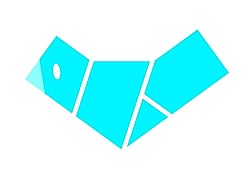県内の障害者が作った食品などを販売する「長崎福祉の店 ふれあいショップ」が20日、佐世保市本島町のトゥインクル西沢8階催事場で始まった。24日まで。
82の福祉施設でつくる「街かどのふれあいバザール運営委員会」が、自立や就労を目指す障害者が手がけた商品の販路を広げ、福祉への理解を深めようと、1991年から県内各地で開いている。
会場には、11施設が出品したクッキーやジャム、木工品、縫製品、小物類など約1600点が並び、来場者が品定めしていた。ミカンのジャムを購入した同市三浦町の山田よし子さん(65)は「障害のある人たちが働ける場所が少しでも増えれば」と話していた。
午前10時~午後6時。問い合わせは運営委事務局の県社会福祉協議会(095・846・8022)へ。

障害者が手がけた商品を品定めする来場者
(2013年3月21日 読売新聞)
82の福祉施設でつくる「街かどのふれあいバザール運営委員会」が、自立や就労を目指す障害者が手がけた商品の販路を広げ、福祉への理解を深めようと、1991年から県内各地で開いている。
会場には、11施設が出品したクッキーやジャム、木工品、縫製品、小物類など約1600点が並び、来場者が品定めしていた。ミカンのジャムを購入した同市三浦町の山田よし子さん(65)は「障害のある人たちが働ける場所が少しでも増えれば」と話していた。
午前10時~午後6時。問い合わせは運営委事務局の県社会福祉協議会(095・846・8022)へ。

障害者が手がけた商品を品定めする来場者
(2013年3月21日 読売新聞)