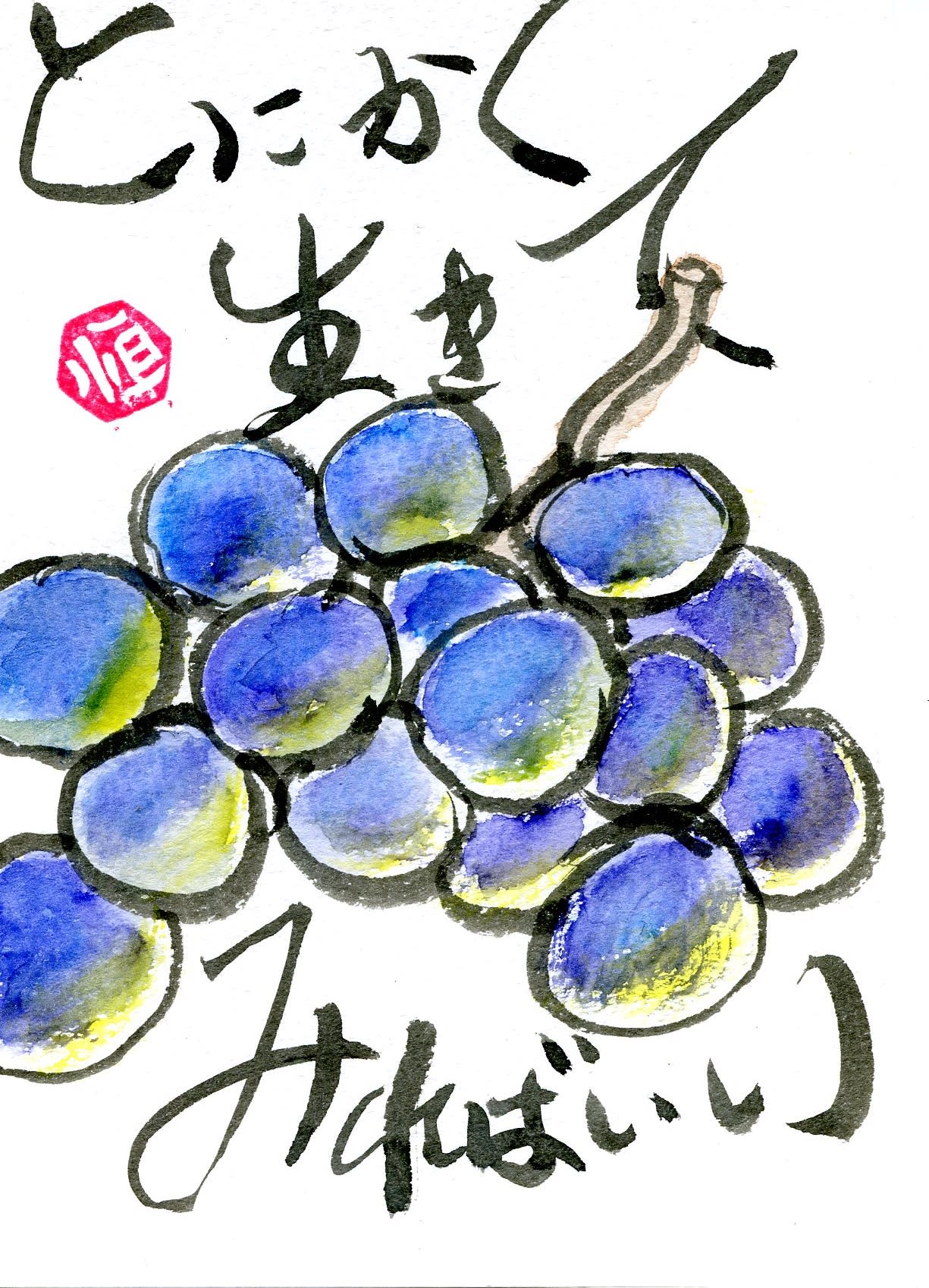
http://blog.goo.ne.jp/admin/newentry/#
「ジリジリ、ジー……」と、やたら油蝉が喧しい。夏になるといつもこうだ。
なびいていた風がピタッと止まる。クーラーのない部屋は一挙に暑さを増す。窓を開け放しても効果は殆どない。ジトーッと掻いた汗を手拭いで拭うと、苛立っている自分に気付く。甲斐文夫は、脚を無造作に投げ出した。
「またー!もうゴロゴロしてられちゃ、少しも片付かへんわ」
真奈美の癇性な声が襲い掛かる。
妻のヒステリックな声は、もう慣れっこのはずだが、こう暑いとカチン!と来る。苛立ちに拍車が掛かる。文夫は時計に目をやった。
「ちょっと、そこらを歩いて来るか……」
文夫は聞こえよがしに言った。
「そう。その気になったら、さっさと動く!」
真奈美に悪気がないのを、文夫は誰よりもよく知っている。夫婦になって20年以上。相手の考えは、すぐ判る。文夫はそそくさと部屋を出た。妻に逆らって碌な事はない。
ムッとする淀んだ外気に顔が歪んだ。
(こりゃあ家で寝転んでいた方がマシだったかな)真奈美の邪険な扱いを無視出来る図々しさを文夫が持ち合わせていればの話である。文夫は、いたって控え目なのだ。
文夫が住むのは、住人の大半が兼業農家という田舎だった。古くからの家ばかりで、付き合いが大変な集落である。ここで生まれ育った文夫は、高校を卒業するとすぐ町に仕事を求めた。結婚もした。子供も授かった。暫らく住んでいたが、結局田舎に戻った。
親が家を建ててくれた。万全の用意で迎えられたのだ。町でうだつの上がらぬ暮らしをしていた文夫は、これ幸いとばかりに家族を引き連れて帰郷した。
「暑いのう」
隣家の隠居だった。骨に皮が貼りついたガリガリの老人である。別に健康を損なっていないのに、いつも寝間着姿で、家の周囲をウロウロしている。雑草を見つけると、まるで憎い敵と遭遇したかのようにグイグイと引き抜く。一本も残さない。お陰で彼の家の周囲は雑草知らずだ。
隠居はギョロッと文夫を見た。生ける屍を連想させる。ゾンビそのものだ。
「ほんま。死にそうな暑さやねえ」
「あ~ん?」
隠居は耳が遠い。これまで何度も話し掛けて同じ目にあった。一度で通じた例がない。最低3度は繰り返すはめになる。
「ほんまに地獄の暑さ……」
「そうよ。全く死んだ方がマシじゃあ。こう暑いと、何も出来よらんで」
珍しく2度目で通じたらしい。大声でブツブツ言っている。いきなりしゃがんだ。足元に雑草の芽を見つけたのだ。その目敏さは凄い。血管が露骨に浮き上がった手を伸ばして雑草の芽を引き抜く。ケラケラと笑った。まだ当分はくたばりそうにない。
きつい日差しを避けて神社に足を向けた。結構大きい社殿がある。秋には氏子が繰り出す5基の祭り屋台が練り合う。年輪を刻んだヒノキの大木がそそり立って、神々しさを際立たせている。さすがの日差しもヒノキの枝葉に遮られて、差し込めない。涼しさを求めるなら、この上ない場所だ。
裏手に広がる豊かな山並みは、過去にゴルフ場開発話の舞台となった。京阪神に近い立地を、開発業者が見逃すはずはない。村は二分したが、結局良識派が勝利した。文夫にはどうでもいい話だった。あえて言うなら、田舎は田舎、自然は自然のままであってほしい。
本殿に上がる石段に尻を下ろした。二対の狛犬に見下ろされる位置だった。文夫は手拭いでごしごしと顔の汗をぬぐった。首筋も丹念にこすった。少しは気持ちが良くなる。
(今日は来るかな……?)
とりとめもなく考えた。文夫が神社に足を運んだのは、ある期待もあってのことだ。家で聞いた蝉の鳴き声が時雨になって境内に降り注ぐ。腕時計を確かめた。10時を回っている。文夫は境内の入り口を見やった。気配を感じたのだ。すぐその正体が姿を見せた。
茶褐色の犬がちょろちょろと動く。柴犬の血が入った雑種の犬。よく知っていた。文夫の匂いをかぎ取って、犬はいきなり顔を上げた。こちらに向かってしゃにむに駆け出した。文夫が差し出す手の中に飛び込んだ。しきりに尾を振る。熱い舌で所構わず舐めた。
「こらこらチビ、止めろ。止めろって」
ポケットに用意していた竹輪を呉れてやると、チビは夢中で食べた。
「おじさん。チビ、喜んでいるよ」
いつの間にか、見知った顔が覗き込んでいた。小学生の康之と母親だった。彼女と目が合うと、お互いに静かな会釈を交わした。
「チビにご馳走してくれたんだ、おじさん」
「いつも、ごめんね」
母と子は同じ仕草で文夫に頬笑んだ。
母親は文夫のよく知った相手だった。幼馴染み。そして初恋の……!6年前の夏、偶然境内で彼女に再会した。髪型と化粧ですっかり変わっていた吉沢志保子は、昔と変わらぬ声で話し掛けて来た。
「あ?甲斐くんじゃないの?」
「え?……そうだけど」
「わたし、吉沢志保子。覚えてる?」
忘れてはいなかった。文夫の記憶にちゃんと刻まれている。よくよく見ると、志保子の面影はしっかりと残っていた。幼馴染みで、高校生の頃付き合い始めた。周囲も好意的に見てくれた。しかし、人生は、そううまく運びはしない。
バイク事故がすべてを変えた。人身事故だった。同乗の志保子と、はねた相手が病院に運ばれた。問題は大きく広がった。無免許で警察沙汰。結局学校は辞めた。必然的に志保子と文夫に距離が生まれた。田舎の保守性は文夫に容赦なかった。痛めつけられた末、罪悪感に支配された文夫は、どん底まで落ちた。
志保子に連絡を取ろうとした文夫を、彼女の両親は露骨に拒絶した。元校長の父親と、教育委員会に務めていた母親を前に、非行少年の烙印を押された文夫になすすべはなかった。志保子が東京の大学へ進むと、もう文夫とは縁のない人となってしまった。
懐かしい志保子の笑顔は眩しかった。それでも文夫は、素知らぬ顔で対応した。昔と違って彼は分別を備えた大人だった。昔馴染みと旧交を暖めると割り切った。最初こそ……。
「すっかり変わっちゃったなあ」
「今は胡桃沢志保子。結婚して大阪人になっちゃった。甲斐くんは、どうなん?」
「俺?ああ、結婚してる。子供は3人だ」
「ああ、幸せなんや」
「俺?うん。まあ、そうかな……」
取り留めのない話が続いた。志保子は何のこだわりも見せなかった。ただ明るかった。昔そのままに。文夫の胸は軽く痛んだ。
夏休みになると、志保子は必ず帰郷した。再会の翌年は赤ん坊を連れて帰った。それからは年々成長する息子の康之と一緒だった。子供を見つめる志保子の目は母親のものだった。母性は彼女を一層美しくさせている。
文夫は母親になった志保子に戸惑いながらも、調子を合わせた。夏休みの出会いで得た胸のときめきを守るために、懐かしい昔馴染みであり続けた。
「もう、田舎には帰ってこられなくなりそう」
「え?」
「中東の方へ夫が赴任するの。付いていかなくちゃあ。彼ね。単身赴任でいいって。でも放っておけないでしょ」
志保子は笑顔を文夫に向けた。ドキッとしたが、取り澄ました笑顔で頷いた。彼女がどんなに夫を、家族を愛しているか、よく分かる。
「吉沢もいい嫁さんになったなあ。頑張れよ。あ?俺が言う事じゃなかったな」
「そんなことないよう。うん。頑張る。でも、甲斐くんと、もう会えなくなるね」
「そうだな」
「楽しかった、本当に。夏休み…私には、高校生の頃に戻れる束の間のシーズンだった」
志保子の声が文夫の感情に突き刺さる。
(なに考えてんだ、俺。ヒトの嫁はんやのに……昔は帰らへん……そやけど……?)
「おじさん。明日、お家に帰るね」
康之が母の腰に手をまわして、文夫を見上げていた。文夫は心の動揺を慌てて隠した。
「おう、そうか。帰ったら、お父さん、喜ぶぞ」
「うん。喜ぶよ。大好きだもん、お父さん」
康之の笑顔が、文夫の立場を如実に語っていた。志保子がペコリと頭を下げた。
境内を出てぶらぶらと歩いていると、駆けてきた子供らとぶつかった。文夫の末っ子の太知がいた。母親にそっくりの顔をしている。
「どうした?」
「境内で野球すんだよ。俺、今日はピッチャーさせて貰えるって」
「そうか。そいつはよかったなあ。頑張って投げて来い。負けんじゃねえぞ」
「当たり前じゃん。俺、父さんの息子だぞ!」
思わず太知の顔を見直した。そして、頷いた。(そうだ。こいつは俺の息子だ。うん!)
「暑いのう、堪らんわい」
隠居だった。ギョロッとした目が文夫に向けられている。エンゲ(縁側)の板間にだらしなく座り込んでいる。
「暑いいうてからに、悪さすんじゃねえぞ」
ドキッとしたが、さりげなく応じた。
「俺は、真面目だけが取り柄じゃ。おやっさんも、ずーっと昔に言うてくれたやんか」
正気じゃないかも知れない隠居に、えらく饒舌な自分に気付いた。きっと暑さのせいだ。
「ジリジリ、ジー……」と、やたら油蝉が喧しい。夏になるといつもこうだ。
なびいていた風がピタッと止まる。クーラーのない部屋は一挙に暑さを増す。窓を開け放しても効果は殆どない。ジトーッと掻いた汗を手拭いで拭うと、苛立っている自分に気付く。甲斐文夫は、脚を無造作に投げ出した。
「またー!もうゴロゴロしてられちゃ、少しも片付かへんわ」
真奈美の癇性な声が襲い掛かる。
妻のヒステリックな声は、もう慣れっこのはずだが、こう暑いとカチン!と来る。苛立ちに拍車が掛かる。文夫は時計に目をやった。
「ちょっと、そこらを歩いて来るか……」
文夫は聞こえよがしに言った。
「そう。その気になったら、さっさと動く!」
真奈美に悪気がないのを、文夫は誰よりもよく知っている。夫婦になって20年以上。相手の考えは、すぐ判る。文夫はそそくさと部屋を出た。妻に逆らって碌な事はない。
ムッとする淀んだ外気に顔が歪んだ。
(こりゃあ家で寝転んでいた方がマシだったかな)真奈美の邪険な扱いを無視出来る図々しさを文夫が持ち合わせていればの話である。文夫は、いたって控え目なのだ。
文夫が住むのは、住人の大半が兼業農家という田舎だった。古くからの家ばかりで、付き合いが大変な集落である。ここで生まれ育った文夫は、高校を卒業するとすぐ町に仕事を求めた。結婚もした。子供も授かった。暫らく住んでいたが、結局田舎に戻った。
親が家を建ててくれた。万全の用意で迎えられたのだ。町でうだつの上がらぬ暮らしをしていた文夫は、これ幸いとばかりに家族を引き連れて帰郷した。
「暑いのう」
隣家の隠居だった。骨に皮が貼りついたガリガリの老人である。別に健康を損なっていないのに、いつも寝間着姿で、家の周囲をウロウロしている。雑草を見つけると、まるで憎い敵と遭遇したかのようにグイグイと引き抜く。一本も残さない。お陰で彼の家の周囲は雑草知らずだ。
隠居はギョロッと文夫を見た。生ける屍を連想させる。ゾンビそのものだ。
「ほんま。死にそうな暑さやねえ」
「あ~ん?」
隠居は耳が遠い。これまで何度も話し掛けて同じ目にあった。一度で通じた例がない。最低3度は繰り返すはめになる。
「ほんまに地獄の暑さ……」
「そうよ。全く死んだ方がマシじゃあ。こう暑いと、何も出来よらんで」
珍しく2度目で通じたらしい。大声でブツブツ言っている。いきなりしゃがんだ。足元に雑草の芽を見つけたのだ。その目敏さは凄い。血管が露骨に浮き上がった手を伸ばして雑草の芽を引き抜く。ケラケラと笑った。まだ当分はくたばりそうにない。
きつい日差しを避けて神社に足を向けた。結構大きい社殿がある。秋には氏子が繰り出す5基の祭り屋台が練り合う。年輪を刻んだヒノキの大木がそそり立って、神々しさを際立たせている。さすがの日差しもヒノキの枝葉に遮られて、差し込めない。涼しさを求めるなら、この上ない場所だ。
裏手に広がる豊かな山並みは、過去にゴルフ場開発話の舞台となった。京阪神に近い立地を、開発業者が見逃すはずはない。村は二分したが、結局良識派が勝利した。文夫にはどうでもいい話だった。あえて言うなら、田舎は田舎、自然は自然のままであってほしい。
本殿に上がる石段に尻を下ろした。二対の狛犬に見下ろされる位置だった。文夫は手拭いでごしごしと顔の汗をぬぐった。首筋も丹念にこすった。少しは気持ちが良くなる。
(今日は来るかな……?)
とりとめもなく考えた。文夫が神社に足を運んだのは、ある期待もあってのことだ。家で聞いた蝉の鳴き声が時雨になって境内に降り注ぐ。腕時計を確かめた。10時を回っている。文夫は境内の入り口を見やった。気配を感じたのだ。すぐその正体が姿を見せた。
茶褐色の犬がちょろちょろと動く。柴犬の血が入った雑種の犬。よく知っていた。文夫の匂いをかぎ取って、犬はいきなり顔を上げた。こちらに向かってしゃにむに駆け出した。文夫が差し出す手の中に飛び込んだ。しきりに尾を振る。熱い舌で所構わず舐めた。
「こらこらチビ、止めろ。止めろって」
ポケットに用意していた竹輪を呉れてやると、チビは夢中で食べた。
「おじさん。チビ、喜んでいるよ」
いつの間にか、見知った顔が覗き込んでいた。小学生の康之と母親だった。彼女と目が合うと、お互いに静かな会釈を交わした。
「チビにご馳走してくれたんだ、おじさん」
「いつも、ごめんね」
母と子は同じ仕草で文夫に頬笑んだ。
母親は文夫のよく知った相手だった。幼馴染み。そして初恋の……!6年前の夏、偶然境内で彼女に再会した。髪型と化粧ですっかり変わっていた吉沢志保子は、昔と変わらぬ声で話し掛けて来た。
「あ?甲斐くんじゃないの?」
「え?……そうだけど」
「わたし、吉沢志保子。覚えてる?」
忘れてはいなかった。文夫の記憶にちゃんと刻まれている。よくよく見ると、志保子の面影はしっかりと残っていた。幼馴染みで、高校生の頃付き合い始めた。周囲も好意的に見てくれた。しかし、人生は、そううまく運びはしない。
バイク事故がすべてを変えた。人身事故だった。同乗の志保子と、はねた相手が病院に運ばれた。問題は大きく広がった。無免許で警察沙汰。結局学校は辞めた。必然的に志保子と文夫に距離が生まれた。田舎の保守性は文夫に容赦なかった。痛めつけられた末、罪悪感に支配された文夫は、どん底まで落ちた。
志保子に連絡を取ろうとした文夫を、彼女の両親は露骨に拒絶した。元校長の父親と、教育委員会に務めていた母親を前に、非行少年の烙印を押された文夫になすすべはなかった。志保子が東京の大学へ進むと、もう文夫とは縁のない人となってしまった。
懐かしい志保子の笑顔は眩しかった。それでも文夫は、素知らぬ顔で対応した。昔と違って彼は分別を備えた大人だった。昔馴染みと旧交を暖めると割り切った。最初こそ……。
「すっかり変わっちゃったなあ」
「今は胡桃沢志保子。結婚して大阪人になっちゃった。甲斐くんは、どうなん?」
「俺?ああ、結婚してる。子供は3人だ」
「ああ、幸せなんや」
「俺?うん。まあ、そうかな……」
取り留めのない話が続いた。志保子は何のこだわりも見せなかった。ただ明るかった。昔そのままに。文夫の胸は軽く痛んだ。
夏休みになると、志保子は必ず帰郷した。再会の翌年は赤ん坊を連れて帰った。それからは年々成長する息子の康之と一緒だった。子供を見つめる志保子の目は母親のものだった。母性は彼女を一層美しくさせている。
文夫は母親になった志保子に戸惑いながらも、調子を合わせた。夏休みの出会いで得た胸のときめきを守るために、懐かしい昔馴染みであり続けた。
「もう、田舎には帰ってこられなくなりそう」
「え?」
「中東の方へ夫が赴任するの。付いていかなくちゃあ。彼ね。単身赴任でいいって。でも放っておけないでしょ」
志保子は笑顔を文夫に向けた。ドキッとしたが、取り澄ました笑顔で頷いた。彼女がどんなに夫を、家族を愛しているか、よく分かる。
「吉沢もいい嫁さんになったなあ。頑張れよ。あ?俺が言う事じゃなかったな」
「そんなことないよう。うん。頑張る。でも、甲斐くんと、もう会えなくなるね」
「そうだな」
「楽しかった、本当に。夏休み…私には、高校生の頃に戻れる束の間のシーズンだった」
志保子の声が文夫の感情に突き刺さる。
(なに考えてんだ、俺。ヒトの嫁はんやのに……昔は帰らへん……そやけど……?)
「おじさん。明日、お家に帰るね」
康之が母の腰に手をまわして、文夫を見上げていた。文夫は心の動揺を慌てて隠した。
「おう、そうか。帰ったら、お父さん、喜ぶぞ」
「うん。喜ぶよ。大好きだもん、お父さん」
康之の笑顔が、文夫の立場を如実に語っていた。志保子がペコリと頭を下げた。
境内を出てぶらぶらと歩いていると、駆けてきた子供らとぶつかった。文夫の末っ子の太知がいた。母親にそっくりの顔をしている。
「どうした?」
「境内で野球すんだよ。俺、今日はピッチャーさせて貰えるって」
「そうか。そいつはよかったなあ。頑張って投げて来い。負けんじゃねえぞ」
「当たり前じゃん。俺、父さんの息子だぞ!」
思わず太知の顔を見直した。そして、頷いた。(そうだ。こいつは俺の息子だ。うん!)
「暑いのう、堪らんわい」
隠居だった。ギョロッとした目が文夫に向けられている。エンゲ(縁側)の板間にだらしなく座り込んでいる。
「暑いいうてからに、悪さすんじゃねえぞ」
ドキッとしたが、さりげなく応じた。
「俺は、真面目だけが取り柄じゃ。おやっさんも、ずーっと昔に言うてくれたやんか」
正気じゃないかも知れない隠居に、えらく饒舌な自分に気付いた。きっと暑さのせいだ。




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます