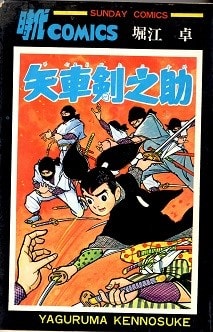「将来飲食店で独立するんやね。ならここで思い切り勉強したらいいじゃないか」
調理師学校に紹介されたH商工会議所内のレストラン。面接相手は何のこだわりも見せない。自分の店を持つまでとハシゴ的な身勝手過ぎる求職者を「いいよ、いいよ」という感じで迎えてくれる。終始ニコニコと緊張感や余分な考えを包み込む。それがY専務だった。二十一歳の若者には父親同然に見えた。
レストラン勤めは順調だった。調理師学校で学んだ調理技術は、職場の上司M調理主任のおおらかな指導のもと生かされた。優しい同僚たちにも恵まれて楽しく仕事をした。
「専務さん、仲人をお願いできますか?」
就職して2年目。つきあっていた彼女と結婚を決め、Y専務のもとを二人で訪れた。
「ほうか。結婚するの。喜んで引き受けましょ」
彼女と二人、感謝の頭を下げた。
Y専務はすぐに動いた。結納で彼女の親元に出向き、結婚式場も早速押さえた。レストランと提携する結婚式場だった。
「これはというメニューを考えてやるよ。きみには一生に一度の晴れ舞台だからな」
W主任も喜んだ。同僚らの好意的な冷やかしも心地よく嬉しかった。
「ありがとうございます!」
何度も頭を下げながら、にやけた。
それが3週間後、事態は一変した。
「結婚するの自信ない。…結婚できない…!」
「え?」
寝耳に水だった。前日までは二人の未来をあんなに幸せいっぱい語っていたのに。
彼女の心を取り戻すべく懸命に慰留したが、無駄だった。彼女の思いは決意に変わった。
「結婚はやめる!」
初めてだった恋愛経験、その彼女との結婚しか考えられなくなっていた私には大ショックだった。しかし、もう彼女に取り付く島はなかった。
何も考えられなくなり、職場を無届けで休み、アパートの自室にこもった。死にたいと思ったが、それを実行する勇気はない。知り合いの誰とも会いたくなかった。ただ布団を頭からかぶってモグラ状態で過ごした。
(…どうしたらいいんだろう?親には…専務さんは…主任さんは…)
どの人にも申し訳ないが先に立つ。やっと落ち着いても、破談の後始末なんて、考えられるはずがない。職場の上司や同僚の顔を思い浮かべ、焦燥感に押しつぶされそうになるだけ。結局3日間、アパートは出られなかった。
誰かがドアを叩いている。フラーッと玄関に移動した。でもドアのノブに手は出なかった。何度も何度もドアを叩いたあげく相手はようやく諦めた。「ホッ」と緊張が解けたとき、郵便受けに何かが差し込まれた。一枚のメモ書きだった。
ドアの向こうに気配が消えたのを確かめると、やっとメモを手にした。
『みんな心配している。きょうの夕方、仕事終わりに専務と一緒に来るから、7時頃、家にいてくれよ M』
3日間何も連絡せずに休むスタッフを心配した主任が、ワザワザ来てくれた。(忙しいのに…)また申し訳なくて堪らなかった。
時間を指定されてしまっては、もう居留守を使う訳にはいかない。Y専務とM主任、あの優しい上司と顔を合わせないわけにはいかない。
「オレ、外で待ってるからな」
M主任の気配りで、私はY専務と二人きりにされた。罪悪感いっぱい、気まずい思いにいる私を慮った専務は先に口を開いた。
「お父さんに☎を貰った。向こうさんの家から連絡があったそうだ。えらく心配されていたよ」
すべてを専務は知っている。それなのに、全く変わらない笑顔が目の前にあった。
「…ぼ、ぼく…」
「無理しなくていいから。ややこしい手続きは私がやっておくから。きみはこの週末まで休みをとるといい。落ち着いたら仕事に出なさい。みんな待ってるよ。きみがいないと寂しいんだってさ」
ボロボロと涙が出た。
「ただ、どんなことがあっても、自分だけで持ち込むんじゃないよ。ご両親だって、僕も主任も、ちゃんと相談に乗れるんだから。せっかく出会えた相手だろ。大事にしなきゃ」
何も言えない。止めどもなく流れ落ちる涙を頻りに拭った。
週明けに職場へ。何とも言えない気恥ずかしさは、同僚たちがすぐ忘れさせてくれた。
「これからの君は、今回のことを生かして、強く成長しなきゃいけないよ。人任せの人生は何度も繰り返さない。いいね、約束だ」
改めて詫びる私に向けたY専務の言葉は、私の胸に深く刻まれた。