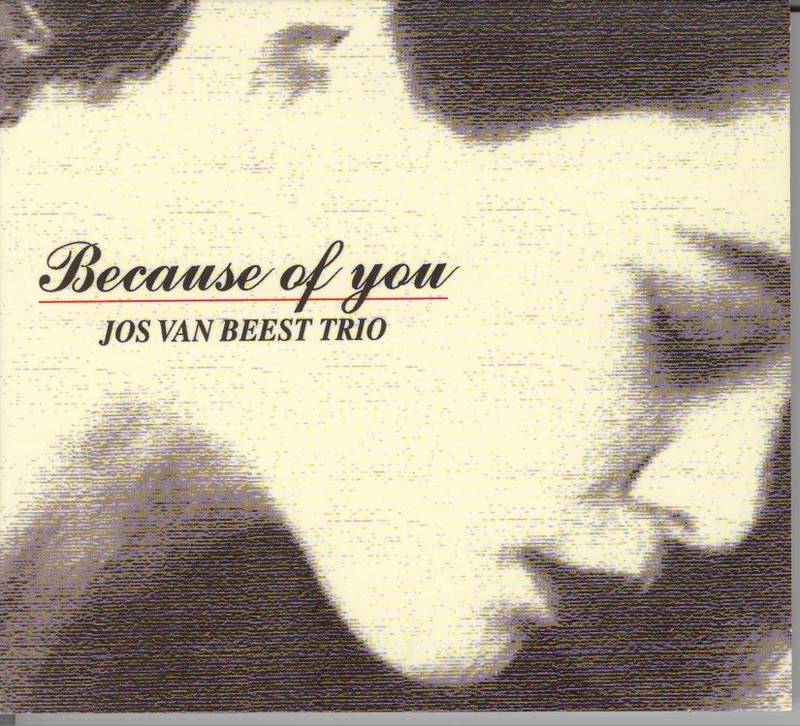●今日の一枚 24●
Ike Quebec
Bossa Nova Soul Samba
 夏……。ボサノヴァの季節。今日の二枚目、 夜聴くボサノヴァだ。一杯やりながら聴くボサノヴァだ。アイク・ケベックのテナーは、どこまでも優しい。中音域を中心とした柔らかい音だ。疲れた身体を優しくいたわるように、ソフトでブルージーなサウンドが私を包んでくれる。
夏……。ボサノヴァの季節。今日の二枚目、 夜聴くボサノヴァだ。一杯やりながら聴くボサノヴァだ。アイク・ケベックのテナーは、どこまでも優しい。中音域を中心とした柔らかい音だ。疲れた身体を優しくいたわるように、ソフトでブルージーなサウンドが私を包んでくれる。
アイク・ケベックは、1940年代に活躍したテナーマンだ。途中、薬におぼれたり、ブルーノートのスカウトをやったりして、ブランクがあったようだ。バド・パウエルもセロニアス・モンクも彼が発掘したアーティストらしい。1950年代末に復活して、ブルーノートに録音を残しているが、1963年肺ガンのためなくなった。このアルバムは1962年の録音、彼の最後の作品だ。
アイク・ケベックは、すごく有名な人ではないが、このアルバムはなかなかの出来である。テナーの音色がすばらしい。柔らか、優しい、包み込むような、などの形容がつく音だ。しかし、このアルバムを"夜聴くボサノヴァ"にしているのは、ケニー・バレルのギターだ。一聴して、いかにもケニー・バレルとしかいいようのないギターが、夜の雰囲気をかもし出している。ケニー・バレルは、夜のギタリストだ(「ミッドナイト・ブルー」という作品があるほどだ)。すごく好きなギタリストではないが、何故かときどき聴く。そして、それは何故か夜だ。昼に聴くことはほとんどない。傍らには必ず酒がある。そんなギタリストだ。優しいテナーにブルージーなギターが絡みつく、これがこのアルバムの聴きどころだ。
今夜はめずらしく時間のゆとりがある。夜はまだ長い。もう少し音楽を楽しむ時間がありそうだ。そして、私の前には何故か今日も酒がある。地酒「澤の泉」(特別純米)だ。