◎今日の一枚 453◎
Wynton Kelly
Wynton Kelly

高校で日本史を教えていて、疑問なことの一つが織田信長のことである。私は戦国時代の専攻ではないのだが、いろいろな関りから、1980年代前半ぐらいまでの戦国時代に関する論文をある程度は読んだ経験がある。そこで感じるのは、織田信長は、通常、新しい時代を切り開いた先進的な革新者として位置づけられるが、その領国経営や諸政策において、決して革新的とはいえないということだ(むしろ、後進的な場合すらあるのだ)。例えば、信長に倒された今川氏の方が土地政策や家臣団統制、流通経済政策において、ずっと先進的であった。このことは、高校日本史でこの時代を考える授業をするとき、必ず引っかかっていた問題である。通説と、それを超えらない自分の非力に、身を割かれる思いをすることもあった。
もう一つ、信長は「天下布武」を掲げて天下統一を目指したというが、「天下」という語が何を意味するのかということについて、ずっと引っかかっていた。学生時代、米原正義先生が授業で(茶の湯に関する講義だった)、史料上の「天下一」という語の検討から、「天下」という語が必ずしも現在的な日本全体を指すわけではないと語ったことが、ずっと気になっいたからである。
今年読んだ、金子拓『織田信長<天下人>の実像』(講談社現代新書2014)は、そんな疑問に不完全なながらも答えてくれるものだった。金子氏は、織田信長の政策の後進性を認めた上で、神田千里氏らの研究を援用しつつ、信長の「天下布武」の「天下」は、日本全体ではなく、京都周辺の狭い領域を意味するものではないかと語り、信長に領土的野心はなく、天下統一=日本の統一など考えてはいなかったのではないかという結論を導き出した。信長は、室町幕府15代将軍の足利義昭を支えることで、京都周辺の「天下静謐」を目指したというのである。信長の領土拡大についても、戦国・織豊期の先行研究を援用しつつ、「天下静謐」を乱そうとした相手を軍事的に制圧した結果であると位置づけ、制圧した地域についても、中央集権的な方法で統治したわけではなく、旧来的な、その地域の支配者に一任するやり方だったと結論付けた。
また、足利義昭の追放についても、義昭の立場をわきまえない独善的な強欲さが許しがたかったからであるとし、義昭追放以降も朝廷の守護者として「天下静謐」のために行動していたとする。
本能寺の変については、四国征伐の頃から「天下静謐」を逸脱し、野心を持ちはじめた信長に対して、明智光秀がそうした信長の動きを頓挫させようとしたのではないかと推論している。
ややスタティックな論理の感もあるが、史料的裏付けのある部分が多く、先の私の疑問に関しても首肯すべき見解が多いように思う。織田信長に関しては、一般的にも、研究者の間でも、スーパー変革者のイメージが強く、それを書き換えるのは一朝一夕ではあるまい。けれども、個別研究の積み重ねで、信長像は大きく書き換えられるという予感はある。私はそのような方向性を妥当だと考えている。
今日の一枚は、ウィントン・ケリーの『枯葉』である。『枯葉』というのは日本語タイトルだ。ジャレットには「wynton kelly」としか書かれていない。
ウィントン・ケリーのピアノは、音が軽いところがいい。深遠さとか、情念とかの概念とは無縁である。もちろん、超絶テクニックなどとも無縁である。そういう意味では表層的なピアノである。一抹の寂しさみたいなものを感じたりするが、それも表層的なテイストに過ぎないだろう。けれども、我々には、ケリーのような、軽い音の、軽いノリが必要なことがある。どうしようもなく、そんなサウンドが必要なことがあるのだ。表層的な軽い響きが、深遠な音を凌駕し、本当の深遠に届くこともあるのだ。絶頂期のウィントン・ケリーのピアノを聴くと、いつもそんなことを夢想する。










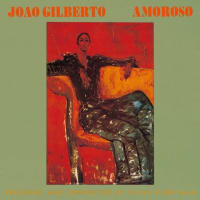
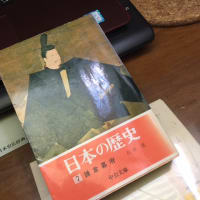
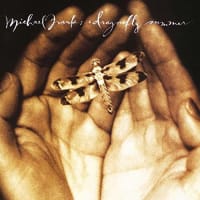
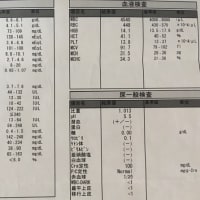


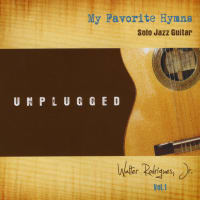








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます