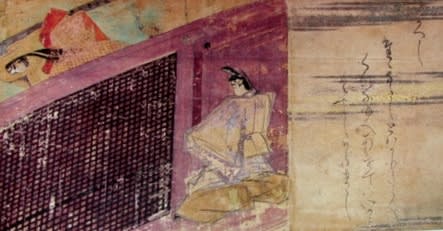行田市若小玉は、古くは若小玉小次郎なるものが住む地と伝わり、風土記稿によれば「嘉禎(かてい)四年(1238)二月二十三日、将軍供奉名のなかに、若小玉小次郎と記す(略)建長二年(1250)閑院殿造営の内、若小玉次郎とあり」鎌倉初期に当地の豪族であった若小玉氏から地名となったのであろう。


御祭神は中筒男命(なかつつおのみこと)イザナギノミコトの禊の際に生まれた水の神。住吉大社の御祭神である。中でも神功皇后の三韓征伐の折り、住吉大社の御神徳で帰路に着け、応神天皇をお産みになられたことから、航海の神、海の神、水の神として近畿を中心に篤い信仰を受けている。なぜ中筒男命がこの若小玉に勧請されたのか、創建時期についても不明であるそうだが、明治期までは別当として真言宗安養山遍性寺が勤めている。往時の本地仏である十一面観音像を本堂に祀るという。明治期の合祀政策で各耕地の十社以上が集められたが、八幡山古墳の頂きにあった八幡神社は古墳に石室が発見されたことで旧地に戻されたという。

また本殿脇に祀られる榛名神社は群馬の本社と同等に霊験あらたかとと伝わり、戦前戦後においても、群馬の総本社への代参は行われなかったという。

昭和初期に建てられた本殿拝殿の彫刻は見事で、神社建築の粋を今に伝える。

現在に至っても大祭時にはササラが奉納され、行田市無形文化財に指定されている。また境内地に建つ神楽殿は平成になってからも修繕が入り、ササラ伝承を大事に守っている様子が伝わる。

もとは大祭(9月二十日)に奉納され、雨乞いササラであったそうだ。五穀豊穣と疫病退治を願い長い伝統を今に伝える若小玉のササラ。
曲目は「橋掛」「花掛」「鐘巻」等があり、特に「鐘巻」見ずして若小玉のササラを語ることなかれと伝わるほど圧巻の舞を仕上げている。
行田市文化財化:の解説によれば、ササラの起源は文化十一年(1814)「鐘巻」はスサノオノミコトがヤマタノ大蛇を退治する場面で、演目後、子供が元気に育つようにと、釣り鐘の上に子供を座らせる光景があるそうです。

境内入り口には巨大な日露戦争出征記念碑が建ちます。非情に国威掲揚が盛んであった時期でしょう。


境内地のあちこちに伊勢奉納神楽の記念碑が残ります。

神社運営上非情に興味深い記事が載って折り、天保、安政期には大祭は七月に行われていましたが、大正期に例祭日が7月二十日から九月二十日へと変更になった子とが伝わります。これは祭りの費用を用立てるにあたり、七月では作物のとれ具合を図るのに大祭そのものを7月から9月へと変更したとの記述が残っています。祭りあっての神社、神社あっての氏子ではありますが、当時では大祭の準備は大変おががりなものであったことでしょう。作柄が明確でなければ、御例祭の用立てもままならない時代の子とです。
それでも今日現在ササラは継承し、他の祭事も奉納されるといいます。

祭りあっての氏神さまであることがよく伝わります。
いつかササラを見に行き壮大な祭りの様子をこのめでみたいと願っています。