
我が家の近くでは毎年2月の終わり頃、初音が聞かれるのに
三月に入ってもまだ鶯の声を耳にしません
そういえば防犯のためと近くの雑木林の木が切られ
スカスカの林になり『千林』とは言えなくなってます
でも先日、月ヶ瀬梅林を訪れれば
メインの帆浦梅林はまだ三分咲きだったが
五月川から代官坂を上れば早咲きの梅は見頃


今年初めて鶯の声を聴けました
まさに千林に入ると処々鶯で来てよかったと・・・・・
 ???
???単純に喜んでいましたが、『春入千林処々鶯』の
本当の意味は???
「北礀居簡(ほっかん きょかん)」語録では
秋澄萬水家家月
春入千林處處花
「春入千林処々鶯」は『花』を『鶯』に
改変された句でどちらも
"仏の光明を受けてすべてが生き生きと輝いている様 ”
を意味しており
表千家には千宗旦の揮毫になる『春入千林処々鶯』の句の軸が
伝存し、初釜の床に掛けるのが恒例とされているそうです
茶掛け禅語辞典より
釣り釜のお稽古の主菓子は『引千切』を
月ヶ瀬で摘んだ蓬

その若菜で作った「こなし」に
ゆり根餡と白餡の金団
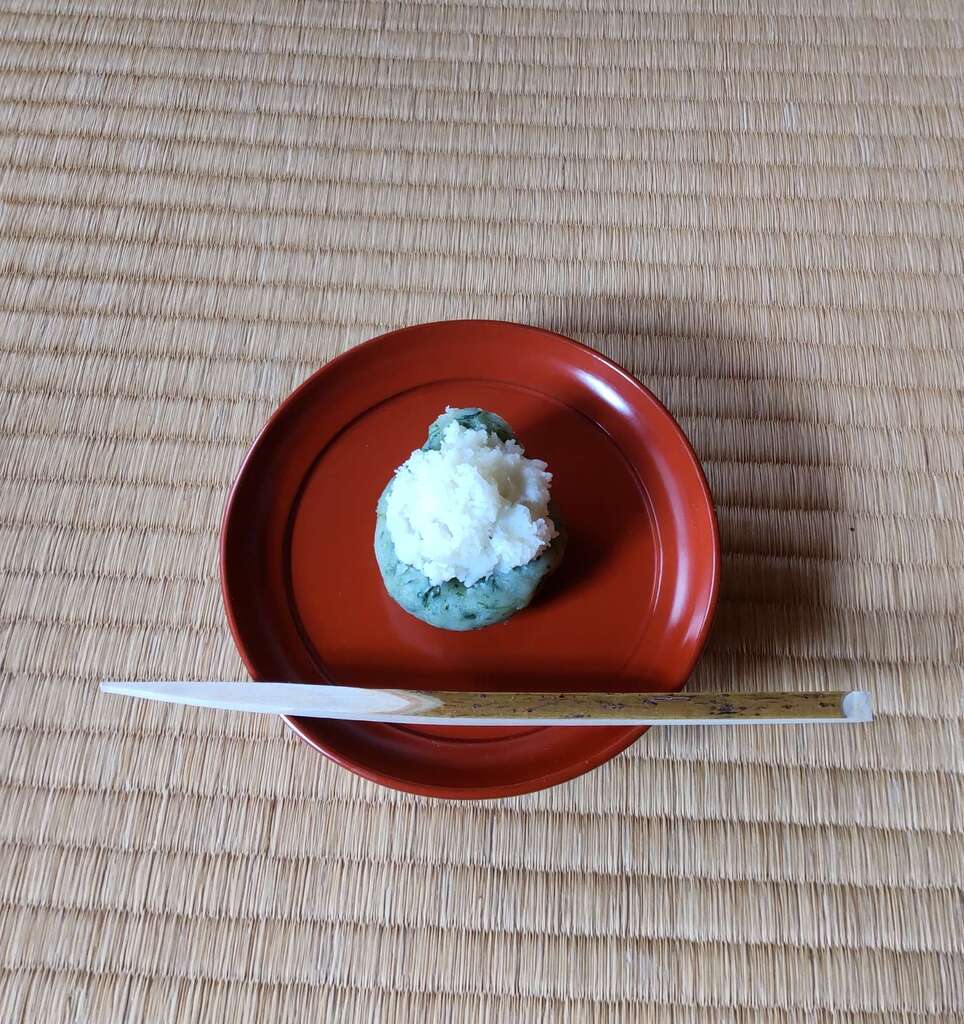

蓬の香りがいいですねと言っていただき
茶杓の銘は・・・玄々斎作『若菜』と
お稽古での一コマです










