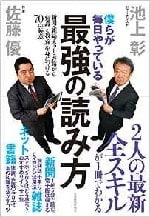〈1〉木村忠正「『ネット世論』で保守に叩かれる理由」(中央公論2018年1月号)
〈2〉記事「旧東ドイツ出身の記者が、故郷の変貌を暴く取材旅行に出る!」(クーリエ・ジャポン〈ネット〉12月11日)
〈3〉嶋田崇治「独で深刻化する富の偏在」(週刊エコノミスト12月5日号)
〈4〉ジェームズ・パーマー「劉暁波の苦難は自業自得? 反体制派が冷笑を浴びる国」(ニューズウィーク日本版〈ネット〉7月16日)
〈5〉空井護「民主体制であること、民主体制であり続けること」(世界2018年1月号)
〈6〉尾木直樹・岩波明・石川結貴 座談会「子どもに『死にたい』と言われたら」(文芸春秋同年1月号)
〈7〉内閣府「『人権擁護に関する世論調査』の概要」(ネット、12月)
〈8〉記事「まとめサイトの差別認定 大阪地裁 運営者に賠償命令」(本紙11月17日付)
*
みんな、何に苛立っているのだろう。何をそんなに恐れているのだろう。
木村忠正によると、在日コリアンなどを「ゴキブリ死ね」などと侮蔑するネット投稿の「主旋律」は、「弱者利権」批判だという〈1〉。ここでの「弱者」には、「生活保護」「沖縄」「LGBT」「障害者」「ベビーカー」なども含まれる。投稿者たちは、これらの人々が「立場の弱さを利用して権利を主張」しているとみなす。「在日特権」という言葉はそうした認識を象徴するものだ。
また木村は、ネット上の韓国・中国への侮蔑も「弱者利権」批判の延長だという。木村によればネット上の中韓批判は「歴史修正主義やナショナリズムの問題というよりも、慰安婦問題、戦争責任、戦後補償、植民地支配について、韓中にいくら謝罪しても結局(第二次大戦時における弱者の立場を盾に取り賠償金をとろうとして)問題を蒸し返されるという意識が根底には強く横たわっている」。その延長で、「弱者」の擁護者とみなされた新聞も「マスゴミ」などと侮蔑される。つまり「嫌韓・嫌中」や「マスコミ批判」も、「弱者に対する強い苛立ち」から派生しているというのだ。
なぜ彼らは苛立つのか。木村は投稿者たちを「『マジョリティ』として満たされていないと感じている人々」と形容する。「弱者」や「少数派」より、自分たちこそ優遇されるべきだ。彼らはそうした認識に立ち、「その人たちなりの公正さ」を主張しているのだという。
*
だがこうした「弱者」「少数派」への苛立ちは、日本だけの現象ではない。
ドイツのザクセン州は、旧東独の炭鉱地帯だった。東西統合後は経済的に停滞し、移民排斥運動への支持が多い。この州の統合省長官は、排斥運動の参加者たちからこう言われたという〈2〉。
「長官さんよ、いつも難民と一緒なんだろ。どうしてまず俺らを統合しようとしないんだ?」
彼らは、最初は難民への怒りを語る。しかし「その後すぐに、自分の話を始める」。それは、体制の変動に翻弄(ほんろう)され、敗北感や疲労感に苛(さいな)まれてきた経験だ。自分たちこそ優遇されるべきなのに、少数派や「弱者」の方に目をむける新聞や政治家は許せない。そうした心理が、難民への憎悪となるのだ。
嶋田崇治は、排斥運動の台頭とドイツの格差拡大との関係を指摘する〈3〉。だが嶋田も認めているように、ドイツでは資産格差が広がってはいるが、所得格差は相対的に小さい。木村を始めとした日本のネット研究者は、過激な投稿をする人に、所得や学歴で顕著な特徴は見いだせないという。彼らは、必ずしも経済的な「弱者」ではないのだ。
中国では、豊かになったはずの中産層に、「少数派」への不寛容が、ドイツとは違う形で現れている。ジェームズ・パーマーは、ノーベル平和賞を受賞しながら獄中にあった劉暁波の死に対する中国での反応をこう記している〈4〉。
「中国の中流階級は、比較的リベラルな人々さえ、反体制派を軽蔑している。最初の反応は、何かしら非難する理由を見つけることだ。悪いのは被害者であって、彼らを逮捕し、拷問し、牢屋に入れる人々は悪くない。……
そんな考え方に最初は衝撃を受けたが、次第に分かってきた。これは生き延びるための自己防衛であり、独裁主義に順応する1つの方法なのだ」
パーマーはいう。「不公正な世界を前にしたとき、人間は精神的な防衛機能として、世の中は公正だと思い込もうとする」。そして「他人の苦しみを正当化する理由を探し、自分は大丈夫だと根拠もなく安心したくなる」。つまり、現状を変えられない自分の無力を直視するよりも、今の秩序を公正なものとして受け入れ、秩序に抗議する側を非難するのだ。
もちろん中国、ドイツ、日本はそれぞれ事情が違う。だが急激に変動する現状に苛立ちながら、それを制御できない無力感を抱く人に、不寛容が蔓延する状況は共通する。ここでの決定要因は政治的・経済的な無力感と疎外感の程度で、必ずしも所得の多寡ではないようだ。
そして世界各地では、無力感の反映としての投票率低下、少数派への不寛容、新たな権威主義が広がる。空井護はこれを「民主体制の崩壊」と評した〈5〉。
*
どうしたらよいか。富の偏在を抑える経済政策も重要だが、それとは別種の工夫で改善できる部分もある。
尾木直樹は、アメリカの14歳の女性が開発したシステムを例に挙げる〈6〉。SNSに人を傷つける言葉を投稿しようとすると、「本当に投稿しますか?」と表示されるというものだ。実験したところ、93%が投稿をやめたという。【引用者注】
過激な少数者差別は目立ちはするが、実は極端な人々の所業である。木村などの研究では、ネットで過激な言辞をくりかえし発信している投稿者は約1%だ。内閣府の調査では、ヘイトスピーチには否定的な回答が大多数で、「ヘイトスピーチをされる側に問題がある」との回答は10・6%にすぎない〈7〉。訴訟などの法的対応を含め、拡大を止める余地はある。大阪地裁は11月に、ネット上の中傷に損害賠償を命じた〈8〉。
無力感と苛立ちを他者にぶつけても何も生まれない。逆にそれを制御する力を自覚することは、誰にとっても生きやすい社会を築く第一歩となる。新年は、そうした努力の始まりにしていきたい。
【引用者注】この実験はアイヒマン実験の対極に位置するように思われる。
「
【心理】組織の論理とアイヒマン実験 ~ブラック企業の心理学~
」
「
【読書余滴】リーダーの条件 ~ミルグラム実験と組織~」
「
【読書余滴】世間は狭い、の心理学 ~ミルグラムの「スモールワールド法」~」
「
【読書余滴】ミルグラムの単純かつ独創的な実験~都市心理学~」
「
【読書余滴】組織人はどこまで人道を踏み外すか ~「アイヒマン実験」~」
「
【読書余滴】組織の中で人はどう変わるか ~集団の心理学~」
□「(論壇時評)弱者への攻撃 なぜ苛立つのか 歴史社会学者・小熊英二」(朝日新聞デジタル 2017年12月21日)を引用
「
(論壇時評)弱者への攻撃 なぜ苛立つのか 歴史社会学者・小熊英二」
↓クリック、プリーズ。↓