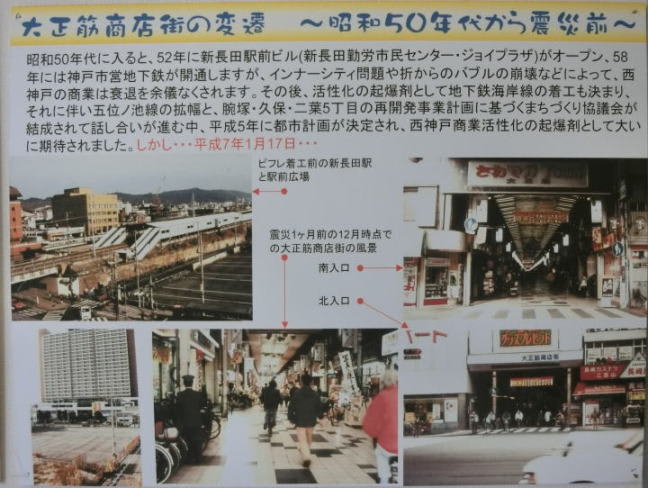(1)ラブロフ・ロシア外相は、典型的な官僚だ。どんな大統領にも忠実に仕えることができる。
熟練した職業外交官だから、物事を敢えて荒立てるようなことはしない。
(2)メドベージェフ大統領(当時)が、2010年11月1日、ソ連時代を通じてロシアの元首として初めて国後島(北方領土)に上陸した。その後、日露関係は戦後最悪レベルになった。
ラブロフ外相は、明らかに「メドベージェフはやり過ぎた。これ以上日本との関係を悪化させるとまずい」と考えた。そこで彼は、2011年2月11日、モスクワを訪問した前原誠司・外相(当時)との会談で、柔軟な姿勢を示した。前原外相が、日本の法的立場を毀損せずに北方領土における日露共同開発の可能性を検討することを提案したのに対して、ラブロフ外相は肯定的な回答をしたのだ。
今からでも遅くはない。安倍晋三政権が、前原提案を推進し、北方領土での共同経済活動を行えば、
(a)色丹島、国後島、択捉島に現在居住するロシア系住民の対日感情が大きく好転する。
(b)日本人が北方領土に常住し、経済活動を行うことになるので、北方領土の日本化が進む。
(3)残念ながら、最近のラブロフ外相は、対日強硬論に流されている。
モルグロフ外務次官(日露平和条約(北方領土)交渉におけるロシア側責任者)が、中国専門家で、習近平政権による対日包囲網形成に協力的だからだ。
2013年12月26日、安部首相が靖国神社に参拝した5時間後に、ロシア外務省は「遺憾の意」を表明した。ロシアが日本首相の靖国参拝を批判するのは、ソ連崩壊後、初めてのことだ。今回の「遺憾の意」表明は、中国や米国の反応を踏まえた上でその尻馬に乗った、というものではない。ロシアが、第二次世界大戦をめぐる認識で、日本を叩く口実を探しており、ちょうどよいタイミングで首相の靖国参拝があったので、それを最大限に活用した、という流れだ。
ラブロフ外相も、モルグロフ次官の対日強硬外交を止めていない。
(4)1月31日、外務省飯倉公館(東京都港区麻布台)で、平和条約に係る日露次官級協議が行われた。交渉内容は外部に漏れ出ていない。北方領土の帰属問題に係る歴史的、法的な経緯が協議の俎上に載ったが、平行線だったらしい。
全般的に極めて率直で真剣な議論を行った。長年にわたって行われてきた交渉であり、1回の交渉で隔たりがなくなった、ということはできない。【杉山晋輔・外務審議官(政務担当)、1月31日NHKニュース】
双方が論点を整理し、首脳間の政治決断に向けた準備が進んでいる(推定)。
(5)2月1日、安全保障会議が開催されているミュンヘン(ドイツ)で、岸田文雄・外相とラブロフ外相が会談した。安倍首相が、7日に開幕するソチ冬季五輪の開会式に出席し、翌8日、プーチン大統領と会談することについて合意した。
外相会議では、かかる事務的事柄を話し合うだけでなく、北方領土問題の実質的内容を話せるレベルの信頼関係を両外相間で構築しなければならない。
前原・ラブロフ関係から、虚心坦懐に学ぶべきだ。
□佐藤優「五輪と北方領土 ロシアの強硬論を変えるには ~佐藤優の人間観察 第56回~」(「週刊現代」2014年2月22日号)
↓クリック、プリーズ。↓



熟練した職業外交官だから、物事を敢えて荒立てるようなことはしない。
(2)メドベージェフ大統領(当時)が、2010年11月1日、ソ連時代を通じてロシアの元首として初めて国後島(北方領土)に上陸した。その後、日露関係は戦後最悪レベルになった。
ラブロフ外相は、明らかに「メドベージェフはやり過ぎた。これ以上日本との関係を悪化させるとまずい」と考えた。そこで彼は、2011年2月11日、モスクワを訪問した前原誠司・外相(当時)との会談で、柔軟な姿勢を示した。前原外相が、日本の法的立場を毀損せずに北方領土における日露共同開発の可能性を検討することを提案したのに対して、ラブロフ外相は肯定的な回答をしたのだ。
今からでも遅くはない。安倍晋三政権が、前原提案を推進し、北方領土での共同経済活動を行えば、
(a)色丹島、国後島、択捉島に現在居住するロシア系住民の対日感情が大きく好転する。
(b)日本人が北方領土に常住し、経済活動を行うことになるので、北方領土の日本化が進む。
(3)残念ながら、最近のラブロフ外相は、対日強硬論に流されている。
モルグロフ外務次官(日露平和条約(北方領土)交渉におけるロシア側責任者)が、中国専門家で、習近平政権による対日包囲網形成に協力的だからだ。
2013年12月26日、安部首相が靖国神社に参拝した5時間後に、ロシア外務省は「遺憾の意」を表明した。ロシアが日本首相の靖国参拝を批判するのは、ソ連崩壊後、初めてのことだ。今回の「遺憾の意」表明は、中国や米国の反応を踏まえた上でその尻馬に乗った、というものではない。ロシアが、第二次世界大戦をめぐる認識で、日本を叩く口実を探しており、ちょうどよいタイミングで首相の靖国参拝があったので、それを最大限に活用した、という流れだ。
ラブロフ外相も、モルグロフ次官の対日強硬外交を止めていない。
(4)1月31日、外務省飯倉公館(東京都港区麻布台)で、平和条約に係る日露次官級協議が行われた。交渉内容は外部に漏れ出ていない。北方領土の帰属問題に係る歴史的、法的な経緯が協議の俎上に載ったが、平行線だったらしい。
全般的に極めて率直で真剣な議論を行った。長年にわたって行われてきた交渉であり、1回の交渉で隔たりがなくなった、ということはできない。【杉山晋輔・外務審議官(政務担当)、1月31日NHKニュース】
双方が論点を整理し、首脳間の政治決断に向けた準備が進んでいる(推定)。
(5)2月1日、安全保障会議が開催されているミュンヘン(ドイツ)で、岸田文雄・外相とラブロフ外相が会談した。安倍首相が、7日に開幕するソチ冬季五輪の開会式に出席し、翌8日、プーチン大統領と会談することについて合意した。
外相会議では、かかる事務的事柄を話し合うだけでなく、北方領土問題の実質的内容を話せるレベルの信頼関係を両外相間で構築しなければならない。
前原・ラブロフ関係から、虚心坦懐に学ぶべきだ。
□佐藤優「五輪と北方領土 ロシアの強硬論を変えるには ~佐藤優の人間観察 第56回~」(「週刊現代」2014年2月22日号)
↓クリック、プリーズ。↓