芥川賞受賞作である。そのことは作家にとって幸せなことだとは思うが、この小説にとって芥川賞受賞作であることが幸せかどうか。余計なお世話と言われればそれまでなのだが、付加価値としてくっついてきてしまうものが、時に迷惑な作品もあるのかもしれない。芥川賞であるという先入観は、賞自体に対する勝手なイメージかもしれないし、それを崩し続けている最近の受賞作群があるとも言える。また、日本語を母語としない外国人作家の受賞や芥川賞初の中国人作家という言葉も果たして、いいのか悪いのか。そもそも、そんなことから考えてしまうのが、何だか、ちょっと、という感じがするわけだが。と、ぐにょぐにょ書いているが、じゃあ、どうだったのと言われれば、食い足りなかったけれど面白かった。不器用な青春を正面から描くことで生みだされた主人公に好感が持てたのだ。不器用な真っ直ぐさが、愚かさにみえない青春小説はいい。そして、楊逸が持っている、天安門や中国との距離感が、作品にも表れていて、表現が告発のような突っ込み方をしていかないし、事件の真実とかいう問いかけになっていないのだ。その分、薄味な感じがしないわけではないが、作家が描きたかったものが、どこにあるのかという問題と絡んでいるのだと思う。天安門事件を歴史の大きな屈折点にして、そこに至る青春と、その渦中の青春、そして、それ以降の青春期からの移行が描かれている。そこには、個人と国家の問題や個人と歴史の問題があるわけだが、それを何か、未来への、進展への足がかりと考えているような前向きな状態が描かれているのだ。天安門での挫折はある。しかし、それ以後の中国の改革開放政策の中での経済的な発展が、矛盾を孕みながら、主人公たちの生活を経済的に豊かなものに下支えしていく現在が書かれているし、その中で、むしろ天安門の青春やそこに至る民主化への歩みが置き忘れられていくような現在が滲みだしているのだ。しかし、そこにも顔を上げて歩いている人々がいる。その印象が小説に溢れている。常に、現在と現実の中にあることの強さのようなものが、溢れているのだ。ボクらは、個人として、国家や政治と無縁な世界にはいない。そのもたらす現在との距離感をどう感じ取るか。そのスタンスを感じさせる小説だった。天安門事件から、そろそろ20年。楊逸にとって書かなければならない小説だったのだろう。書かれるべきことは書かれたのだろうか。書かれたものからさらに、大きな書かれるべきものへの予感を感じた。
最新の画像[もっと見る]
-
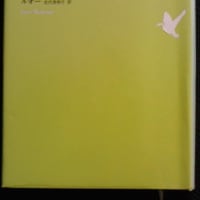 ポール・ニザン『アデン、アラビア』小野正嗣訳(河出書房新社 世界文学全集Ⅰー10)
8年前
ポール・ニザン『アデン、アラビア』小野正嗣訳(河出書房新社 世界文学全集Ⅰー10)
8年前
-
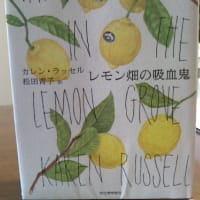 カレン・ラッセル『レモン畑の吸血鬼』松田青子訳(河出書房新社 2016年1月30日)
8年前
カレン・ラッセル『レモン畑の吸血鬼』松田青子訳(河出書房新社 2016年1月30日)
8年前
-
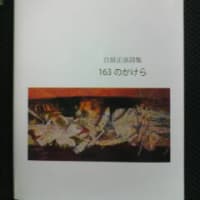 日原正彦『163のかけら』(ふたば工房)
9年前
日原正彦『163のかけら』(ふたば工房)
9年前
-
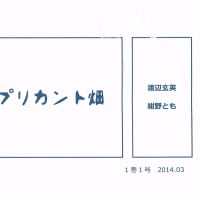 渡辺玄英・紺野とも 詩誌「レプリカント畑」(2014年3月31日発行)
11年前
渡辺玄英・紺野とも 詩誌「レプリカント畑」(2014年3月31日発行)
11年前
-
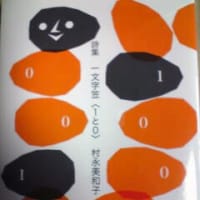 村永美和子『一文字笠〈1と0〉』(あざみ書房2014年1月31日発行)
11年前
村永美和子『一文字笠〈1と0〉』(あざみ書房2014年1月31日発行)
11年前
-
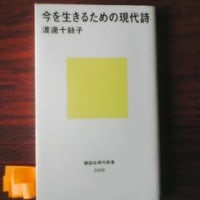 渡邊十絲子『今を生きるための現代詩』(講談社現代新書)
12年前
渡邊十絲子『今を生きるための現代詩』(講談社現代新書)
12年前
-
 冬、ソウル(3)成均館と宣靖陵
12年前
冬、ソウル(3)成均館と宣靖陵
12年前
-
 冬、ソウル(3)成均館と宣靖陵
12年前
冬、ソウル(3)成均館と宣靖陵
12年前
-
 冬、ソウル(3)成均館と宣靖陵
12年前
冬、ソウル(3)成均館と宣靖陵
12年前
-
 冬、ソウル(3)成均館と宣靖陵
12年前
冬、ソウル(3)成均館と宣靖陵
12年前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます