梅雨のうっとしい日が続いています。
雨の中出かけていくのも躊躇われ、所在のない時間をつぶすには、東海林さだおとか、益田ミリの本でも読むと何となくほっこりした時間を過ごすことが出来ます。
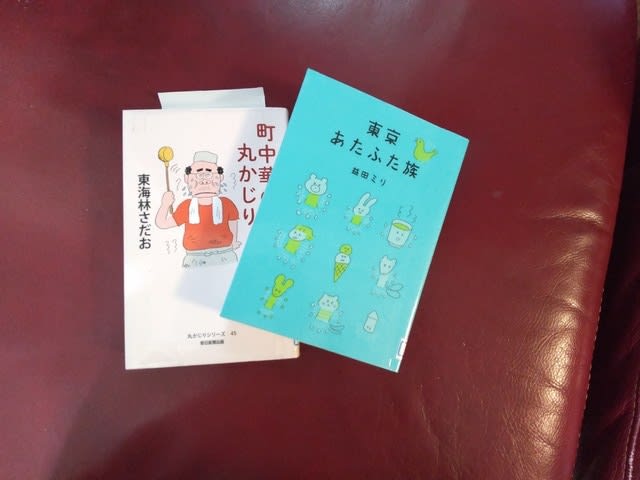
益田ミリの「東京あたふた族」は、3部構成。最初は上京したころの日々のエッセイです。ОL生活で貯めた200万円ほどを持って、イラストレーターになろうと誰も知り合いのいない東京で一人暮らし。今までの人生で1か月以上名古屋市を出たことがないというドメスティックにしか生きていない私にとっては無謀ともいえる行為。
当時無職の若い女性の一人暮らしは住むアパート探しも大変で断られてばかりだったのですが、いい不動産屋のおかみさんに出会って何とか見つかります。住むところが出来てもしばらくは東京で一人ぼーっとする生活を楽しむだけ。大変な覚悟をして上京してきたはずなのに、どうも緩い展開です。
それでも半年ほどプータロー生活をするとさすがに貯金の切り崩しでは心もとなく、バイトを始めイラストを売り込みに出版会社巡り。東海林さだおの青春記にも漫画を売り込みに出版社を回る話が出てきますが、とにかく担当の人に合って話を聞いてもらうのに勇気を振り絞らなくてはいけないし、持って行っても置いてくるだけでなかなか連絡も来ない。漫画家なりイラストレータを目指す同じような人は五万といて、その中で世に出て食べていけるようになるのはほんの一握り。私だと2~3回いい反応がなければそこですぐめげてしばらく引き籠りになりそうです。はるか昔の就職時の会社訪問の記憶がよみがえってきますが、当時はオイルショック後の就職氷河期で内定取り消しなども取りざたされていて、面接を受けても受けても連続で落ちると言うのは思い出したくもない記憶です。益田ミリは担当者の目に留まるようにあの手この手を考えてめげずに回っているうちに少しづつ仕事が入ってくるのですが、こうなると本人の努力もですが才能を認める担当者の眼力というのがいかに重要かと言うことですね。
第2章はコロナ前とコロナ禍の2019年から2022年までのエッセイで、第3章は同じ頃の長めのエッセイですが、読んでいると亡くなった父のことが時折出て来て、以前「永遠のお出かけ」でも書きましたが、父に対してアンビバレントな気持ちがありつつ、さりげないエピソードにそれでも深い愛情が見えてきます。自分には読む人の心に触れるような父に対するエピソードは何もないし何も書けないだろうなと思うと、ちょっと残念ですし、益田ミリの感性と才能に嫉妬してしまいます。
もう1冊はおなじみの東海林さだおの丸かじりシリーズの最新版。週刊朝日は今月で廃刊となるので東海林さんの丸かじりシリーズはどうなるのか。年齢も年齢なのでもう連載はやめるとなるとこのシリーズもあと1冊だけ?
この「町中華の丸かじり」は2019年9月から2020年11月までの連載分ですが、まさにコロナ禍が始まって猖獗を極めた頃。東海林さんの目に映ったコロナ禍の様子がよく分かります。記憶したくない過去で思い出したくもないかもしれませんが、当時の混乱ぶりと政府の行き当たりばったりのその場しのぎが直接的に表現されていなくても背景に映し出されています。小池都知事もよく登場しているのですけど、イラストを見ていると東海林さんの苛立ちがよく分かります。ちょっとびっくりしたのは「国難!ガリガリ君総理誕生す」、ここには総理大臣は誰でもできるんだと言う強烈な皮肉が入っている。あまり政治的な話は直接的には書かないのに、安倍総理については、
経綸、識見いっさいなし、そういうものは役人に書かせて透明なプロンプターに映してそれを棒読みすればよい。
棒読みをいかにも読んでいないように見せかける技術さえ習得すればよい。
あとは自宅のソファでお茶を飲みながら愛犬を撫でていればよい。
と書いている。ちょっと東海林さんのいら立ちが半端なく、このエッセイは激しくうなずくとともに思わず2度読みしてしまいました。
東海林さん85歳になっても健在です。
コロナ禍では二人とも外へ出かけることも出来ず、人とあって談笑することも出来ない。エッセイのネタにも困ると思うのですが、日常のさりげないこととか普段使いのものを視点を変えてちゃんと読ませるエッセイにしているテクニックはプロです。
雨の中出かけていくのも躊躇われ、所在のない時間をつぶすには、東海林さだおとか、益田ミリの本でも読むと何となくほっこりした時間を過ごすことが出来ます。
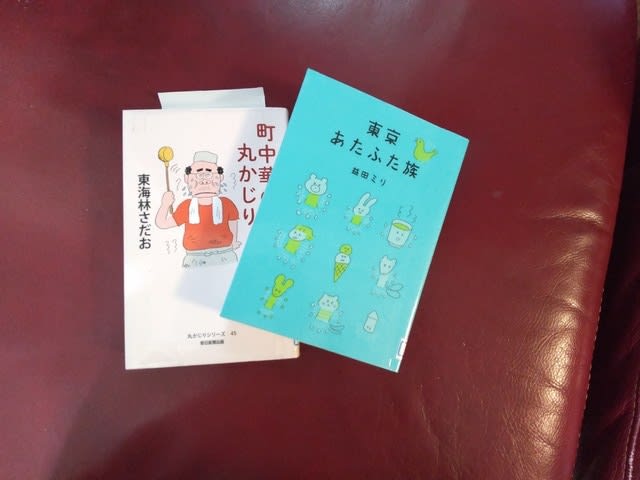
益田ミリの「東京あたふた族」は、3部構成。最初は上京したころの日々のエッセイです。ОL生活で貯めた200万円ほどを持って、イラストレーターになろうと誰も知り合いのいない東京で一人暮らし。今までの人生で1か月以上名古屋市を出たことがないというドメスティックにしか生きていない私にとっては無謀ともいえる行為。
当時無職の若い女性の一人暮らしは住むアパート探しも大変で断られてばかりだったのですが、いい不動産屋のおかみさんに出会って何とか見つかります。住むところが出来てもしばらくは東京で一人ぼーっとする生活を楽しむだけ。大変な覚悟をして上京してきたはずなのに、どうも緩い展開です。
それでも半年ほどプータロー生活をするとさすがに貯金の切り崩しでは心もとなく、バイトを始めイラストを売り込みに出版会社巡り。東海林さだおの青春記にも漫画を売り込みに出版社を回る話が出てきますが、とにかく担当の人に合って話を聞いてもらうのに勇気を振り絞らなくてはいけないし、持って行っても置いてくるだけでなかなか連絡も来ない。漫画家なりイラストレータを目指す同じような人は五万といて、その中で世に出て食べていけるようになるのはほんの一握り。私だと2~3回いい反応がなければそこですぐめげてしばらく引き籠りになりそうです。はるか昔の就職時の会社訪問の記憶がよみがえってきますが、当時はオイルショック後の就職氷河期で内定取り消しなども取りざたされていて、面接を受けても受けても連続で落ちると言うのは思い出したくもない記憶です。益田ミリは担当者の目に留まるようにあの手この手を考えてめげずに回っているうちに少しづつ仕事が入ってくるのですが、こうなると本人の努力もですが才能を認める担当者の眼力というのがいかに重要かと言うことですね。
第2章はコロナ前とコロナ禍の2019年から2022年までのエッセイで、第3章は同じ頃の長めのエッセイですが、読んでいると亡くなった父のことが時折出て来て、以前「永遠のお出かけ」でも書きましたが、父に対してアンビバレントな気持ちがありつつ、さりげないエピソードにそれでも深い愛情が見えてきます。自分には読む人の心に触れるような父に対するエピソードは何もないし何も書けないだろうなと思うと、ちょっと残念ですし、益田ミリの感性と才能に嫉妬してしまいます。
もう1冊はおなじみの東海林さだおの丸かじりシリーズの最新版。週刊朝日は今月で廃刊となるので東海林さんの丸かじりシリーズはどうなるのか。年齢も年齢なのでもう連載はやめるとなるとこのシリーズもあと1冊だけ?
この「町中華の丸かじり」は2019年9月から2020年11月までの連載分ですが、まさにコロナ禍が始まって猖獗を極めた頃。東海林さんの目に映ったコロナ禍の様子がよく分かります。記憶したくない過去で思い出したくもないかもしれませんが、当時の混乱ぶりと政府の行き当たりばったりのその場しのぎが直接的に表現されていなくても背景に映し出されています。小池都知事もよく登場しているのですけど、イラストを見ていると東海林さんの苛立ちがよく分かります。ちょっとびっくりしたのは「国難!ガリガリ君総理誕生す」、ここには総理大臣は誰でもできるんだと言う強烈な皮肉が入っている。あまり政治的な話は直接的には書かないのに、安倍総理については、
経綸、識見いっさいなし、そういうものは役人に書かせて透明なプロンプターに映してそれを棒読みすればよい。
棒読みをいかにも読んでいないように見せかける技術さえ習得すればよい。
あとは自宅のソファでお茶を飲みながら愛犬を撫でていればよい。
と書いている。ちょっと東海林さんのいら立ちが半端なく、このエッセイは激しくうなずくとともに思わず2度読みしてしまいました。
東海林さん85歳になっても健在です。
コロナ禍では二人とも外へ出かけることも出来ず、人とあって談笑することも出来ない。エッセイのネタにも困ると思うのですが、日常のさりげないこととか普段使いのものを視点を変えてちゃんと読ませるエッセイにしているテクニックはプロです。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます