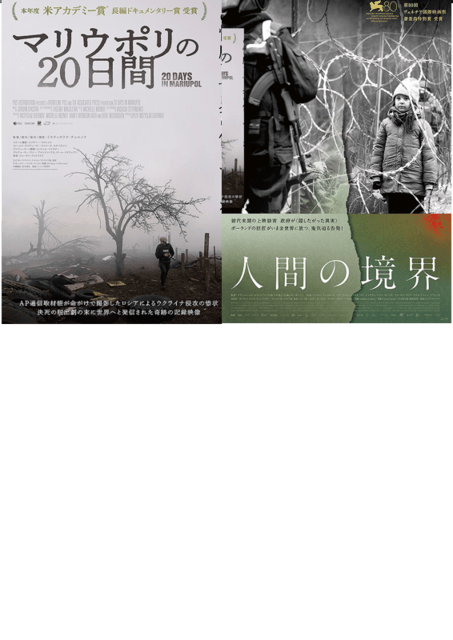警察、検察は証拠をつくる。その人を真犯人とするために。いや、逮捕、勾留した人物が本当の犯人かもしれない。しかし、裁判で有罪とするためには証拠を積み重ねて裁判官(所)を納得させればいいだけのことだ。しかし、そもそも証拠が作られたものであったとしたら。
一昨年大きな話題を呼んだテレビドラマ「エルピス〜希望、あるいは災い〜」は明らかに飯塚事件をベースにしたものだった。被害者の遺体が見つかった八頭尾山は、飯塚事件の八丁峠。不正確なDNA鑑定、目撃証言の信憑性など。しかし、飯塚事件では被疑者の久間三千年さんは一貫して否認していたのに死刑に。そして確定後わずか2年で執行された。
映画は、ある意味、極めて公平である。福岡県警の捜査員らの言い分、弁護側の見方、そして事件を報道した西日本新聞の記者たち。捜査員は絶対久間が犯人で間違いないと揺れることなく言い切り、弁護側は先述の証拠を訝り、報道は難航していた事件解決のスクープを打った。しかし、西日本新聞の編集キャップに当時の担当記者が一から洗い直そうと、担当していなかった記者らに命じ、長編の調査報道が掲載され、NHKドキュメンタリー、そして本作に繋がった。
この原稿執筆時点で、袴田事件の再審公判が結審し、9月には無罪判決が予想されている。この間、さまざまな再審無罪案件があるが、死刑囚の再審事案であり、その重要度は言うまでもない。袴田巌さんは、執行の恐怖のもとでの長期勾留で精神に障害をきたしている。しかし飯塚事件は執行されているのだ。もし無辜の民を国家がくびきっていたとしたら、取り返しがつかないどころの話ではないのだ。そして飯塚事件はその可能性が大である。足利事件でDNA鑑定の新方式で再審無罪が出る直前に、古い鑑定方式で有罪となった久間さんの死刑を急いだのではとの疑念が拭えないからだ。確定から2年での死刑執行は異例中の異例である。オウム真理教事件でも7年の期間がある。さらに、再審却下の理由はDNA鑑定の証拠能力を無視しても「総合的に判断して」久間さんが真犯人と推定できるとする。確定判決の依拠するところはDNA鑑定だけであったはずなのにである。
映画を見ていて感じるのは、捜査側の人たちが退職してずいぶん経ち、取材を断ってもいいのに、皆誠実に対応していることに驚いたことと、揺るぎない久間=犯人への強固な確信だ。多分、迷いを一ミリでも入れれば自己を保てないという整合性への自己納得(暗示)なのではないか。一方、スクープを打った西日本新聞の記者は逡巡そのものの体である。あの久間=犯人報道は正しかったのか、警察に沿った報道で良かったのか。だから検証がなされたのだ。
実は、虚実不明であるが、安倍政権下で政権からの圧力、最大限政権に忖度したNHKをはじめとするメディアが圧を感じず、以前と比べると報道の自由さを取り戻したという。それが今般の正義の行方NHK版に繋がったとも。ならば、次は司法の誤りにも真実追求の刃を向けるべきである。袴田事件再審公判と並行して、日弁連をはじめとして刑事再審法改正の機運が高まっているところでもある。
狭山事件では鴨居の上にペンが、袴田事件では味噌タンクから衣類が。郵便不正・厚労省元局長事件ではフロッピーディスクの日付書き換えが。大川原化工機事件では報告書改竄が。
警察、検察は証拠をつくるのだ。