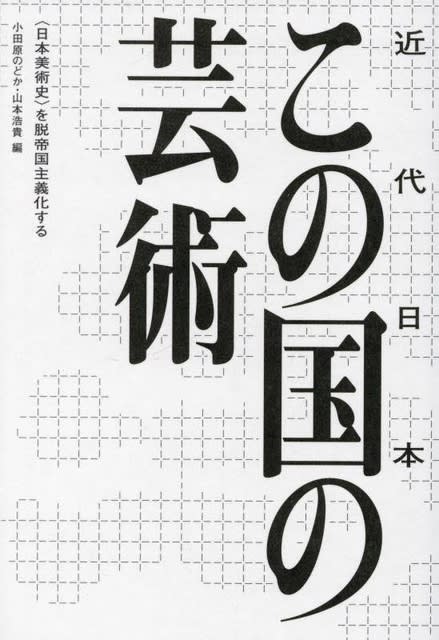「誰に食わせてもらっていると思うんだ!」。本書でも紹介され、解説の上野千鶴子さんが取り上げる近代日本での典型的な言い回しだ。これは、ずいぶん前に亡くなった私の父が、私の母である妻に浴びせていた言葉でもある。しかし、その言辞が「家父長制」の悪しき発現であると知ったのはずっと後のことだ。
強固に残る性別役割分業、選択的夫婦別姓が進まない「家制度」の残滓、政治でもビジネスでも女性が指導的立場に立てないなどなど。「家父長制」が原因、遠因と思われる現代社会の性差別は弱まってきたとの見方も、全く改善していないとの見方もできる。ではその「家父長制」はいつから、どこで始まり、長らえてきたのか。あるいは衰退しているのか。
本書は、人類の誕生から古生代の集団生活から紐解き、キリスト教など宗教との関係、産業革命後の近代まで時代に応じて「家父長制」は浸透し、その拡張したり、弱まったりの歴史を克明に記す。「家父長制」は字の如く父系社会が基本だが、母系社会ではもちろん見られない。だから、父系社会に見られる男子のみが相続するといった慣習はない。しかし、母系社会は、ステレオタイプな平和主義や協調主義ではない。このステレオタイプも家父長制が圧倒的に強い歴史の作為かもしれない。女性も戦士になるし、争いも起こる。当たり前である。
要はその時代、地域社会にとって「家父長制」を維持、温存、拡大する必要性があったのだ。日本でなら、明治以降男系男子しか認めない天皇制と、その神権天皇の赤子である国民全てが家長たるたった一人の男性に支配された「家制度」を想起すると分かりやすいのではないか。夫が妻の元に通った婚姻形態や、女性でも天皇になった前近代でそれは明らかだ。日本の例はさておき、興味深いのは、イスラム社会での女性の地位や、女性だけを蹂躙する制度や風習を女性自身が守ろうとすることがあるという歴史的変遷だ。イランではホメイニ師のイスラム革命前には女性の地位は高かったし、これはアメリカと結びついたパフラヴィー政権が資本主義の発展のためにそれを企図したこと。あるいは、革命後40年経ち、ヒジャブを強制されるものの男性を養う女性たちの存在。また、後者ではFGM(女性性器切除)を支持する女性たちの存在など。
根本的な問題は「家父長制」を支える言説が、「男の方が強くて賢い」「支配者に向いている」「女は出産・育児するから働く(戦う)のに向かない」など、根拠もない陳腐なものばかり、それも現代に言われることばかりということだ。例えば、戦争で女性が奴隷にされたり、略奪されるのは次代を産むからである。その構造を支配しようとする欲望こそ「家父長制」と考えるとストンと落ちる。
選択的夫婦別姓法制化に頑迷に反対する層は、安倍政権を後ろ押しした統一教会などの宗教右派と、安倍亡き後その意志を注ぐと鮮明にしている高市早苗議員などである。彼らは、戦前の日本のカタチ、それも大和政権から日本史を数えるとほんの半世紀ほどのことであるが、を最良・最上の政治体制とする価値観にまみれている。しかし、冒頭に指摘したような性差別が横たわるこの国の根本に巣食う「家父長制」をこそ破壊されなければならない。(『家父長制の起源』アンジェラ・サイニー 集英社 2024)