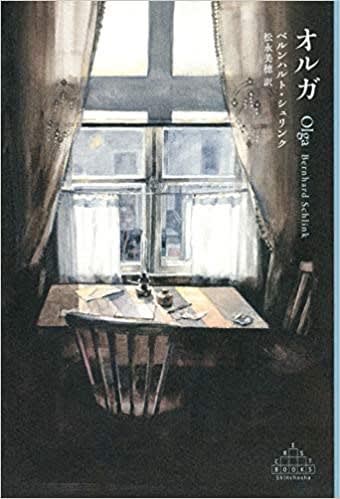小説は多分あまり読まない方なので、たまたまそう感じたのかもしれないが、翻訳ものの語りにとても惹かれる。カズオ・イシグロがノーベル文学賞を取ったので『わたしを離さないで』を読んでみたが、抑揚感の希薄な語りが素敵だった。それでいて引き込まれた。ベルンハルト・シュリンクの『オルガ』(松永美穂訳 新潮クレスト・ブックス)は映画にもなった『朗読者』(映画邦題 愛を読むひと)以来だが、やはり淡々とすすむ語りにまたしても夢中になった。
主人公オルガは、ドイツ東北部ブレスラウ(現ポーランド)で生を受けるが、幼くして両親が発疹チフスで死去。祖母に引き取られ、ドイツ北東部に移るが祖母がスラブ系でなくドイツ系の名前に変えようとするが頑として拒否。祖母とはソリが合わず孤独な少女時代を過ごすが、貧しい中勉強を教えてくれる教師に出会い、師範学校に進学でき、学生寮にも入れる。教師になったオルガは農園主の息子で幼馴染のヘルベルトと恋に落ちる。しかしドイツ帝国の威信を体現したいヘルベルトは外国に出征し、北極圏の探検に命を懸け、オルガのもとにいない。ここまでは貧しさ、拭いきれない孤独感などのハンディがありながら人一倍の努力と独立心で自立を果たした女性の物語。しかし、これは3部構成の第1部。第2部で老いたオルガに可愛がられ、親子以上に年の離れたオルガに寄り添い続けたフェルディナントのオルガとの思い出が語られる。そして第3部ではフェルディナントが、オルガがヘルベルト宛に送ったもののヘルベルトのもとに届かなかった大量の手紙を読み、オルガの本当の思いを知るというもの。
切ない。みなし子ではないとはいえ唯一の肉親祖母とはソリが合わず、ヘルベルトと妹のヴィクトリアとは幼い頃あんなに仲よかったのに、年頃になり、ヘルベルトがオルガとの結婚を望むようになると身分違いを理由にヴィクトリアはオルガを徹底的に差別、妨害する。教職を得て安定した生活であったが、ヘルベルトはいつ戻ってくるかも分からない。そして不十分な装備のまま極寒の地に出かけついに帰って来なかった。いつも孤独だったオルガ。そのオルガが支えた、いや、支えられたのは同僚の養子である幼いアイクの成長を見守られたことと、耳が聞こえなくなって教師を辞め、お針子として勤めていた家の息子フェルディナントと交流できたこと。しかし、オルガを支えていたのは二人の男の子と過ごせたことより、ヘルベルトへの変わらぬ思いと膨張する帝国ドイツへの不信感だったのかもしれない。
だが、ドイツ帝国の膨張政策になんの疑念も持たず、他国との戦争に出かけ、武勲をあげ、次第に極北探検家として夢を大きくするヘルベルトこそ「帝国」=男像の権化であったのかもしれない。あんなに慈しんだアイクは成長するとナチ党を信奉するようになり、ナチスドイツでは非道な指揮官となっていく。
二つの大戦を経験し、時代に翻弄されたと書けば簡単だが、オルガの周囲はその時代の流れに敏感な者と鈍感な者のグラデーション。そして多分オルガの孤独の正体は、「帝国」「ナチスドイツ」「男の」と言った大文字のはびこる時代と、それに反する声も粗雑に聞こえたことへの違和感ではなかったか。そしてオルガが貫いたのは、帝国を帝国たらしめたビスマルクへの拒否の態度であった。オルガの立ち位置は子どもの頃から何も変わっていない。大文字が時代ごとに変わり、貧しい者、持たざる者を差別し、排除し、そしてまたその対象を作り出していく。オルガの賢さ、敏感さが清々しいとともにやはり切なくて、淡い読後感を伝えられなくてもどかしい。