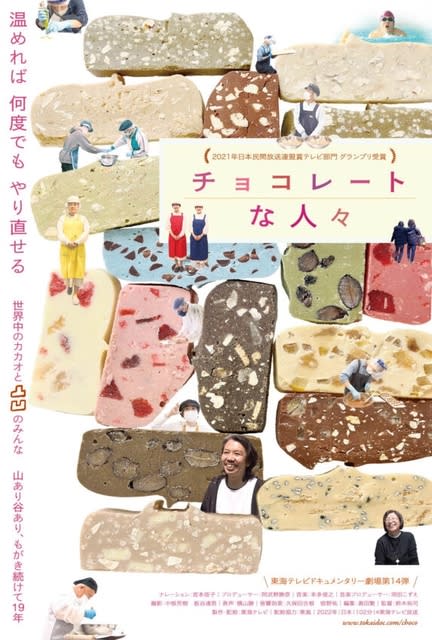黒澤明ファンでも、古い日本映画ファンでもないので、さすがに志村喬版は見たことがない。それでも、カズオ・イシグロ脚本にかかる本作を見れば、黒澤・志村の「生きる」が名作であることが偲ばれる。
ストーリーに現代のようにひねりがあるわけではない。余命いくばくもないことを知った男が、無気力に生きてきた自身の現在、生き方を見つめ直し、最後にやり遂げる仕事を見出す。言ってしまえばただそれだけだ。もちろん彼が正気を取り戻したのには、職場の部下である溌剌とした若い女性の存在がある。これは老いらくの恋ではないし、下心でもない。彼女は、階層的には上流出身ではなく、洞察力深い人物にも描かれていない。若さとそこから迸る衒いのなさだけが取り柄にも見える。しかし、そこに彼は「生きる」意味とその表し方を見とったのだ。そう、「生きる」ことの崇高さを見出したのだ。
日本人のルーツを持つカズオ・イシグロが小津安二郎の世界ではなく黒澤映画、それも「生きる」を選んだことに英国と日本、明快ではない曖昧な態度、本質を直接は問わないその文化的近似性に着目したからの成功と言えるだろう。カズオ・イシグロの世界は静謐、特に大きな事件も起こらず、展開も穏やかであるのに読む者を引き込む。『クララとお日さま』は未読だが、『日の名残り』の語り手のとても抑えた、それでいてページを繰るのももどかしいくらいの展開にワクワクし、アンソニー・ホプキンスの映画版も何度も見たことを思い出す。そのイシグロが選んだのが「生きる」。戦後間もない頃を時代背景として、敗戦国の日本と戦勝国の英国。とは言え、どちらも戦後復興からこれからという時代。高度経済成長はまだだが、これからは戦争もなく、働いて自分も家庭も国も上向きになるだろう。主人公は世代的に戦争も経験している。出征経験もあるかもしれない。それが、不治のガンと知り、半ば自暴自棄になるが、それまで自分は一所懸命に生きてきたのか、なすことをなしてきたかと反芻すると、光が見えてきた。人の「生きる」には死とは違った終わり方があるのだと。
ウィリアムズ演じるビル・ナイがいい。風貌はリタイアしてもいい老齢だが、部下はいるが役所の一介の市民課の課長。部署間の関係もあり、権限が大きいわけではない。たらい回しにしてきた案件、地区の婦人らが陳情してきた公園整備がある。死期を知り、貯金をおろして無断欠勤を続けるウィリアムズは、街で部下のマーガレットに会い、何かと誘い出す。戸惑うマーガレット。しかし、ウィリアムズが、忙しそうにして自分の退職金だけが目当ての息子にはガンを告げられないでいるのに、マーガレットには打ち明ける。驚くマーガレットの頬を伝う涙がとてつもなく美しい。本作で一番好きなシークエンスだ。やっと他者に自己の残された時間の短さを伝えられたウィリアムズは、公園整備に残り時間の全てをかける。
マーガレットに「ゾンビ」とあだ名を付けられていたウィリアムズが「復活」したのだ。黒澤の「生きる」には、戦中世代の志村演じる渡辺の記憶、それは戦時中賛美された「散華」という戦場で死ぬことこそ美とする倒錯した価値観を見出すのは容易だろう。しかし、ウィリアムズの「復活」は死して、あるいは死ぬ前の底力といった嫌らしい見方はしたくない。「生きる」ということは、時流を含めいかなるものにも流されず、流されていることを自覚しつつ、それに抗う自己確認の絶え間ない、弛まない作業なのだろう。
かくも「生きる」というのは深く、尊いものなのだ。