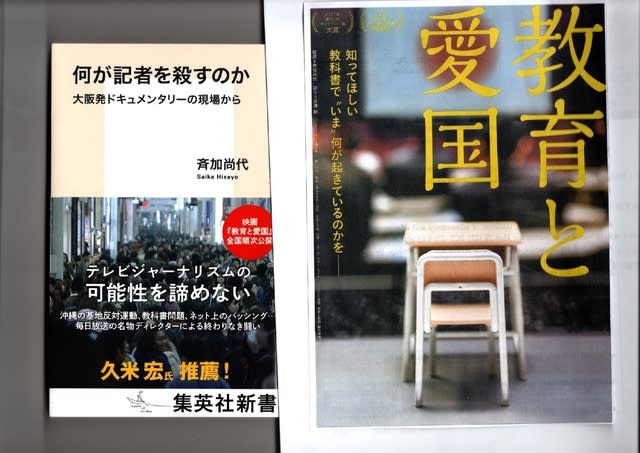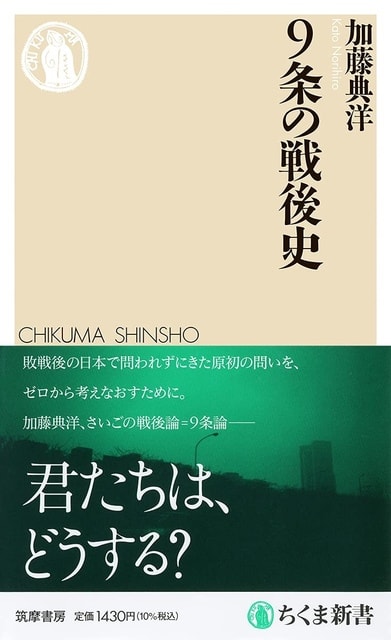戦争の不合理、不条理が語られることは多い。しかし、そもそも合理的な戦争、条理にかなった戦争などあるものだろうか。本作を見た第一の感想だ。そして、その不合理、不条理の被害を受けるのは戦争を開始し、指揮する指導層とは一番遠い存在の市井の市民、末端兵士などだ。
本作とその後のロシアのウクライナ侵攻をめぐる情勢−姿勢と言った方がいいかもしれない−から、ロシアでは上映が禁止され、自身はプーチン非難をしないヨーロッパ映画アカデミーに抗議し、一方ロシア映画をボイコットせよとウクライナ映画アカデミーを批判したため除名されたその人こそ、監督のセルゲイ・ロズニツァである。
ロズニツァ監督はこれまで数々の優れたドキュメンタリー作品を制作している。だから本作もリアルと見紛うが、完全な劇映画である。戦争の不合理、不条理は、例えば戦火を逃れ、ジメジメした地下で不衛生、不健康な生活を余儀なくされる住民に、ウクライナ軍の末端兵士が親ロシア軍兵士に捕らえられ、晒し者にされるが、その兵士を辱め、苛烈な暴力をふるい、そして「殺せ」と騒ぎ立てる親ロシア住民に見るころができる。そしてその暴力的な若者は結婚式では明るく祝う姿が。さらに、政治に距離を置きビジネスに勤しむ男は、ビジネスに不可欠の車を親ロシア軍に接収され、「車を軍に委任します」と書けと脅かされる。その上で法外な金銭を要求される。これでもかと描かれる不合理、不条理の連続にげんなりする私たちを欺くかのように、最初と最後に登場する被災者アクターたち。親ロシア勢力の宣伝のために、地域住民を装ったアクターに「(ウクライナ軍の砲撃で)人が死にました。本当に怖いです」と語らせる。ところが、アクターら全員と、軍との連絡役の人間まで、射殺する兵士。その現場に急行したのは警察や救急と共にテレビメディアであった。そう、全てやらせだったのだ。そうすると、途中の地下の避難住民も、うち殴られるウクライナ兵士も、全てやらせかと勘繰ってしまう。その証拠に、最初から最後まで当時人物は少しづつ、つながりがあり、全て一連の輪の中に収まってしまう、ある意味壮大なメタ構造を有しているのが本作のキモだ。
これは戦争の本質、つまり、始まってしまえばどんどん誰が本当の責任者か、誰を追及すれば正当であるのか分からなくなってしまうという、終わりが見えない果てしない戦争の本質を表していると言えよう。そして、その責任追求の矛先の不明さとパラレルにあるのが、住民、兵士らを取り巻く不合理、不条理の連続だ。例えば、車を奪われるくらいの不条理は、命を落とすことに比べればマシに思えてくるし、あまりにも不合理、不条理が蔓延していて、戦争そのものへの反戦、厭戦感も麻痺してしまうかのようだ。そういう目で見ると、安倍政権以降何重にも、何度も重ねられてきた不合理、不条理−国会招集を怠ったり、モリ・カケ・サクラ、日本学術会議任命拒否などいくらでもある−は全て、この不合理、不条理に国民を馴致させるためであったのか、戦争準備だったのかと合点がいく。ロシアのウクライナ侵攻で「核共有」「敵基地攻撃」「憲法9条改正」と、好戦派が勢いを増している現在の姿がその証だ。
ロズニツァ監督は自分をコスモポリタン(地球市民)であるとする。国境なきところに国境を超えた戦争など存在しない。そんな夢想を嘲笑うがの如く、あらゆる不合理、不条理に直面し、人間のいやらしさ、悲しさ、愚かさ、非道さをこれでもかと見せつける本作は劇映画であるゆえにとてつもなくリアルである。