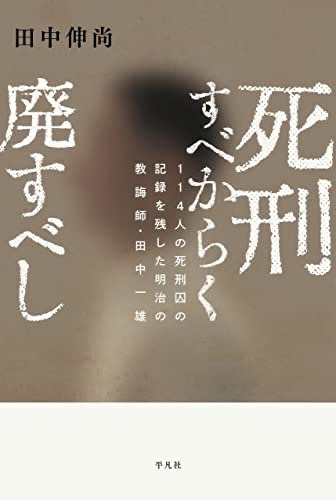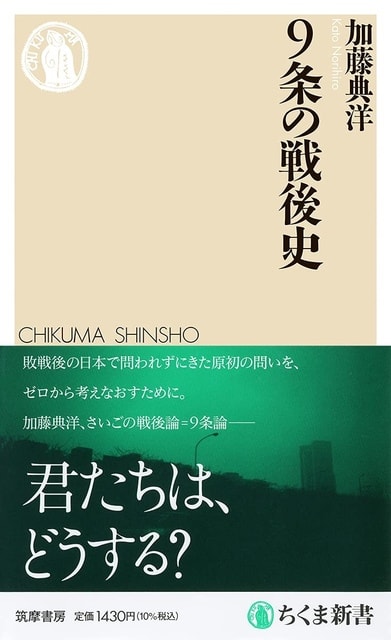著者には『大逆事件 死と生の群像』(2010岩波書店)という労作がある。労作というのは、『大逆事件』の取材に10年以上の歳月をかけ、その後も『飾らず、偽らず、欺かず 管野須賀子と伊藤野枝』(2016 同)、『一粒の麦 死して 弁護士・森長英三郎の「大逆事件」』(2019 同)と徹底して「大逆事件」を追及してきた最近作であるからである。実は、著者の田中伸尚さんには30年以上前に講演をお願いしたことがあり、その中で「大逆事件」で死刑判決、減刑、獄中で自死した高木顕明のことを取り上げられた。であるから著者にとってこの労作には40年いやそれ以上を超える取材とこだわりがあると考える。
著者は『大逆事件』で、幸徳秋水、管野須賀子ら以外の著名ではない被告人に思いを馳せる重要性を指摘している。そうである。24名もの冤罪で「大逆」を問われ、うち12名が判決後まもなく頚きられた戦前日本で最大級の国家犯罪であるのに、その雪冤が全くなされていない。『一粒の麦』では、死刑を免れた坂本清馬の戦後の再審請求を担当した森長を取り上げたが、本書の教誨師・田中一雄はさらに資料がない。どこに光を当てるのか、当てられるのか。田中一雄の手記には森長の調査の過程で出会ったという。200人を超える死刑囚の教誨師を務めた田中は浄土真宗の僧侶であった。そして著者の記するように当時の教誨は「教育勅語にもとづく国民道徳を説き、極悪人の心を落ち着かせて死を受け入れさせる『安心就死』であった」(4頁)。しかし、田中は死刑(制度)に違和があった。教誨を通して、死刑囚が自己を振り返り、十分な機会が与えられれば更生の可能性が大きいと感じていたからだ。制度としての死刑の壁はあつく、田中の悲憤はどう描かれたか。
本書は4章構成である。教誨した114名分の記録を残した田中のその全体像から、死刑囚に寄り添う姿勢を分析する第1章。多いのは強盗殺人や田中が取り上げる「情欲殺人」といった現代の刑法概念で捉えると、動機の背景や態様が複雑ではなくどちらかというと「粗暴犯」に分類される事案かもしれない。しかし、そのようないわば単純な動機や犯意を持つ被告人は、更生の可能性こそ高いと田中は考えた。「手記には、情欲に絡んだ殺人事件は十数件を数えるが、いずれについても田中は『死刑の必要なし』『死刑するには及ばず』『死刑は無益なり』などと言い切っている。」(43頁)
さて、人を実際に殺したわけでもなく、その「謀議」にかかずらったとされるだけであるのに24名もの死刑判決を出した大逆事件を扱う第2章。判決からわずか6日で12名の死刑が執行されたこともあり、どの死刑囚にどのような教誨がなされたか不明な部分が多い。執行には立ち会った田中も手控えには判決をそのまま写すのみで、感想もない。著者は「『大逆事件』が政治的でっち上げでもそれを見抜ける立場にはいなかった田中は紛れもなく明治人で、同時代のほとんどの人びとに共通する明治天皇への敬愛は強かったろう。それゆえ押し黙ったように寡黙になったのだろうか。」(101頁)と推しはかる。同時に「『沈黙』を貫いたのは田中のぎりぎりの抵抗だったのかもしれない。」(104頁)。しかし手記から田中が管野須賀子の明晰さを読み取り、著者によればお互いを尊重する交流があったことを示す資料もある。ただ、やはり大逆事件の核心は実行行為ではなく、思想そのものを刑死させる(当時の)刑法第七十三条の存在であった。大逆事件後の田中の教誨メモは一気にそっけなくなる。
田中の手記が残された経緯を辿るのが第3章。その最重要のキーパーソンたる教誨師がキリスト者の原胤昭(たねあき)である。田中から手記を託された原がその保管と分析に尽力した。田中一雄が旧会津藩士で前歴があり、医師でもあった。それがなぜ東京で僧侶となり、教誨師を務めることになったのか。真偽を確かめる道行きが第4章である。結局決定的な立証とはまではいかないまでもその可能性は十分にあり、幕末維新の激動期、その激動の目撃者たる旧会津藩という特殊な出自、さらに天皇教には完全に絡め取れなかったクリスチャンの原に手記を託した必然性。
物語は多分終わらない。「死刑制度」は「未決の問題」であり続けるからだ(204頁)。田中の、生きていてこそ更生が得られるという考えは、浄土に行く仏教概念より、肉体の復活を信じるキリスト教に近いとも言える。しかし、現実に死刑はあり、現在も続く。冤罪が明白である袴田巌さんの再審が決まったのはついこの間だ。だからこそ「死刑すべからく廃すべし」なのだ。
(『死刑すべからく廃すべし 114人の死刑囚の記録を残した明治の教誨師・田中一雄』2023 平凡社)