宝巌寺の宝物を公開 「竹生島文書」重文指定を記念
滋賀県長浜市、竹生島の宝巌寺(ほうごんじ)に伝わる「竹生島文書」が国の重要文化財に指定されたのを記念した名宝展が同寺宝物殿で開催されている。織田信長や地元の戦国武将、浅井氏に関する同文書9点や仏像など計23点が展示されている。
指定された竹生島文書は鎌倉時代から明治時代にかけて書かれ、312通ある。武家の文書が豊富なほか、竹生島信仰に関する勧進状などがある。政治・宗教史料として学術的評価が高く、9月に重文指定された。
滋賀県長浜市、竹生島の宝巌寺(ほうごんじ)に伝わる「竹生島文書」が国の重要文化財に指定されたのを記念した名宝展が同寺宝物殿で開催されている。織田信長や地元の戦国武将、浅井氏に関する同文書9点や仏像など計23点が展示されている。
指定された竹生島文書は鎌倉時代から明治時代にかけて書かれ、312通ある。武家の文書が豊富なほか、竹生島信仰に関する勧進状などがある。政治・宗教史料として学術的評価が高く、9月に重文指定された。
「近江水の宝」は、琵琶湖や水にかかわる文化遺産のうち、特に優れたものとして滋賀県教育委員会が64件を選定し、地域資源として魅力を発信して、その価値の定着化をはかっています。
上布とは麻を素材とした織物で、近江上布の生産は鎌倉時代に京都から職人が移り住んだことに起源するといわれています。室町時代にはすでに高島(高島市)や高宮(彦根市)の上布が名産品として知られ、江戸時代には彦根藩の奨励策もあって、豊かな湧水に恵まれた湖東地域一帯の村々でさかんに生産されました。そして、これらは中山道高宮宿に集められて旅人へ販売されるとともに、近江商人によって全国に持ち運ばれたことから、高宮布と呼ばれて名声を博し、彦根藩から将軍家への献上品としても用いられました。
現在も愛荘町では、宇曽川や愛知川の豊かな伏流水の恵みを受けて、高宮布から受け継いだ伝統の技で近江上布を作り続けています。また、豊郷町は、こうした高宮布を江戸時代に商った偉大なる近江商人のふるさとです。
今回の探訪では、県の文化財専門職員および、愛荘町や豊郷町の観光ボランティアガイドのみなさんが同行案内し、近江上布の織手と商人の里を、中山道に沿って詳しく訪ねます。


てんびん鞠資料館 http://plaza.rakuten.co.jp/t036kkk/diary/201210080001/
探訪「近江水の宝」~近江上布の織りてと商人の里を歩く・・・愛荘・豊郷~20121014





旧愛知川役場



近江の麻(近江上布伝統産業会館 見学)
近江上布は、京都の職人が宇曽川沿いで農業をするかたわら教えたのが始まりと伝えられ、永禄元年(1558)には犬上、愛知、神崎、蒲生などで生産されたものが近江商人によって諸国に売りに出されたといわれています。江戸時代には彦根藩は、国産方により、彦根藩の副業対策として麻布の振興を計り、着尺地、蚊帳地を増産し、文明年間には板締や櫛押による絣模様が開発されました。天保2年(1831)には、近江麻布蚊帳改会所を設立し、良品の生産に努め、近代になると、羽根巻による型紙捺染法を工夫し、絵羽調の縮絣が人気を呼ぶようになります。昭和52年3月には伝統的工芸品として国の指定を受けるにいたります。














中山道愛知川宿~中仙道を東へ下る

 むちんばし絵図
むちんばし絵図



















 愛知川宿北入口の道標
愛知川宿北入口の道標
更に、中山道を北へ・・・商人屋敷や神社仏閣が続きます。























 歌詰橋…愛知川宿から、宇曽川を超える橋
歌詰橋…愛知川宿から、宇曽川を超える橋


愛知川ボランティアカイドさんの案内は、ここまで!
歌詰橋を渡れば、豊郷町!
 橋をわたり豊郷へ
橋をわたり豊郷へ
 豊郷町ボランティアガイドさんに交代
豊郷町ボランティアガイドさんに交代


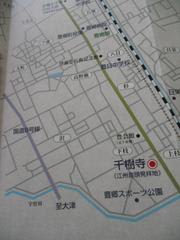









パンフレットより


江州音頭http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E5%B7%9E%E9%9F%B3%E9%A0%AD
http://go-shu.biwako-visitors.jp/index.html






滋賀県には近江商人の町と呼ばれるところがいくつかあります。豊郷町もそのひとつです。
豊郷出身の豪商
又十・・・藤野家屋敷(天平の飢饉普請の屋敷)
北海道の松前で、「はごろも缶詰」創業、










現在の大手商社の伊藤忠・丸紅の創始者で近江商人の筆頭とあげられる伊藤忠兵衛は、1842年に繊維品の小売業を営む「紅長」の家に生まれました。現在、伊藤忠兵衛の本家は記念館として開放されており、「見越しの松に黒い塀」と呼ばれた堂々とした造りで、中山道に面してひときわ目をひきます。




総合商社の伊藤忠、丸紅の創業者である伊藤忠兵衛の出身地も豊郷町です。伊藤忠兵衛に仕え、後に丸紅商店(現、丸紅)の専務となったのが古川鉄治郎という人です。古川鉄治郎の出身地も豊郷町。



近江商人を表わす言葉に「三方よし」というものがあります。商売においては、売り手よし、買い手よし、世間よしの三方がよくなければならないとする経営理念です。三方よしの実践者であった伊藤忠兵衛の意思を忠実に受けついた古川鉄治朗は、世間よしとするための事業を行ないました。
それが旧豊郷小学校の建設。旧豊郷小学校を目の前にしたとき、近江商人の地域社会に貢献したいという、心意気に圧倒されるます。
















アニメ殿堂【旧豊郷小学校】「聖地巡礼」としてファンが訪れているhttp://plaza.rakuten.co.jp/t036kkk/diary/201210160004/
旧豊郷小学校の校舎は、今からおよそ70年前に建設されました。当時としてはめずらしい鉄筋コンクリートのヴォーリス建築。 写真でも分かるように、横に長い建物で、その趣のある様はとても小学校とは思えません。 当時のお金で60万円の費用、古川鉄治郎は私財を費やして小学校を建設し、寄贈。 故郷に充実した教育設備をもった小学校をつくりたいとする思いが、この事業を導いたのです。

しかし、建設から70年を経た現在、この校舎は使用されていません。 老朽化による、強度不足で、安全が確保できないとの理由がら、一時は解体の危機に遭遇しました。 地域住民からの反対運動で何とか今現在は解体されずに残っています。 新校舎も建設されました。
近江商人の三方よしのなかで、世間よし実践の証として記念碑的に残すのがいいのかどうか、保存のための費用など、まだまだ検討すべきことがらは多くあるように思います。
那須城は旧中山道沿いにあって、豊郷町の八幡神社一帯とされ、八幡神社の境内に石碑が建てられている。
豊郷小学校の南に土塁が残されていたといい、その規模は一辺が50m~100mはあったことになる。
また、付近には「門根」という一画があり、城門があったという伝承もある。



八幡神社前には、昔は豊郷町役場前にあったとされる土饅頭型の一里塚が再現されており、このような一里塚もあったのかと認識を新たにした。

 那須城の隣に「弘誓山称名寺」
那須城の隣に「弘誓山称名寺」
那須城は治承・寿永の乱(源平の争乱)において、元暦2年(1185年)の屋島の戦いで平氏方の軍船に掲げられた扇の的を射落とした那須与一宗高の次男・砂田民部大輔宗伝が城を築いたと伝えられるが、定かではない。
近江七弘誓寺:中興の祖は源平の合戦のときの「扇の的」で有名な源氏の武士那須与一宗高の二男である願名坊宗信です。 那須与一は東国下野国から近江の国に封ぜられ石畑建部領主となり発願して建てた寺。




・・・豊郷駅へ
~近江上布の織りてと商人の里を歩く・・・愛荘・豊郷~充実した、探訪ウォークでした
消費カロリー 791.9kcal 脂肪消費量 113.1g
今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。
水茎岡山城(滋賀県近江八幡市牧町) 別 名:岡山城
遺 構:土塁、石垣、堀切、竪堀 山城(標高187.7m、比高102m) 築 城 者:九里備前守信隆 築 城 年:永正5年(1508)頃
 八幡山から見た水茎岡山城。
八幡山から見た水茎岡山城。
 頭山の麓に建つ城址碑
頭山の麓に建つ城址碑
城跡の石碑がありこれで満足とするしかない。背面側が大きな山の方である。出張後なので杖もなく(杖があれば地面を掻き分けマムシをよけれる)藪に入る気がしない。
 岡山の全景左側が大山、右側が頭山
岡山の全景左側が大山、右側が頭山
 岡山の全景右側が大山、左側が頭山
岡山の全景右側が大山、左側が頭山
頭山に
立ち入り禁止の、林道がきれいに除草されてる、狼煙リレーの準備かも?





 11月の狼煙リレーの狼煙台?
11月の狼煙リレーの狼煙台?
 牧水泳場から、急な階段が整備・除草されていた。
牧水泳場から、急な階段が整備・除草されていた。
 階段を上がり、そのままブッシュの山上を目指す。
階段を上がり、そのままブッシュの山上を目指す。
 「削岩のノミ跡」がはっきり三つ。
「削岩のノミ跡」がはっきり三つ。

 山上の平削地、びわこの湖上監視
山上の平削地、びわこの湖上監視














水茎岡山城は近江八幡城の西方、琵琶湖に面した頭山に築かれた山城である。伝によれば、南北朝時代に六角氏の湖上警備の城として築かれ、戦国時代最中の永正五年(1508)ころより本格的な築城が行われたようだ。 かつては琵琶湖に浮かぶ水城であったが、戦後の干拓事業によって周囲が埋め立てられてしまい、戦国時代に「湖中の浮城」といわれた風情はない。戦国時代の城主は、六角氏の被官九里氏であった。
水茎岡山城が戦国史に大きな足跡を刻んだのは、幕府内における抗争に敗れた十二代将軍足利義澄をかくまったことである。当時、幕府は管領細川氏の内部抗争が続き、将軍はまったく政争の具ともいえる傀儡状態であった。義澄は細川澄元にかつがれて将軍職にあったが、細川高国と大内義興のかつぐ前将軍足利義尹(のち義稙)に京を追われ、近江に逃れて岡山城に入り再起を期したのである。しかし、京への復帰はならず、永正八年(1511年)、むなしくこの城で病没した。その後、六角氏と伊庭氏との間で抗争が起こると、九里氏は伊庭氏に与して活躍したが、敗れて岡山城は廃城となった。
【水茎岡山城の縄張り】
 縄張り図【頭山に本丸。大山に二の丸。亀山に三の丸
縄張り図【頭山に本丸。大山に二の丸。亀山に三の丸
 水城(昭和24年頃)・・・戦争の引揚者の為に干拓
水城(昭和24年頃)・・・戦争の引揚者の為に干拓
 発掘調査の遺構図
発掘調査の遺構図
岡山城は琵琶湖の東岸に位置する標高187mの岡山に築かれた城です。岡山は古来和歌に「水茎の岡(みずぐき
のおか)」として詠まれた名勝の地で、城は別名水茎岡山城(すいけいおかやまじょう)とも呼ばれています。
岡山城は、南北朝期に近江守護佐々木氏が湖上の監視所として築いたとされていますが、室町期には在地領主九
里氏の居城となっています。永正5年(1508)、将軍足利義澄が京都を逐われ、近江に逃亡しました。坂本から長命
寺をへて、最終的に岡山城に入ります。応仁の乱の後、足利将軍家も分裂し、将軍が京都を逐われる事態がしばし
ばおこります。この時は周防の大内氏のもとに身を寄せていた前将軍足利義尹が、京都で権力を握っていた細川高
国と結んで軍勢を率いて上洛しようとしており、高国と敵対する細川澄元と結んでいた義澄は六角氏を頼って近江
へと逃れたのでした。その3年後、足利義澄は岡山城中に没します。一方、六角氏と対立を深めていた守護代伊庭
氏は九里氏と結んでおり、永正15年(1518)六角氏と結んだ細川高国によって岡山城は攻撃を受けます。永正17年(1
520)岡山城は陥落し、伊庭氏・九里氏は退城しましたが、その後も戦いは続き、最終的には大永5年(1525)、六角
氏の江北出陣の隙を突いて挙兵した伊庭氏・九里氏の残党が、観音寺城の留守居であった後藤氏と戦った黒橋の戦
いに敗れ、伊庭氏は歴史の表舞台から姿を消します。岡山城もこの段階で廃城したとされています。
岡山は三つの小丘陵が連なってできて山です。琵琶湖に近い方から頭山(標高147m)・尾山(標高187m)・後山(標高113
m)と呼ばれていますが、このうち頭山・尾山に城の遺構が見られます。また現在は干拓によって失われていますが、かつて
は城の南面に内湖が広がり、湖上の浮城のような城でした。頭山は城の本丸といわれていますが、山頂部は造成工事によって
城の遺構は破壊されており、わずかに山復部に帯郭状の平坦部が見られるだけです。一方、尾山山頂部には城の遺構が良好に
残されています。山頂部に二つの郭が並んで築かれ、両者は土橋でつながっています。また郭の周囲を帯郭が取り巻き、琵琶
湖側の外周には土塁が巡っています。南斜面には山麓へと延びる竪堀があります。
頭山と尾山との間の鞍部は現在湖岸道路が通っていますが、道路建設に伴う発掘調査で建物礎石と石垣が発見されました。永正5年に岡山城に入った足利義澄の御殿跡ではないかといわれています。
岡山城へは、近江八幡駅より近江鉄道バス野ヶ崎行きで牧町西口下車、湖岸道路までしばらく歩き、湖岸道路を左に折れて老人ホーム水茎の里の前を過ぎると、左手に「名勝水茎岡」とかかれた石標と階段があります。これを登ると、尾山山頂部へといたる山道へとつづいています。頭山へは湖岸道路の琵琶湖側を山の方に進み、山裾の道を琵琶湖方面に進むと山に登る道があります。道は山頂部までは延びていませんが、「高御座のほらす年のよろこ
ひをしるしととめよ水くきの岡」という御歌所長入江為守の和歌を刻んだ石碑と、その下に「水茎岡山城」と墨書された木の看板が置かれた所に行くことができます。(松下)
 八幡山から見た岡山(右から頭山・尾山・後山)
八幡山から見た岡山(右から頭山・尾山・後山)
尾山は後日にhttp://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/aa033e165e1a250d6e2e1db0a4d82c15
消費カロリー 270.9kcal 脂肪消費量 38.7g
NETに感謝!感涙! ・・・・・・Openされたをblog・HPは、「著作権・肖像権の承諾と」勝手に解釈しております。
blogやHPの管理者様に感涙! 薄知の当blog管理人はとっては、Openされたをblog・HPは世界の知恵袋、大辞典です。
今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました