彦根城外堀の土塁見つかる 市内唯一・・・・(滋賀彦根新聞2015.5.20)
滋賀・彦根城外堀の土塁確認 23メートル原形とどめる
 現存する彦根城外堀の土塁。右上から左奥に向かって23メートルが原形をとどめていることが確認された。左のテントは堀があった場所(彦根市中央町)京都新聞
現存する彦根城外堀の土塁。右上から左奥に向かって23メートルが原形をとどめていることが確認された。左のテントは堀があった場所(彦根市中央町)京都新聞
滋賀県彦根市中央町の彦根城外堀跡で現地調査を進めている彦根市教委は20日までに、外堀の土塁が23メートルにわたり原形をとどめていることを確認した。市教委文化財課は「城の外堀の土塁がそのまま残る例は全国的にも珍しい」としている。
外堀は1615(元和元)年の彦根城第2期工事で建設され、総延長は3・4キロあった。戦後に、蚊の発生を抑え、マラリアの流行を防ぐ目的で埋められた。埋め立ては堀の内側(城郭側)を囲んでいた土塁の土砂を利用したため、土塁はほぼ姿を消したとされていた。

今回調査対象となったのは、銭湯「山の湯」の敷地内で、庭園築山として長年使われていた。台形の丘に見えることから地元では「山」と呼ばれており、外堀の土塁であったことは市内でもほとんど知られていなかった。
市教委は4月から調査を実施。外堀の土塁の高さは内側が5・5メートル、外側は6~7メートル。台形の上部幅は4メートル、基底幅は18メートルあることも確認した。堀の幅は約16メートルで、文書史料の記述や絵図とも一致している、という。市教委の下高大輔主任は「断面から9層になっていることも確認でき、外堀の構造を知る上で貴重な遺構だ」と話す。
市教委は今後、外堀の文化的価値を証明し、どのような保存方法があるか検討する方針。
問い合わせは市文化財課TEL0749(26)5833。
本日も訪問、ありがとうございました!!感謝
















 張り出した木の下から、城道ある
張り出した木の下から、城道ある












 主郭上部狼煙台(動画を撮った為)の写真はこれだけ・・・。
主郭上部狼煙台(動画を撮った為)の写真はこれだけ・・・。
 主郭に背後大堀切
主郭に背後大堀切


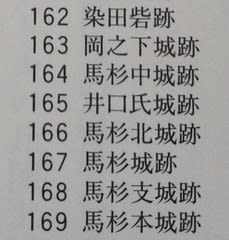
 主郭は方形で土塁で囲う
主郭は方形で土塁で囲う 

 農道を東に進み、突き当りを北へ
農道を東に進み、突き当りを北へ 獣害フェンスから、栢ノ木城(フェンス内は作付け放棄地)のあぜ道を登り口まで
獣害フェンスから、栢ノ木城(フェンス内は作付け放棄地)のあぜ道を登り口まで


























 堀(池)
堀(池)





 駐車位置から遠望
駐車位置から遠望 「
「