

お城のデータ
所在地:長浜市宮司町 map:http://yahoo.jp/6VMuJJ
別 名:宮川氏館
区 分:陣屋
遺 構:城跡碑
築城期:江戸期・・・・・元禄11年(1698)
初城主:堀田正休
訪城日:2015.6.27、2015.10.17

お城の概要
日枝神社の前に宮川陣屋跡を示す石碑が建てられている。現在は、陣屋跡の碑があるのみである(『名城をゆく(小学館)』)。
宮川陣屋は宮川氏館跡に建てられた。石碑の横には十一川が流れ、宮川氏の館が十一川を利用した形で建てられていたことが窺える。
なお、一帯は蔵などの古い家並みが残る。


 番場堀
番場堀 碑
碑
お城の歴史
宮川陣屋は元禄11年(1698)堀田正休が宮川藩の政庁として設けたもので、長浜平野を南北に走る加田街道と東西に走る長浜街道の交差する交通の要所に位置している。元禄十一年(1698)、上野国吉井藩から堀田正休が1万石で入封し、陣屋を構えた。
宮川藩は寛延元年(1748)には3000石を加増され、その領地は坂田郡16か村のほか、他郡21か村に及んだ。(『名城をゆく(小学館)』)。
城主と見られる宮川氏は、『総持寺文書』中の永享5年(1433)屋敷寄進状に宮河光道等の名が見られるのが初見である。更に、総持寺の文書は、同氏が山門領坂田荘の下司・公公であったことも語ってくれる。
その城地として伝えるところはないが、宮司町(宮司は、明治7年宮川と下司が合併して成立)小字古殿が最もふさわしいだろう。この字内には、垣見氏館も含まれるが、元禄11年(1698)堀田正休が宮川藩の政庁として設けた宮川陣屋の跡地も存在する。
この陣屋は宮川氏が田中吉政に従い筑後柳川へ転出した屋敷跡を利用して設けられたと考えることもできるでしょう。
当時の南東端で南川が十一川に合流し、南西端で十一側が分かれており、長浜平野を南北に走る加田街道と東西に走る長浜街道の交差する交通の要所に位置しているが、明治期の地籍図によれば、この二つの道は同字の東端を南北に重複していた事がわかり、宮司町内の元宮川村に属する当字には垣見氏屋敷が知られている。
東隣には元宮川山王と称した楞厳院荘の総社日枝神社があり、地名を姓にもつ宮川氏の屋敷が有ったものと思われる。
宮川氏には永享5年総持寺文書の宮川光道や同11年長浜八幡宮塔供養の宮川又次郎らがいて、上坂に分家した宮川源六は上坂内蔵介に仕えている。
また、古殿の東半分は近世宮川藩の陣屋であったところで、十一川を隔てて満立寺がある。
元禄十一年(1698)、上野国吉井藩から堀田正休が1万石で入封し、陣屋を構えた。
宮川藩は寛延元年(1748)には3000石を加増され、その領地は坂田郡16か村のほか、他郡21か村に及んだ。現在は、陣屋跡の碑があるのみである(『名城をゆく(小学館)』)。 明治4年の廃藩置県により宮川藩は廃された。なお、同町小字古殿内には垣見氏屋敷があったとされている。
宮川藩は元禄11年(1698年)に堀田正休が、上野吉井から近江国甲賀、坂田、蒲生、愛知4郡内に領地を移され、坂田郡宮川に陣屋を構えて成立した藩である。
宮川藩堀田氏は堀田の宗家にあたり、先々代正盛は家光の寵臣として下総佐倉11万石にまで登りつめたが家光に殉死し、二代正信は無断帰国をして除封された。
正信は狂疾とされ、堀田家は正盛の忠義によって家名存続が認められ、正休に上野国吉井でで1万石が与えられ、さらに宮川に移された。
三代正陳は、延享2年(1745年)7月に若年寄、寛延元年(1748年)10月に西の丸若年寄となって近江国野洲郡、滋賀郡内で3千石を加増された。
最後の藩主正養は出羽亀田藩主岩城隆喜の子で堀田家に養子に入り、戊辰戦争では他の近江の小藩同様彦根藩の影響を強く受けて、新政府軍側に立った。
参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城
本日も訪問、ありがとうございました!!。感謝!!

















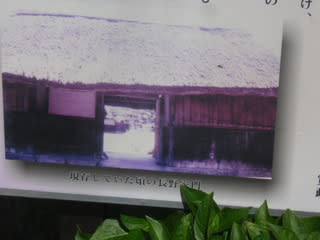 取り壊された長野家
取り壊された長野家





