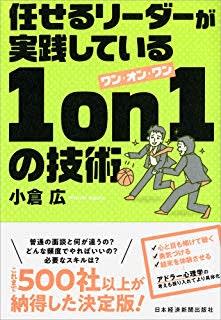任せるリーダーが実践している1on1の技術
クライアント、部下に1対1で向かい合う技術。
①
成長している企業はみんな取り入れ出している。アドラーがもし上司だったら?1on1のコミュニケーション術。
<著者のミッション>
アドラー心理学のカウンセリング技術を経営に活用してもらうことで世界を変える。3
▼
核心:◎ひと言で言うと、これをどう実践,導入するかの本。
ティータイム面談:用事が会ってもなくても週に1回は必ず上司と部下が一対一で,できれば一時間,無理なら30分でもいいので面談をする。4
▼
相互理解がまずはスタート
◎ 目的:
エンゲージメントを高める。経験学習サイクルを高める。30
⇒
★ ★★★★人は知識から学ぶのではありません。経験から知識が導き出されたときにはじめて深い学びが起きるのです。32
▼
組織的なノウハウの共有
経験の言語化
▲②-aなぜ?★★★★★
googleの心理的安全性、日本でのヤフーでの導入
⇒アメリカシリコンバレーでは当たり前で,日本ではクックパッド,カルビー、モノタロウ・・・など成長企業が取り入れている。
▼ googleのチームアリストテレス:◎◎ここ
★★★★★好業績に最も影響を大きく与える因子が「心理的安全性」であったことです。「誰もが均等に話す機会があること」「自由に意見が言える」「否定されない」、これらの条件があることで初めてチームの業績が高まるのです。22
⇒
1on1により、上司と部下の関係の質を向上させ,エンゲージメントを高めることが間接的に業績向上に貢献する。98
解決型マネジメント⇒成長支援型マネジメント
書き出し★★★★★
★ ★★★★人に優しく=信頼。仕事に厳しく=信用。昔から、尊敬される上司は『人に優しく、仕事に厳しく』です。信頼と信用を使い分けてこそ,本物のリーダーとなるのです。197
部下の行為と人格を分離し,部下の失敗と不適切な行為を分離して尊敬することです。部下の可能性を無条件に根拠なく信頼することです。部下に協力しようとすることです。212
②-bマインドセット★★★★★
【課題の分離】
★ ★★★★「私は不適切な行為をしてしまった。しかし、目的は所属であり,善である。私の人格は善である」、このように自分を尊敬するのです。すると他者を尊敬できるようになります。
対人関係の基本は自分との関係と同様です。自分で自分にダメだししている人は,他者に対しても同じようにダメ出しをします。
そうではなく、失敗と不適切な行為を分離し,二度見(respect)するのです。そして、さらに行為と人格を分離し,もう一度二度見するのです。それを自分に対しても実施する。それが相互尊敬の状態です。191
★ ★★★★0-0-
1on1において時間のほとんどは「聴く」に費やされることになります。神様は人間に口を1つ、耳を2つ授けました。つまり、話す2倍聴きなさい、という教えである、と言われています。その際,ただ漠然と耳で聞くのではなく、「目と耳と心で聴く」になります。151
★★★★★共同体感覚は、アドラーが「導きの星」と呼び「あらゆる問題の原因は共同体感覚の欠如にある」と述べた、治療と教育の目標です。ひと言で言うならば,「自分さえ良ければいい」と他者に迷惑をかけるのではなく、「私だけでなく、周囲の人たちの一緒に幸せになる」協力的な方法を探す態度のことです。184
◎ アドラー心理学的な万人に共通する究極目標:社会への所属38
「さて、これからどの話をしますか?『悪いあの人』『かわいそうな私』『これからどうする』の3つから選んでみよう」、このようにあらかじめ話題の選択をさせると、ほとんどの相手が「これからどうする?」を選びます。批判やグチを言っても生産性が低いということに気づくからです。95
コア◎◎
【1on1はアドラー心理学をベースにした上司と部下のコミュニケーションスタイル】
◎良好な人間関係の4条件=「尊敬」「信頼」「協力」「目標の一致」181
★ ★★★★頼まれてもいないのに手伝うような(距離が近すぎる)過干渉でもなく、放ったらかしの(距離が遠すぎる)放任でもない,相手の自主性や主体性を邪魔せずに,しかし(適切な距離で)きちんと協力をするのです。144
★ 問題や原因意フォーカスせずに,未来の解決にアプローチしていくユニークな技法。144
②-c★★★★★項目+α
⇒必要な5つのスキル
1傾聴:相手の話を注意深く共感し丁寧に聴く◎
⇒カウンセリング,コーチングの基本
相手の話をジャッジせず無条件に肯定的に聴く
あなたはそう考えるのですねと相手の立場を共感的に理解すること
あるべき自分と現実の自分が乖離せず自然体で一致していること。114
2勇気づけ:
★★★★★貢献伝達,正のフィードバック、感謝、共感的理解141
自分には能力があり,周囲の人は仲間であるという感覚を育てる
⇒
相手のプラス面に注目し,自らもプラスの感情を持って相手と接する。116
3質問:効果的な質問をすることで、部下が自ら考えるきっかけを生み出す
4フィードバック:目標と部下の行動とのギャップを伝える
5結末を体験させる:相手に答えを教えるのではなく,失敗を含めた経験もしてもらい、そこから学んでもらう。
⇒成功体験に限らず失敗体験もまた、貴重な学びに満ちていると考える。130
クライアント、部下に1対1で向かい合う技術。
①
成長している企業はみんな取り入れ出している。アドラーがもし上司だったら?1on1のコミュニケーション術。
<著者のミッション>
アドラー心理学のカウンセリング技術を経営に活用してもらうことで世界を変える。3
▼
核心:◎ひと言で言うと、これをどう実践,導入するかの本。
ティータイム面談:用事が会ってもなくても週に1回は必ず上司と部下が一対一で,できれば一時間,無理なら30分でもいいので面談をする。4
▼
相互理解がまずはスタート
◎ 目的:
エンゲージメントを高める。経験学習サイクルを高める。30
⇒
★ ★★★★人は知識から学ぶのではありません。経験から知識が導き出されたときにはじめて深い学びが起きるのです。32
▼
組織的なノウハウの共有
経験の言語化
▲②-aなぜ?★★★★★
googleの心理的安全性、日本でのヤフーでの導入
⇒アメリカシリコンバレーでは当たり前で,日本ではクックパッド,カルビー、モノタロウ・・・など成長企業が取り入れている。
▼ googleのチームアリストテレス:◎◎ここ
★★★★★好業績に最も影響を大きく与える因子が「心理的安全性」であったことです。「誰もが均等に話す機会があること」「自由に意見が言える」「否定されない」、これらの条件があることで初めてチームの業績が高まるのです。22
⇒
1on1により、上司と部下の関係の質を向上させ,エンゲージメントを高めることが間接的に業績向上に貢献する。98
解決型マネジメント⇒成長支援型マネジメント
書き出し★★★★★
★ ★★★★人に優しく=信頼。仕事に厳しく=信用。昔から、尊敬される上司は『人に優しく、仕事に厳しく』です。信頼と信用を使い分けてこそ,本物のリーダーとなるのです。197
部下の行為と人格を分離し,部下の失敗と不適切な行為を分離して尊敬することです。部下の可能性を無条件に根拠なく信頼することです。部下に協力しようとすることです。212
②-bマインドセット★★★★★
【課題の分離】
★ ★★★★「私は不適切な行為をしてしまった。しかし、目的は所属であり,善である。私の人格は善である」、このように自分を尊敬するのです。すると他者を尊敬できるようになります。
対人関係の基本は自分との関係と同様です。自分で自分にダメだししている人は,他者に対しても同じようにダメ出しをします。
そうではなく、失敗と不適切な行為を分離し,二度見(respect)するのです。そして、さらに行為と人格を分離し,もう一度二度見するのです。それを自分に対しても実施する。それが相互尊敬の状態です。191
★ ★★★★0-0-
1on1において時間のほとんどは「聴く」に費やされることになります。神様は人間に口を1つ、耳を2つ授けました。つまり、話す2倍聴きなさい、という教えである、と言われています。その際,ただ漠然と耳で聞くのではなく、「目と耳と心で聴く」になります。151
★★★★★共同体感覚は、アドラーが「導きの星」と呼び「あらゆる問題の原因は共同体感覚の欠如にある」と述べた、治療と教育の目標です。ひと言で言うならば,「自分さえ良ければいい」と他者に迷惑をかけるのではなく、「私だけでなく、周囲の人たちの一緒に幸せになる」協力的な方法を探す態度のことです。184
◎ アドラー心理学的な万人に共通する究極目標:社会への所属38
「さて、これからどの話をしますか?『悪いあの人』『かわいそうな私』『これからどうする』の3つから選んでみよう」、このようにあらかじめ話題の選択をさせると、ほとんどの相手が「これからどうする?」を選びます。批判やグチを言っても生産性が低いということに気づくからです。95
コア◎◎
【1on1はアドラー心理学をベースにした上司と部下のコミュニケーションスタイル】
◎良好な人間関係の4条件=「尊敬」「信頼」「協力」「目標の一致」181
★ ★★★★頼まれてもいないのに手伝うような(距離が近すぎる)過干渉でもなく、放ったらかしの(距離が遠すぎる)放任でもない,相手の自主性や主体性を邪魔せずに,しかし(適切な距離で)きちんと協力をするのです。144
★ 問題や原因意フォーカスせずに,未来の解決にアプローチしていくユニークな技法。144
②-c★★★★★項目+α
⇒必要な5つのスキル
1傾聴:相手の話を注意深く共感し丁寧に聴く◎
⇒カウンセリング,コーチングの基本
相手の話をジャッジせず無条件に肯定的に聴く
あなたはそう考えるのですねと相手の立場を共感的に理解すること
あるべき自分と現実の自分が乖離せず自然体で一致していること。114
2勇気づけ:
★★★★★貢献伝達,正のフィードバック、感謝、共感的理解141
自分には能力があり,周囲の人は仲間であるという感覚を育てる
⇒
相手のプラス面に注目し,自らもプラスの感情を持って相手と接する。116
3質問:効果的な質問をすることで、部下が自ら考えるきっかけを生み出す
4フィードバック:目標と部下の行動とのギャップを伝える
5結末を体験させる:相手に答えを教えるのではなく,失敗を含めた経験もしてもらい、そこから学んでもらう。
⇒成功体験に限らず失敗体験もまた、貴重な学びに満ちていると考える。130